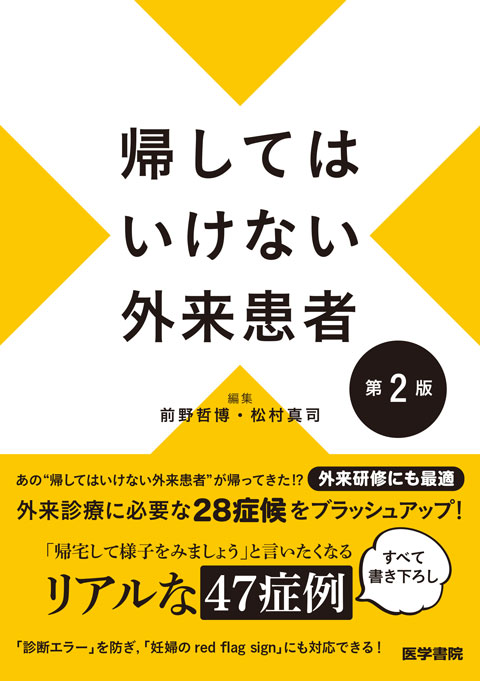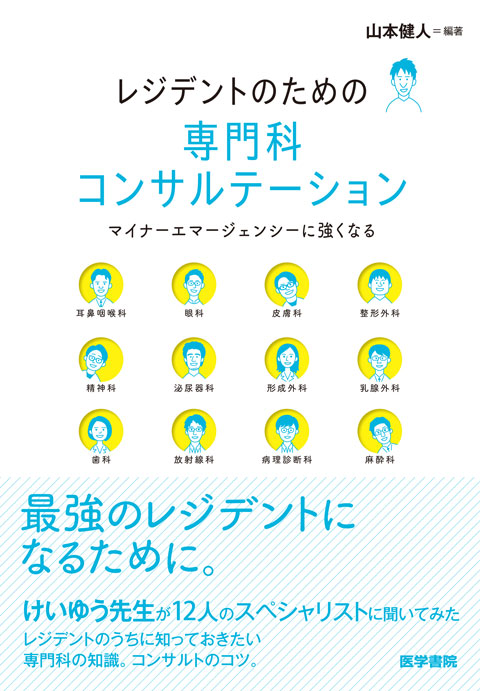MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.12.06 週刊医学界新聞(レジデント号):第3448号より
《評者》
坂本 壮
総合病院国保旭中央病院救急救命科医長
臨床研修センター副センター長
リアルなあるある症例からピットフォールを学ぼう
“人は,変えられるのは未来だけだと思い込んでいる。だけど,実際は,未来は常に過去を変えてるんです。”
私は主に救急外来で仕事をしている。救急というと多発外傷やショック,心肺停止など,死に瀕している患者さんばかりが来院すると思われがちだが,そんなことはない。『救命病棟24時』『コード・ブルー―ドクターヘリ緊急救命―』,最近では『TOKYO MER~走る緊急救命室~』,『ナイト・ドクター』など,「おいおい,こんな若手がそんなことを,それも美男美女ばかりが……」てな感じの突っ込みどころ満載ながらも楽しいドラマに出てくるような症例はまれだ。リアルな救急外来で出合う症例の多くは,発熱,呼吸困難,意識障害,意識消失,めまい,何らかの痛みなどを主訴に来院し,バイタルサインはおおむね安定している。最近では,高齢者が動けない,元気がない,食欲がないといった症例も多く,病歴聴取や身体所見の評価に苦渋しながら,みんな対応しているだろう。
限られた時間,資源の中で多くの患者さんを同時に見ることが要求される救急外来ではエラーが起こりがちである。振り返ってみると,そこには見逃してはいけないはずの訴えや検査結果がきちんとあるにもかかわらず,だ。それには,さまざまな認知バイアスが影響していて,知識不足以上の要因となっているとされる。しかし,当然のことながら知識は大切である。特にわが国では初期研修医など若手の医師が救急外来を担うことが多く,彼らが陥るエラーは誰もが経験するエラーであることがほとんどだ。嘔気や体動困難という主訴から心筋梗塞を想起できなかった,来院時には痛みの程度が軽度であったため大動脈解離やくも膜下出血を問診の段階で除外してしまった,外傷の背景に潜む内因性疾患を意識しなかった,X線のみで骨折を否定してしまったなど,あるあるはたくさんある。
本書『帰してはいけない外来患者 第2版』は,第1章「外来で使えるgeneral rule」,第2章「症候別general rule」,第3章「ケースブック」で構成され,外来診療で頻度の高い症候の一般的なアプローチを解説するとともに,陥りやすい点をケースを通じて学ぶことができる。第3章のケースブックは47症例と豊富だが,そのどれもが「こんなこともある」というレアケースではなく,非典型的なように見えて実は典型的といった症例ばかりで,病歴や身体所見,バイタルサインの重要性がひしひしと伝わってくる。私のお勧めは第3→1章の逆読みだ。症例であるあるとうなずきながら一般的なアプローチを振り返るのだ(症例でうんうんうなずけない場合には,第2章から読むとよいだろう)。第1章,前野哲博先生の「外来で使えるgeneral rule」は外来特有の臨床決断の思考ロジックを,和足孝之先生の「外来で必要な診断エラーの知識」では認知バイアスまで学ぶことができてしまうという,お得感満載である。
冒頭のセリフは映画化もされた平野啓一郎著『マチネの終わりに』の一節である。過去に起こった出来事,それ自身は変えられなくても,その経験から成長していくことができれば,過去も変わるのではないだろうか。本書から学び,実臨床で生かしていただきたい。
《評者》 倉原 優 国立病院機構近畿中央呼吸器センター 呼吸器内科
“盗んだバイク”で走り出す本
若手医師に限った話ではないが,臨床医を続ける以上「専門科にコンサルトすること」と「患者に病状説明すること」は避けて通れない。その技術は,一朝...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。