夏休み読書特集
医学生・研修医のためのベッドサイド「漫画」ライブラリー
寄稿 川上 英良,權 寧博,髙尾 昌樹,北 和也,山本 舜悟,林 寛之
2021.08.09 週刊医学界新聞(レジデント号):第3432号より
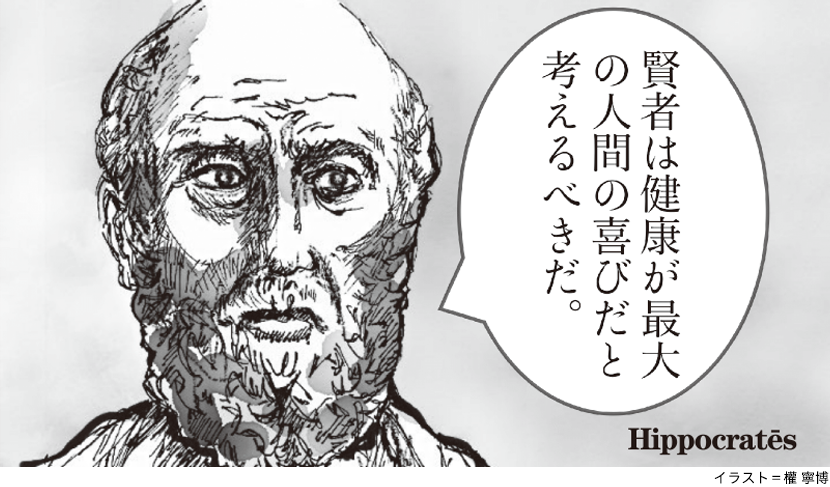
慌ただしい毎日を送る医学生・研修医の皆さんの中には,「休日の漫画タイムが癒やし!」という方も多いのではないでしょうか。漫画は娯楽の域を超え,研究分野を決める手掛かりや仕事をする上での心の戒めを見つけるきっかけにもなり得ます。
本紙では,漫画愛好家かつ医学の第一線で活躍する方々から,お薦めの漫画を3冊ずつご紹介いただきました。「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスも,現代に生きていたら漫画から医師の矜持を学んでいたかも(?)。ぜひ,夏のステイホームのお供を探す参考にしてください!

川上 英良
千葉大学大学院医学研究院
人工知能(AI)医学 教授
①『ARMS』皆川亮二
②『僕だけがいない街』三部けい
③『ワールドトリガー』葦原大介
現在AI・機械学習を用いた医科学研究を行っている私は,2001年の大学入学当時からAIに興味を持っていました。これは,漫画をはじめとするSFに大きな影響を受けています。SFはエンターテインメントであると同時に,未来の世界を思い描く手掛かりだと思います。ここでは,そんなSF漫画を3作品紹介します。
①事故に巻き込まれて失った腕にナノマシンを移植された主人公が,世界を陰で支配する秘密結社と戦うSF漫画。ナノマシンをはじめサイボーグや遺伝子改変といったさまざまな技術が次々に登場したり,秘密結社を支配しているのが開発者を取り込んだAIだったりとSF要素の見本市のような作品。私がちょうど高校生の時に連載されており,相当影響を受けています。SF要素以外にも,自宅の押入れからおもむろに機関銃を取り出す主婦とか,サイボーグを素手でなぎ倒すサラリーマンとか,個性的な登場人物も魅力です。
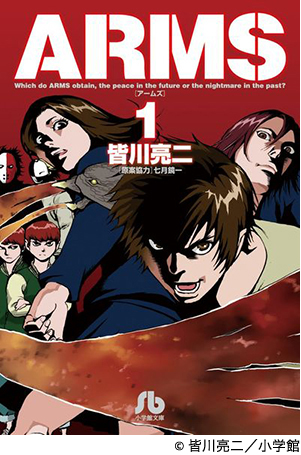
②タイムリープ能力を持つ主人公が現在と過去を行き来して,幼少期に起きた連続誘拐殺人事件を阻止するSFサスペンス漫画。周到で狡猾な真犯人との一進一退の駆け引きが緻密に描かれており,手に汗を握ります。
タイムリープものは未来の記憶を持った主人公が過去に戻るということで,何かとご都合主義に陥りがちですが,本書は綿密なプロットによってサスペンスとしても完成度が高いです。昭和後期へのタイムリープということもあり,自分自身が幼少期に感じた探検や秘密基地のワクワク感を思い出しました。
③異世界からの侵略者と戦う防衛組織を描いたSFアクション漫画。『週刊少年ジャンプ』連載のアクション漫画は強さのインフレが起こりがちですが,本書は「トリガー」と呼ばれる武器の特性や登場人物ごとの特殊能力を組み合わせて一見格上の相手を攻略するといった頭脳戦が秀逸。異世界から侵略が行われる背景や防衛組織ができた経緯などが非常に丁寧に描かれており,派手さはないもののジワジワと魅力が出てくる作品です。キャッチコピーは「遅効性SF」。
*
「人間が想像できることは,人間が必ず実現できる」とは,SF作家・ジュール・ヴェルヌの名言です。これらの作品を読みつつ未来の社会に思いを馳せるのも一興かと思います。

權 寧博
日本大学医学部内科学系・
呼吸器内科学分野 教授
①『火の鳥』手塚治虫
②『アドルフに告ぐ』手塚治虫
③『100日後に死ぬワニ』きくちゆうき
最近の医学生は,私の頃よりも授業や国家試験対策などで忙しそうで,気の毒に感じることさえあります。スマホが登場し,読書時間も減っていると想像します。今回私が紹介するのは漫画ですが,最近の学生の漫画を読む時間は,私たちの頃と比べて変わっているのでしょうか。漫画を読む習慣というのは,個人差が大きいので把握しにくいかもしれませんね。
①②私が医学生の頃は,『ブラック・ジャック』を読んで医者になった先輩や仲間が少なからずおりました。最近の医学部の面接で,『Dr.コトー診療所』や『医龍』などを読んで医者になることを決めたと,志望動機を語る学生はそれほど多くないはずです。当時の受験生が,面接で『ブラック・ジャック』を医師志望動機に挙げることに躊躇せず,面接官もそれに納得するという芸術作品級の扱いを受けていたという点でも,手塚治虫が稀代の漫画家だったことを物語っています。ちなみに,私自身は『火の鳥』のほうが印象に残っており,『ブラック・ジャック』に心酔するという経験はしておりませんが,手塚作品の文芸性を知ることができるという点で,ここでは『アドルフに告ぐ』という作品を紹介したいと思います。
主人公は,第二次世界大戦時下に,神戸に住む2人のアドルフという名の少年たちです。2人はそれぞれ,ゲルマン民族とユダヤ人として生まれ,時代に翻弄されて行く様を手塚治虫がドラマタッチに描いております。作品を読み進めるうちに,ふと気付くと漫画を読んでいるのか,小説を読んでいるのか,映画を観ているのか,頭の中で混乱を来す感覚を経験します。そこに,漫画を芸術の域に高めた,手塚治虫の高いポテンシャルを感じることができます。本書で手塚は,戦争時下での人々の狂気と人間の愚かさを描き出しています。また,この物語は史実に基づいて展開されております。歴史の結末を既に知る読み手に,登場人物たちが出口のない閉塞感のなかで必死にもがき続ける様を見せることで,戦争の不条理や時代の空気感がより強調されるという効果を生み出しています。
③物事をカウントダウンの視点から見ると,物語の情景は全く違って見えます。最近,『100日後に死ぬワニ』という漫画が話題になりましたが,「死まであと○日」との表記があると,平凡な日常の情景の見え方も変化します。
死を終わりとして考えると,人生そのものはカウントダウンで進んでいきます。私も年齢のせいか,最近はカウントダウン目線で物事を見るようになってきて,若い時とは考え方の根本が変わってきました。医学生や研修医の皆さんは,若いのでカウントアップの目線で日常を見ているのではないでしょうか。どちらが良いかという話ではありませんが,カウントアップの方が大きな情熱や成長のチャンスが生まれやすく,若い時はそれで良いのだと思います。カウントアップのほうが,カウントダウンよりも時間が長く感じられることを証明した研究もあるそうです1)。
さて,最近の学生や研修医は,安定志向や研究意欲の低下,海外留学希望者の激減など,自身の進路選択がカウントダウン目線で現実的過ぎるとの意見をよく耳にします。取り巻く制度設計にも少しは原因がありそうですが,皆さんのお考えはいかがでしょうか。
参考文献
1)高橋怜央,他.カウント方向が時間評価へ及ぼす影響.日心理会発表論集.2014;78:650.

髙尾 昌樹
国立精神・神経医療研究センター病院
臨床検査部・総合内科 部長
①『こちら葛飾区亀有公園前派出所』秋本治
②『きりひと讃歌』手塚治虫
③『がんばれ! 猫山先生』茨木保
①知らない人がいるとは思えないけれど,お若い先生は読んだことがないかもしれませんね。デビュー当初の作者のペンネームは,『がきデカ』の作者「山上たつひこ」さんに似た,「山止たつひこ」でした。1976年から連載が始まって,2016年まで連載が続いたので,私に例えると小学校5年生から,医師26年目までです。小学校で友達から借りて読んだのが最初でした。今読んでみると,当時,どんなことが流行っていたのかがよくわかります。作中に出てくるアイデアが,その後実現したことも多く,本当にすごい漫画です。絵の細部もさまざまなこだわりがあって,読むたびに新たな発見があります。いろいろ余裕があった時代です。お仕事に疲れた時にぜひ読んで明日への活力を。
②学生,研修医の方,ぜひ読んでください。四国の山間の風土病にまつわるお話です。1970年に発表された本作を私が読んだのは医学部6年生の時(1989年)でした。当時は単純に医学にかかわる内容が面白かったことを記憶していますが,今回,あらためて読み直してみると,随分異なった印象を持ちました。大学医局,医師の保身など,なんかよくある話のような気もして(笑)。作中に出てくるカシン・ベック病という風土病が,いまだに解明されて...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
