予防接種政策の推進に不可欠な安全性モニタリングシステム
日本版VSDの構築をめざして
対談・座談会 福田 治久,紙谷 聡
2021.07.19 週刊医学界新聞(通常号):第3429号より
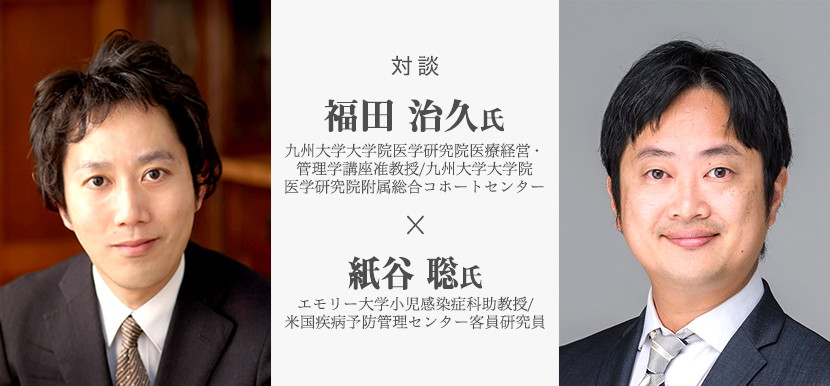
「ワクチンを接種後,○人が死亡」――。新型コロナワクチンの接種が進む中,時にはセンセーショナルにこうした報道がなされる。そして厚労省の検討部会では「因果関係が評価できない」との判定が下されることが多い。こうした事例の中には,基礎疾患や死因等を総合的に判断すればワクチンが原因である可能性は極めて低い状況も含まれているのにもかかわらずだ。その根本的な原因として,ワクチン接種と有害事象の因果関係を検証できない,日本の現行システムの限界が挙げられる。
米国疾病予防管理センター(CDC)には30年以上の実績を持つ予防接種安全性モニタリングシステムが存在しており,その最前線で活躍するのが紙谷聡氏だ。そして日本でもAMED研究として,ワクチンの有効性・安全性の検証が可能な大規模データベース構築が模索されており,福田治久氏が研究を推進する。本対談にて両氏が,国際標準の予防接種安全性モニタリングシステムの日本での構築に向けた展望を語った(関連記事)。
福田 私は,自治体保有の医療・介護・保健・行政データを収集・統合しコホート研究を行うLIFE Study(MEMO)を実施しています。この研究プロジェクトの一環として現在,AMED研究事業「保健・医療・介護・行政データを統合した大規模データベースを活用したワクチンの有効性・安全性の検証に資する研究開発(以下,AMEDワクチン研究)」(2021~23年度,研究代表者=福田治久氏)に取り組んでいるところです。
研究計画段階で各国のワクチンの有効性・安全性評価システムを調べたところ,米国や英国,北欧諸国などでは,予防接種歴と医療記録を合わせたデータベースが既に構築されていることを知りました。そして米国CDCで安全性モニタリングを統括する部署では,なんと日本人医師が活躍している。そんな情報を得て,紙谷先生にはぜひお話を伺いたかった次第です。
紙谷 AMEDワクチン研究の話は私も耳にしていました。その研究代表者の福田先生との対談がかない,うれしく思います。実は私が渡米しその後はCDCに参画することになったのは,まさに安全性モニタリングシステムこそが,日本の予防接種の未来に不可欠なものであるという確信を得たからなのです。
因果関係を検証できない「副反応疑い報告制度」の限界
紙谷 私が日本で小児科医として診療していた2010年代前半,ワクチンで予防できるはずの疾患にかかった子どもをたくさん診てきました。それで小児感染症と予防接種について学びたいという想いから,渡米を果たしたのが2015年です。
福田 その後,どういった経緯で安全性モニタリングの問題にたどり着いたのでしょうか。
紙谷 私の問題意識のひとつとして,ヒトパピローマウィルス(HPV)ワクチンの件がありました。一向に積極的勧奨の再開に向かわない日本の状況を米国の医師と議論する中で,日本の安全性モニタリングシステムの限界に気付いたのです。
福田 日本には副反応疑い報告制度があり,副反応の疑いがある事象を発見した場合に医師が厚労省に報告する仕組みになっています。
紙谷 受動的モニタリングの一種であり,米国のVAERS(Vaccine Adverse Event Reporting System)に相当しますね。この制度は運用が比較的容易で途上国も含め多くの国が採用しており,安全性への懸念をシグナルとして迅速に検出できるなどの利点があります。ただし最大の欠点として挙げられるのは,因果関係の検証ができないこと。厚労省はワクチン接種後の死亡例を検証しているものの,実際には「ワクチン接種との因果関係が評価できない」と報告されることがほとんどです。
これは一般の人には誤解されやすく,「予防接種後に〇〇が起こった」という前後関係が,「ワクチンが原因で〇〇が起こった」という因果関係にすり替わってしまう危険性を伴う。特に日本は,一部メディアのセンセーショナルな報道が,その危険性を助長しています。
福田 先述のHPVワクチンの問題では,厚労省が「副反応に関する十分な情報提供ができるまでは積極的勧奨を一時差し控える」と決定したものの,因果関係の検証は困難を極めました。その後は名古屋スタディ(Papillomavirus Res. 2018[PMID:29481964])によってワクチン接種と副反応の関連性が否定される形で,科学的には一定の結論に達したと言ってよいのかもしれません。しかし市長のリーダーシップと疫学研究者らの努力がなければ,あれほどの手間と費用をかけて調査を行うことは不可能だったはずです。
紙谷 しかも論文は2018年掲載で,HPVワクチンの問題が表面化した2013年から5年もたっています。そして大変な労力にもかかわらず,匿名郵便によるアンケート調査という研究デザインの限界もあるのではないでしょうか。
福田 確かに,もし前向きコホート研究などの形で研究デザインを組めたなら,学術的なインパクトはさらに大きかったはずです。
紙谷 いずれ時を経て,HPVワクチンの積極的勧奨は再開されるかもしれません。しかし新しいワクチンが導入されるたびに,同様の事態が生じるリスクをはらみます。やはり各事例の「木」ばかりを見ていてはどう頑張っても因果関係の評価は難しく,疫学的に集団全体を観察する,すなわち「森」を見て評価する必要があります。「森」をみるために米国で創設されたシステムが,VSD(Vaccine Safety Datalink)なのです。
私自身は...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

福田 治久(ふくだ・はるひさ)氏 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座准教授/九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター
2004年慶大商学部卒。09年京大大学院医学研究科社会健康医学系専攻博士後期課程修了。博士(社会健康医学)。医療経済研究機構主任研究員などを経て13年より現職。専門は医療経済学,データベース疫学研究。19年以降は,自治体保有の医療・介護・保健・行政データを住民単位で統合してコホート研究を行うLIFE Studyを推進している。

紙谷 聡(かみだに・さとし)氏 エモリー大学小児感染症科助教授/米国疾病予防管理センター客員研究員
2008年富山大医学部卒。国立成育医療研究センターなどを経て15年に渡米。現在はエモリー大にて小児感染症診療に携わる一方,NIAID主導ワクチン治療評価部門(Vaccine and Treatment Evaluation Unit)の共同研究者としてCOVID-19ワクチンなどの臨床試験に従事。さらにCDC予防接種安全評価室客員研究員としてVSD(Vaccine Safety Datalink)に所属し,認可後のワクチンの安全性モニタリングを行っている。21年より現職。日本・米国小児科専門医。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
