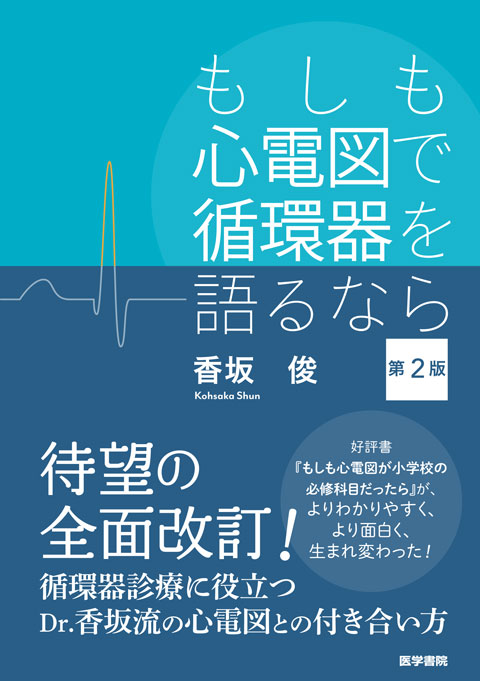シリーズ この先生に会いたい!! 香坂俊氏に聞く
納得いくまで診療を突き詰める
インタビュー 香坂 俊,荻原 壽弘,小泉 明子
2021.07.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3428号より

循環器医として米国で研鑽を積んだ後,国内で診療に従事しながら多数の臨床研究の実施や後進の育成,書籍の執筆と多方面で活躍する香坂俊氏。しかし豊富な実績から想起されるイメージとは裏腹に,「臨床研究は最初,受け身的に始めた」「留学は目的を持ってすべき」と語る。では一体何が香坂氏を駆り立てるのか。荻原壽弘さん(東大医学部4年)と小泉明子さん(旭川医大4年)がインタビューを行った。飽くなき日々の挑戦は,核となる矜持を貫いた結果,もたらされた。
小泉 私が現在関心を抱いている「海外での研修」「臨床研究」の分野で,よく先生のお名前を拝見します。香坂先生がさまざまな実践を続ける上では,どのような思いが原動力となっているのですか。
香坂 教育や研究を通じて医療に貢献したいという思いは,キャリアの後のほうでようやく強くなったというのが正直なところです。最初は,「学んで実践している医療が本当に正しいのか」を知りたいという気持ちが一番でした。学生の頃,そうした「正しい医療」は図書館に行けばわかると考えていましたが,現場に出てみるとそうはいかなかったのです。
EBMは当時「根拠に基づく医療」として広まり始めていたものの,医療ではそもそもその「根拠」が曖昧なところが多く,また「根拠」があったとしても現場ではその受け止めにかなりの温度差があることに気付かされました。
診療の根拠を突き詰めるため米国での研修を決意
香坂 例えば,横須賀米海軍病院で整形外科の研修をしていた時のことです。スキー場での休暇中,大腿骨頸部を骨折した米兵さんがいました。運び込まれた現地の病院で,まずは保存的に牽引療法が選択されたとの一報が入りました。すると米海軍病院の整形外科医は,その病院から患者をすぐに搬送するよう指示を出しました。結果当直だった私が現地に向かい,搬送後直ちに緊急手術が実施されたのです。
荻原 なぜ初診を覆し,緊急手術が実施されたのでしょうか。
香坂 大腿骨頸部骨折では時間を置けば置くほど合併症リスクが高くなることが当時からわかっており,何をおいてもすぐに手術するというのが「根拠」に基づく判断だったのです(現在の診療ガイドラインでも48時間以内の整復手術を推奨)。その時の整形外科医が,「エビデンスがあれば行動するのは当然のことだ」とおっしゃっていたのを今でも覚えています。
荻原 広く一般的とされていた治療が,「根拠」によってアップデートされていたのですね。
香坂 ええ。治療の根拠を個人や施設の経験だけで済ませては駄目だと学びました。臨床現場では,医師の判断ひとつで患者さんの容体が急変します。そうした時,周囲は仕方がないとフォローしてくれますが,「本当にこの判断で良かったのだろうか。何か自分が知らない選択肢があったのではないか」と考えるようになりました。
その後2年目は国内の病院で研修しましたが,「根拠」について事細かに聞くのが癖になっていたため,周りにはさぞかし迷惑な研修医だったのではないか,と今は思います(笑)。しかし海外の論文やガイドライン等を基に質問をしても,ここは日本だから当てはまらないのではないかと曖昧な結論に終始することがどうしても多かったですね。
小泉 そうした経験が積み重なり,留学を決意されたのでしょうか。
香坂 そうですね。このまま続けても,いずれ自身の診療に納得がいかなくなるのではと感じました。エビデンスベースの臨床を実践している米国での研修に,徐々に焦点が絞られていったのです。
さらに,その頃には循環器内科に進もうとはっきり決めていたので,症例が多い米国で経験を積んだほうが,患者さんに提供できる知識やスキルが増えるとも感じていました。
巨人の肩に乗って議論は若手より始めよ
小泉 私は海外への留学に興味があり,医療者の留学に関する情報を発信するNPO法人に所属しています。米国の医学教育では,どのような点が特に印象的でしたか。
香坂 診断や治療判断の「結論」ではなく,その結論に至る「プロセス」の説明が求められる点です。
カンファレンスの際,日本でもS(subjective:主観的情報)とO(objective:客観的情報)の収集までは研修医が実施し,プレゼンテーションがなされます。米国の場合は,その後のA(assessment:評価)とP(plan:計画・治療)についても学生や研修医が立案します。当然最初は酷評されますが,その分伸びるのは早い。日本の場合,A/Pを立案するのは報告を受けた中堅以上の医師であり,研修医が自ら考えて行動を起こすことは求められていません。これでは若手が「指示待ち」状態であり,技量は伸びませんし,モチベーションも低下します。
荻原 米国では若手が主体的に動くと。
香坂 ええ。学生・研修医の判断を基にして,治療方針の議論が日々進められるのです。米国の教育システムは「医師を短期間で効率的に育てる」点で,今のところは世界一でしょう。
小泉 私は現在医学部4年で臨床科目の学習が始まったばかりです。経験の少ない学生や研修医が診療方針を組み立てるのは難しいことではないですか。
香坂 もちろん大変です。それに加えて自分より経験と知識を備えた上級医に対し,判断を述べるのは重圧に感じ緊張もするでしょう。私も慣れないうちは病院に行くのが苦痛でした。しかし,このステップを踏むかどうかで,後の成長度合いが大きく変わります。
荻原 ベテランの医師を前に,若手にできることは何でしょう。
香坂 経験ではかないませんから,論文を引き「巨人の肩に乗る」ことです。特に臨床研究の原著論文は,フォーカスされた臨床上の問題解決を目的に執筆されたものですので,診療方針を決めるための大きな武器となります。米国では学生や研修医の時からエビデンスベースの医療を徹底しています。
多数の学生や研修医が同時にローテートする日本では,一人ひとりに割ける時間が限られてしまい,こうした能動的な役割を期待するのは難しいのが現実です。しかし,経過報告で済ませるのではなく,SOAPのA/Pまで立案してもらう習慣は見習うべきと考えています。
日米のEBMの実践に立場による相違
小泉 香坂先生は専修を経て,そのまま米国で循環器内科医として勤務した後に帰国されました。米国での経験により,日本の医療への見方に何か変化は生まれましたか。
香坂 EBMの実践は米国で学びましたが,患者さん一人ひとりに対しエビデンスをtaylormade(個別化)する重要性は,日本に帰国しなければわからなかったでしょう。欧米はエビデンスを「創る」立場にあるので,強い推奨のエビデンスが出たらそのままためらうことなく実践します。一方日本はエビデンスを「輸入する」側にいますから,その実践に関してはかなり慎重で,経験や安全性をより重視しているように感じました。
荻原 日米の医療に双方の良さを実感した香坂先生は,どちらをより実践すべき医療だと考えていま...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

香坂 俊(こうさか・しゅん)氏 慶應義塾大学医学部循環器内科 専任講師
1997年慶大医学部卒。国内での研修後,99年に渡米しColumbia大,Baylor大で研修。Columbia大循環器内科スタッフ(臨床講師)を経て2008年に帰国。循環器領域の医療の質や臨床アウトカムに関する臨床研究を専門とし,12年慶大に医療科学系大学院(臨床研究)開設。東大医療品質評価講座特任研究員,AMED Program Officer,Stanford大Visiting Scholarをそれぞれ併任。近著に『もしも心電図で循環器を語るなら 第2版』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。