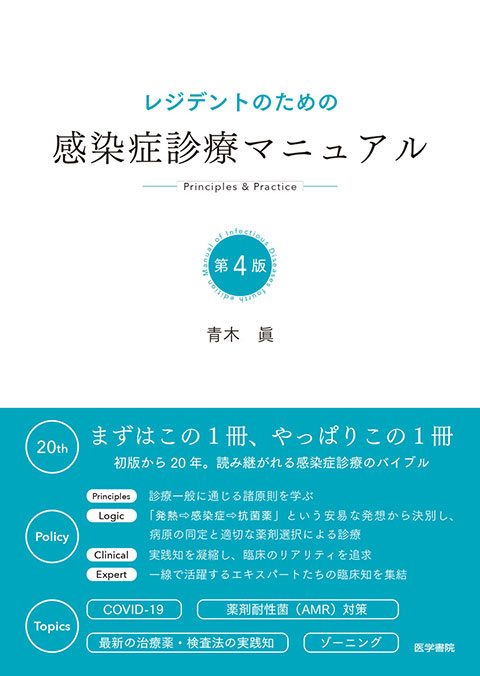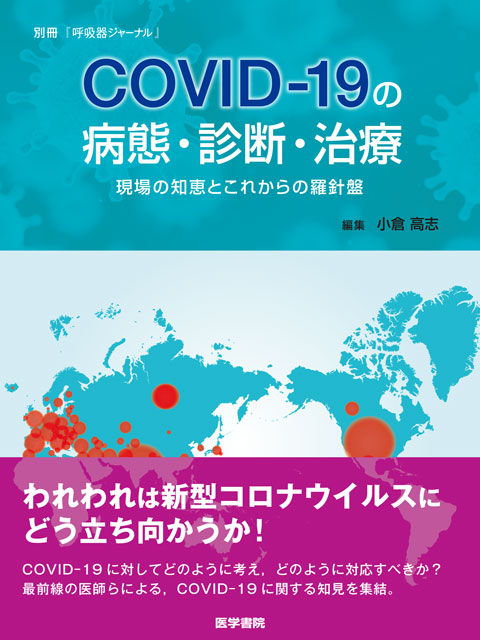MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.03.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3411号より
《評者》 岩田 健太郎 神戸大大学院教授・感染治療学/神戸大病院感染症内科
全ての医療者のために
本書の第3版が出たときも書評を書かせていただいたが(2015年),力を込めすぎついつい長文になってしまった。今回は「800~1400字で」,と編集部から注文がついている。宴席でスピーチが長すぎるおじさんがあらかじめくぎを刺されている様相だが,その「宴席」もいずれ死語になるやもしれぬ今日このごろだ。
というわけで,今回は短く書かせていただく。
結論を先に申し上げる。本書初版が2000年に出版されていたのは本当に僥倖であった。さもなくば,日本の医療は現在直面するパンデミックの厄災に到底,耐えきれなかったであろう。今(2021年1月),日本の医療は何とか持ちこたえている状況(hang in there)だ。それを支えている全国の感染症対策のキープレイヤーたちのほとんどが,青木眞先生の「マニュアル」で学んだいわば同門の徒だ。本書がなかった世界を想像すると本当にぞっとするのだ。
全ての特定の感染症診療方法は,基本的な感染症診療方法の応用問題にすぎない。COVID-19ももちろん,例外ではない。逆に,基本的な感染症診療を無視した形で質の高いCOVID-19診療遂行は到底不可能だ。これは感染防御という観点からも同様だ。例えば,ゾーニングとか防護服(PPE)とかを実践し,マニュアルに組み込むことは誰にでもできる。が,「原則」を無視したままでそれを行うと,PPEを着用したままでレッドゾーンからグリーンゾーンに無邪気に歩き出たりする(p.1597)。院内感染のリスクも考えずに「ちょっと胸の画像を見てみたいから」とCTをオーダーしたりする。そのCT画像が,診療に変化を及ぼすことがない場合にもかかわらず,だ。治療薬の選択も「耳学問」的であり,アドホックに「ネットに書いてあった」治療を試してみたりする。例えば,炎症が激しいのだからと(推奨されていない)ステロイドパルス療法を試みて,そのために不要な合併症を起こしたりする。
こうした誤謬は全て感染症診療の「原則」の欠如に起因する。「マニュアル」出版後の20年で,こうした誤謬は随分減った。しかし,医師の大多数は「マニュアル」をまだ読んでいない。第3版の書評で2015年の日本感染症界は夜明け前の薄明かり状態だと書いた。2021年の日本はそれなりに明るさを増しているが,それでも日本晴れとはいい難い。
「経過観察」という言葉がある。多くの医者はこれを「何もしないこと」と勘違いしている。しかし,経過観察は得られる見通しがちゃんと立てられているとき初めてとれる戦略で,よって観察すべきパラメーターも明確だ。そこで「避けるべきパラメーター」である体温や白血球数ばかり見ていて「用いるべきパラメーター」である呼吸数などに目配りしないと構造的な失敗が生じるのだ(p.576)。
感染症診療の失敗の多くは「恐怖」が原因だ。その恐怖は知識と(適切な)経験の欠如が原因だ。目の前が真っ暗だと不安になるのは当然だ。啓蒙とは決して表層的差別語ではなく「光を照らす」(enlighten)という意味だ。知識が光を照らし,光が導いた適切な治療とその成功体験が,さらに明るく道を照らし,われわれに勇気を与えるのだ。真っ暗な夜道を突っ走るのは火に飛び込む昆虫のごとく「勇気」ではない。
本書は症例ごとにペラペラとめくればよい本だ。電話帳を怖がる人がいないように,本書の分厚さを恐れる必要はない(電話帳も,そろそろ死語だが)。
本書にたじろぐのは本屋で手に取るときだけである。その後はじんわりと,毎日のように読者に勇気を与えてくれることだろう。間違いなく。
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。