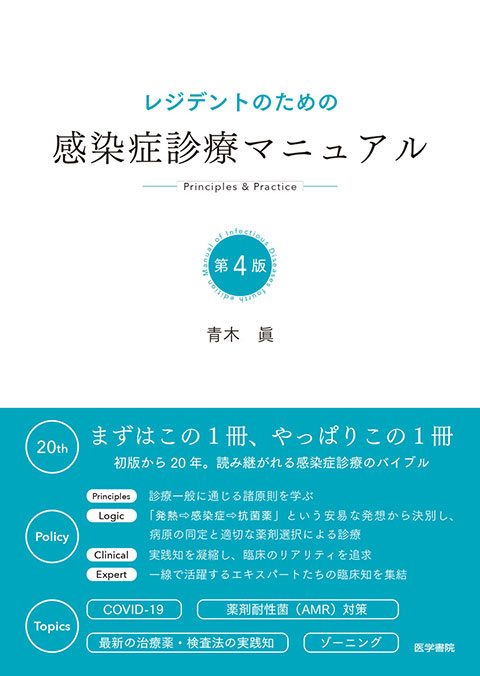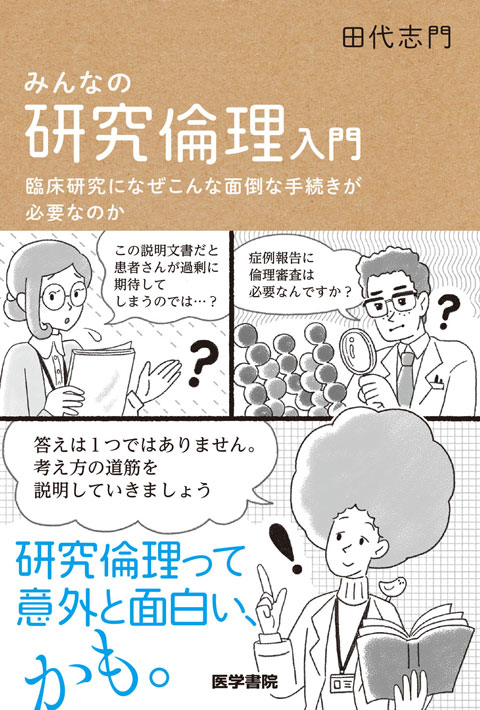MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.03.01 週刊医学界新聞(通常号):第3410号より
《評者》 志水 太郎 獨協医大主任教授・総合診療医学
本書が全医師にとって必読である理由
青木眞先生の本書に出会ったのは今から約20年前,医学部2年生のときで,偶然,初版が発行されてからすぐのことでした。大学生協書店で立ち読みしていたUSMLE関連の本の横に並んでいたこと,特別講義で感染症の授業があった直後だったこともあり手に取ったのです。
医学部低学年でもすごい本はわかるものです。衝撃を受けたのは,今もその形をとどめ,さらにデザインも洗練された第1章の「感染症診療の基本原則」でした。ページをめくるたび臨床のリアルがそこに展開され,興奮しました。学年が進むにつれ,初版序の記載を地で行く“無数の感染症治療薬に窒息しかかっていた”自分に,先に進む光を与えてくれた感動を昨日のように思い出します。
医師になった後は本書の“名所”の一つである感染症フローチャート(p.7)に倣い,自分は初期研修医時代の紙製の温度板にマニュアルの指示通りこれでもかというくらいびっしり重要な情報を書き込み,温度板を見ただけで全てのことが一目瞭然に明快にわかるように整理しました。青木先生が“内科は整理の学問だ”とおっしゃる通り,この温度板の習慣が症例を頭の中で俯瞰して整理する能力を鍛えてくれたと感じています。
『ハリソン内科学』と同様に,総論部分は本書の価値の中核を成しています。本書は約1700ページの大著ですが,ページ数に圧倒される必要もなく,積読にする必要もありません。時間がなければ各論は必要時に参照するとして,まず購入日のうちにでも確実にお読みいただきたいのは第1章です。わずか38ページですが,濃密な38ページでもあります。全てのページが重要ですが,「重症度を理解する」(p.2),「各論的に考えよう」(p.2),「やるとなったら治療は徹底的に」(p.4),「回復のペース,パターンを予測する」(p.5),「経時的な変化を追う」(p.6),「基礎疾患と起因菌」(p.13),「グラム染色に対しての否定的な意見」(p.19),「治療効果は何と何で判定するか?」(p.35),「細菌感染症は悪化か改善あるのみ」(p.37)などは遅くとも初期研修修了までに体感として骨の髄まで染み込ませる必要があると思います。そして現場に出て発熱患者に途方にくれないためにも,次に読み込み制覇すべき章は,第6章の「A 不明熱」の(pp.441-59)の19ページです。ここまでの領域が頭の中でクリアに整理されていれば,少なくともベッドサイドでコモンな感染症や熱・不明熱のケースに対峙する準備は整ったといえると思います。
本書が第4版を迎えても「マニュアル」の名前を変えない理由はなぜでしょうか? それは,マニュアルとして指針を示すが,盲従するわけではなく,原則に則った上での個別化を考えよ,というメッセージと想像します。“青木マニュアルにこう書かれているからそうすべき”というより,“マニュアルにはこう書かれている。その上で,この患者さんの場合は○○という条件もあるから,今回は△△の根拠と理由でこうするべきだと思う”が,本書が期待する臨床医の姿勢だと思います。仮にその上でベストの方針を採用しても,患者さんはさまざまな状況性のもと臨床上難しい経過をたどることもあります。そんなときに生きるのが総論で強調された原則をもとにした,解剖,生理,生化学といったbiomedicalの力,psychological,social medicineを多面的に考慮してゼロベースで考える,総合的な思考力や応用力だと思います。
「師匠は優れた弟子の数で偉大さがわかる」というのは,本書の推薦の言葉のLawrence M. Tierney Jr.先生の数あるパール(名言)の一つです。初版の単著から幾星霜,初版からのファンであったことが想像に難くない弟子・盟友の先生方が今度は著者側となり,本書をさらに充実させています。共著者が多数になっても論調が単著のように一貫し続けているのは,執筆のプリンシプルやロジックが著者陣に十分に共有されているからと思います。この事実自体が,先生が日本の医療界に与えられてきた歴史とインパクトを証明していると感じます。また,初版にしてすでにベストセラーだった本書の改訂を,先生が単著ではなく共著者を入れられていること(前版より)も,教育者である先生の懐の大きさを感じます。もちろん,特に第2版の時など文字通り「命を削って」この本を書かれていた先生のお姿を身近で知る自分としては,このような継承で本書が改訂を続けられていることは,弟子として安心し,またうれしく感じています。
最後に一つ,提案としてこの書評をご覧の先生方にお願いがあります。秘書さんなどにお伝えいただき,本書評を医局のポットの近くなど,よく目につくところに貼っていただきたいのです。本書評を読む機会のない先生方にお読みいただきたいからです。臨床医である以上,感染症を診察しない医師はいないと思います。感染症を診る奥義ともいうべき基本の考え方や共通言語が,まず本書の総論部分と不明熱の章に明示されています。そのため,この章は全ての医師にお読みいただいたほうが良いと思います。さらに臓器別科の先生方であれば追加で担当臓器の章を,総合診療医や救急・集中治療の先生方であれば全ての章を,お読みいただくと良いと思います。つまり全てのベッドサイドの医師にとって,本書は必読となる一冊と思います。
本書を通して,COVID-19の騒動であらためて明らかになった医師のダークサイド,つまり感染症に対する思考停止の常態化の連鎖と悪夢を断ち切り,日本の臨床感染症のレベルを向上させるのは,今が絶好のタイミングだと思います。
《評者》 藤原 康弘 医薬品医療機
史上最高の研究倫理に関する入門書である。一読して,まずそう思った。なにも著者の田代...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。