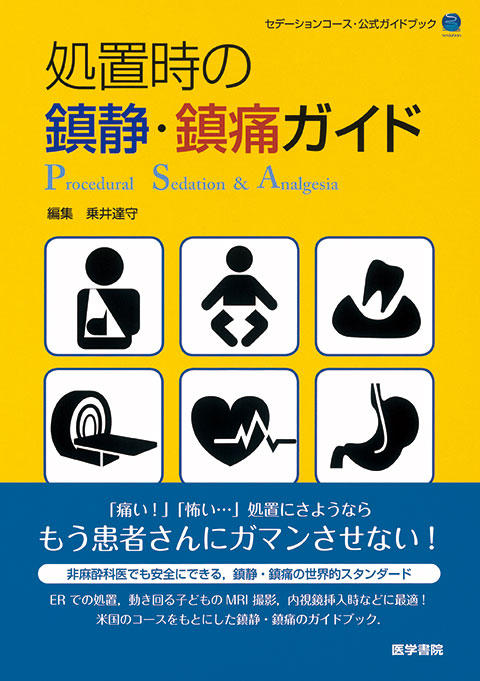MOCHI:世界初の窒息レジストリ研究
寄稿 吉野 雄大,乗井 達守
2021.02.01 週刊医学界新聞(通常号):第3406号より
2019年の人口動態統計によれば窒息による死亡は8379人であり,不慮の事故による死亡の中では転倒・転落・墜落に次ぐ多さです1)。交通事故死が2000人台後半へ減少しているのに対して2),窒息による死亡は増加傾向にあり,高齢化社会の進む日本の公衆衛生上の大きな課題と言えます1)。その一方で,窒息についての研究は不足しています。この点に注目したわれわれは,気道異物による窒息に関する多施設共同観察研究(Multi-center Observational Choking Investigation:MOCHI)グループを2017年に立ち上げ,研究を進めています。まずはMOCHI-retro(2014~19年)という多施設後方視研究を行い,得られたさまざまな知見をもとに多くの発表を行ってきました。そして現在は研究を発展させ,日本救急医学会学会主導研究として,前向き多施設観察研究を行っています3)。
窒息解除手技に関する国際的な推奨とその課題
2020年は国際蘇生連絡委員会(International Liaison Committee on Resuscitation:ILCOR)が,蘇生に関する国際コンセンサス(Consensus on Science with Treatment Recommendations:CoSTR)を発表する年でした。世界中のアスリートが4年に一度のオリンピックを楽しみにするように,われわれ救急医は5年に一度のこの発表をいつも心待ちにしています。当然ですが,米国心臓協会(American Heart Association:AHA)の心肺蘇生ガイドラインもこのCoSTRに準拠しています。毎回さまざまな改訂がなされるのですが,この20年近く窒息の項目は「新たなエビデンスなし」とされ,大きな改訂は行われていませんでした4)。
しかし,2020年度のCoSTRにおける窒息に関する記載は下記の通りに変更があったのです。
推奨
①背部叩打
②背部叩打が有効ではない場合,成人と1歳以上の小児には腹部突き上げ法
③口の中に異物が見える場合は手で取り出す
④心肺停止患者であり,かつ医療従事者が対応するのであればMagil鉗子を用いた異物除去が可能
⑤意識のない成人および小児には胸部突き上げ法
⑥バイスタンダーによる除去
など
推奨せず
❶盲目的に手で掻き出すこと
❷吸引式気道クリアランス装置のルーチンの使用
①②⑥については,2017年にわれわれMOCHI研究班がThe American Journal of Emergency Medicine誌に発表した論文5)が引用されています。特に⑥については新設の項目であり,同論文が唯一のエビデンスとして認められました。ですが,いずれの方法も回数や,方法論に関する具体的な指示の記載はなく,大幅な改訂と表現するにはほど遠いものでした。近日刊行予定の2020年版の『JRC蘇生ガイドライン』(現状の最新は2015年版)においてもCoSTRの内容を踏襲した記載となることが予想されます。
窒息解除に当たり見逃せないのがその手技...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

吉野 雄大(よしの・ゆうだい)氏 会津中央病院救命救急センター/日本医科大学救急医学教室
2011年昭和大医学部卒後,山梨県立中央病院で初期研修。日医大救急医学教室に入局し,関連施設にて研修。その後,東京都済生会中央病院一般・消化器外科での3年間の研修を経て,19年より会津中央病院にて勤務。救急科専門医。

乗井 達守(のりい・たつや)氏 米ニューメキシコ大学医学部救急部
2007年佐賀大医学部卒。健和会大手町病院等で研修後,米ニューメキシコ大病院にて救急研修,チーフレジデントを経て14年より同大医学部指導医。American College of Emergency Physicians評議員およびニューメキシコ州支部前代表。編著書に『処置時の鎮静・鎮痛ガイド』(医学書院)。
いま話題の記事
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。