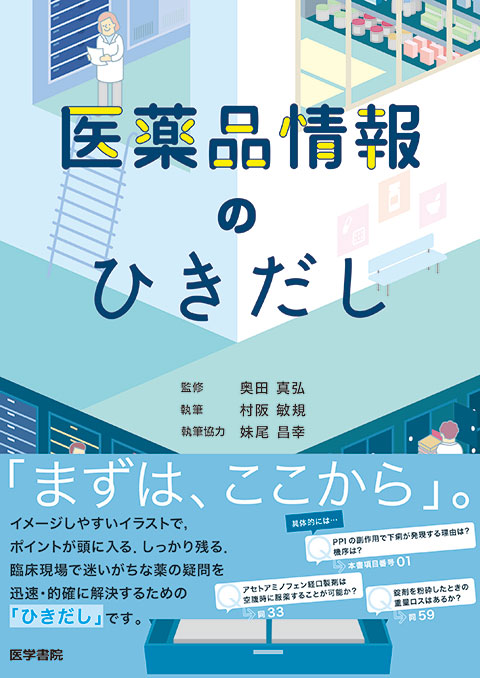DI業務を担う薬剤師が知っておきたい
「医薬品情報のひきだし」の増やし方
寄稿 村阪 敏規
2020.11.30
厚労省が地域包括ケアシステムの構築を推進する中で,2015年には地域医療における薬局の在り方を模索する「患者のための薬局ビジョン」1)が策定されるなど,薬局薬剤師の他職種と連携した地域医療に対する積極的な介入が進みつつあります。それに伴い薬局薬剤師に対する他職種からの問い合わせの増加が予想され,医薬品情報業務(DI業務)の重要性がさらに高まると考えられます。しかし薬局薬剤師が担う業務領域は,調剤業務,服薬指導業務など多岐にわたり,DI業務に多くの時間を費やすことが難しい状況があります。
病院では東大病院,阪大病院,九大病院への設置を皮切りに,各地の国立大学病院に医薬品情報室が設置されました。これにより医薬品情報を駆使した病院薬剤師の役割が他職種に周知され,病院薬剤師の病棟におけるチーム医療への積極的な介入が進みました。同様に薬局薬剤師も「医薬品情報のひきだし」を増やすことで,地域医療におけるチーム医療に積極的に介入できるようになると考えられます。
「医薬品情報編集者」としてDI業務を担う
医薬品に関する問い合わせがあれば,薬剤師は医薬品情報を検索・取得して批判的吟味を加え,適切に評価・確知します。その上で受け手の知識や理解度に応じて医薬品情報を再構築する「編集」を行い,的確かつ迅速に提供します。このような業務を行う薬剤師は「医薬品情報編集者」とも言えるでしょう。
DI業務を行う薬剤師は,さまざまな場面や状況下の受け手に対して刻々と更新される医薬品情報を提供し,薬に付加価値を与えます。限られた時間の中で薬剤師が DI業務を行うには,薬剤師間で問い合わせ内容と回答を分析・評価した上で医薬品情報を蓄積・共有して効率化を図り,情報の質を確保することが必要です。特に医療従事者が情報の受け手であれば,薬剤師の情報によって薬物療法の選択に大きな影響と重大な責任が生じるため,薬剤師は質の高い医薬品情報の提供に努める必要があります。
また薬剤師にとって,最終的な回答に到達するまでに多くの「問いの繰り返し」を行い,関連した情報を付加して提供することも重要です。「問いの繰り返し」を行うことで,一つの「問い」をきっかけとして薬剤師が持つ「医薬品情報のひきだし」を増やすことができます。医薬品情報業務の効率化を図り,情報の受け手の満足度を向上させるためには,一人ひとりの薬剤師が問い合わせに対する回答までの考え方の道筋を経験するなど研さんを積むことが必要です。
以下,このたび筆者が上梓した『医薬品情報のひきだし』(医学書院)に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
村阪 敏規(むらさか・としき)氏 株式会社トゥモファ代表取締役 こうなん薬局
2008年神戸薬科大卒。18年三重大大学院医学系研究科修士課程修了。医療薬学専門薬剤師。08年三重大病院薬剤部入職,11年こうなん薬局を開局。13年に株式会社トゥモファに組織変更。薬局経営・薬局実務を行いつつ,薬剤師のための医薬品情報編集室「CloseDi」を運営している。近著に『医薬品情報のひきだし』(医学書院)がある。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。