MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.11.09
Medical Library 書評・新刊案内
NHKスペシャル「人体」取材班 編
《評者》石野 史敏(東京医歯大難治疾患研究所教授・エピジェネティクス分野)
ヒトはゲノムから,自分自身をどこまで理解できるか?
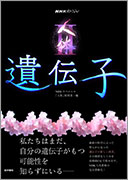 2003年にヒトゲノム計画は完了し,全ゲノム配列が明らかになった。しかし,計画が最終目標に掲げていた「ヒトゲノムの機能を完全に読み解く」ことはまだできていない。予想よりもはるかに少ない2万の遺伝子しかなく,それが占める部分はゲノム全体のたった2%ほどしかない。ヒトゲノムの残り98%は一見,訳のわからない無意味なDNAで占められているが,世界中が競って集めた疾患SNPデータのその多くがここにマップされた。
2003年にヒトゲノム計画は完了し,全ゲノム配列が明らかになった。しかし,計画が最終目標に掲げていた「ヒトゲノムの機能を完全に読み解く」ことはまだできていない。予想よりもはるかに少ない2万の遺伝子しかなく,それが占める部分はゲノム全体のたった2%ほどしかない。ヒトゲノムの残り98%は一見,訳のわからない無意味なDNAで占められているが,世界中が競って集めた疾患SNPデータのその多くがここにマップされた。
『NHKスペシャル――シリーズ「人体」II 遺伝子』には,このヒトゲノムの98%部分に潜んでいる機能に関する研究の最前線が取り上げられている。第1集では,この未知の部分にあるたった1つのDNA塩基の変異(SNP)がヒトの表現型に影響を与える例がいくつか紹介されている。これは,さまざまな環境に適応してきたヒトの進化における自然選択の歴史を物語っている。最先端の分子生物学は,これにどのような説明を与えるのか? SNPが遺伝子発現メカニズムに与える影響を,CGの力も借りてわかりやすく紹介している。ここからわかるのは,疾患にかかわる一つひとつの遺伝子変異やSNPがヒトの表現型に与える影響を,丁寧に深く掘り下げていく地道な研究者の努力が心踊る発見につながっていくのであり,その成果の積み重ねが,最終的に「ヒトゲノムの機能を完全に読み解く」ことにつながることである。
第2集では,同じDNA配列を持つにもかかわらず,多様な表現型を生み出す原動力であるエピジェネティクスに焦点が当てられている。第1集で扱ったDNAの変異(配列の変化)がどのように表現型に影響を与えるかに対し,エピジェネティクスは1つの受精卵から多様な細胞,組織を持つ個体を作り上げる機構を理解するための,DNAメチル化による遺伝子発現のスイッチ機能や,ヒストン複合体によるクロマチンの構造変化の重要な役割などが紹介されている。
読者の皆さんは,この本で語られる新しい世界観にきっと驚かされるだろう。「ゲノム情報からヒトを理解する」研究がここまで進んでいることにきっと感動を受けるであろう。同時に,生物の多様性を守るために人類は何をなすべきなのか? これらの技術が将来の人類社会,生物界に与える影響も問い掛けている。ヒトゲノム研究は慎重に進めなければならないが,この本には多くの日本人研究者の仕事が紹介されており,若い世代には,そこには魅力に満ちた世界が広がっていることを知って欲しいと思う。
最後に,オリジナリティー溢れる世界の一流研究者への取材を,美しい風景写真,見事な電子顕微鏡写真,細胞世界を分子レベルで表現したハイレベルのCGを盛り込み,素晴らしい本にまとめあげたNHKスペシャル「人体」取材班の努力に敬意を払いたい。
B5・頁224 定価:本体2,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-04244-4


國松 淳和 編
《評者》萩野 昇(帝京大ちば総合医療センター第三内科学講座講師(血液・リウマチ))
通読後も折に触れて読んで使い倒していくべき本
 COVID-19の波が世界を押し流している。まさしく「パンデミック」の風景であるが,このパンデミックは各社会が内包する脆弱(ぜいじゃく)性を片端から明らかにしつつある。わが国の診療現場においても,少なからぬ数の「システムエラー」が明白になったが,その一つに「日常診療において『発熱患者』に対してどのようにワークアップすればよいのか,きちんと理解して診療している医師は決して多くない」という不都合な事実がある。卒前の医学教育において,疾患ごと・臓器ごとの縦割りの教育(そのメリットが幾分かは存在することは,旧世代の医学教育を受けた者としては,一応留保をつけておきたいところではあるが)を受け,卒後の臨床現場では多くはon-the-job trainingの形で,教える側の医師の専門性に大きく偏った教育が施される現状であれば,今後もしばらくは慣性的に現状が維持されるのではないかと悲観せざるを得ない。
COVID-19の波が世界を押し流している。まさしく「パンデミック」の風景であるが,このパンデミックは各社会が内包する脆弱(ぜいじゃく)性を片端から明らかにしつつある。わが国の診療現場においても,少なからぬ数の「システムエラー」が明白になったが,その一つに「日常診療において『発熱患者』に対してどのようにワークアップすればよいのか,きちんと理解して診療している医師は決して多くない」という不都合な事実がある。卒前の医学教育において,疾患ごと・臓器ごとの縦割りの教育(そのメリットが幾分かは存在することは,旧世代の医学教育を受けた者としては,一応留保をつけておきたいところではあるが)を受け,卒後の臨床現場では多くはon-the-job trainingの形で,教える側の医師の専門性に大きく偏った教育が施される現状であれば,今後もしばらくは慣性的に現状が維持されるのではないかと悲観せざるを得ない。
そのような状況で出版された『不明熱・不明炎症レジデントマニュアル』は,「遷延する発熱=不明熱」ならびに「不明炎症」という,非常にありふれていながらぞんざいな扱いを受けてきた症候に対して,多くの分野の専門家が寄稿する形でまとめられた1冊であり,まさにwith COVID-19の一著としてふさわしい内容である。編者の國松淳和先生はすでに類似テーマで『外来で診る不明熱――Dr. Kの発熱カレンダーでよくわかる不明熱のミカタ』(中山書店,2017),『「これって自己炎症性疾患?」と思ったら――疑い,捉え,実践する』(金芳堂,2018)などのスマッシュヒットを飛ばしておられるが,今回のレジデントマニュアルは過去の単著よりもやや基本的なレベルに読者対象を絞っており,「レジデント」が踏まえておくべき内容として適切と思われる。一方で,「コアな國松ファン」にとっては,やや食い足りない感じも否めないが,そういう読者に向けては國松節全開の10章「とにかく全然わからないとき」,付章「こっそり読みたい『不明熱マニュアル外伝』」が準備されている。ただし,付章については「コアな國松ファン」は立ち入り禁止の札が立っているので,そういう意味でも「こっそり読みたい」。
章立てとして「検査(4章)」「疾患(5,7,9章)」「症候(6,8章)」と分けられているのも素晴らしい。疾患・症候がわざわざ2群に分けられていることからは,最初からまれな事象を考えるべきではなく,同時にまれな事象を見落としてはならないという編者のニッチな切り口がうかがえる。言い換えると,5章から9章に至るまでの流れには「病名がなくてもできること」があるだろうという編者の思想をバックグラウンドとして見てとることができる。
「コアな國松ファン」であると同時に「不明熱・不明炎症屋」の端くれとして,自分ならどう書くだろう,と考えたとき,「状況による分類」をもう少し前面に打ち出すのではないか,と思った。つまり,本書では「渡航関連感染症」のみ「状況」が明記されているが,それ以外にも「高齢者・超高齢者」や「透析患者」「担がん患者」という切り口があっても良い。第2版以降に期待したい。
総括すると,本書はレジデントマニュアルシリーズの他の本と同様,1回軽く通読して「脳内にOSをインストール」し,折に触れて(不明熱・不明炎症の患者を診療する度に)該当部分を読んで使い倒していくべき本である。お手元に置かれることを強くお薦めしたい。
B6変型・頁498 定価:本体4,500円+税 医学書院
ISBN978-4-260-04201-7


中村 好一 著
《評者》堤 明純(北里大医学部教授・公衆衛生学)
人間を対象とした学問だからこその面白み
 『基礎から学ぶ 楽しい疫学』の第4版が出版された。この業界(?)では有名な本で,どの版も8刷,9刷を重ねている。PR通り,疫学の初学者にはとてもよい本だと思う。単著であることは,この本の特徴の1つで,章ごとに質,量ともに濃淡なく,必要最小限の(と著者が考える)情報が整理されている。
『基礎から学ぶ 楽しい疫学』の第4版が出版された。この業界(?)では有名な本で,どの版も8刷,9刷を重ねている。PR通り,疫学の初学者にはとてもよい本だと思う。単著であることは,この本の特徴の1つで,章ごとに質,量ともに濃淡なく,必要最小限の(と著者が考える)情報が整理されている。
私は,2002年4月に著者の署名入りの初版を読んでから,本書のファンの一人で(第2版,第3版も購入),現職では,学部学生に準教科書として紹介している。大学院生には必読書として,早期に3回読むよ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
