臨床と科学哲学の間から「死」を考える
対談・座談会 村上 陽一郎,國頭 英夫
2020.11.02 週刊医学界新聞(通常号):第3394号より
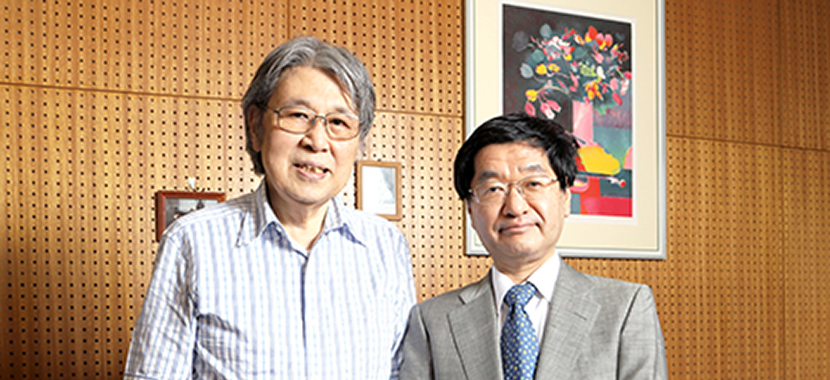
現代社会では多くの死は病院内における出来事となり,人々が死を身近なものとしてとらえることは少なくなった。その中で訪れた新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)の流行は,人々の死生観にどのような影響を与えているのだろうか。
今回,哲学の場から死を見つめてきた科学哲学の泰斗である村上氏と,このたび『「治る」ってどういうことですか?――看護学生と臨床医が一緒に考える医療の難問』(医学書院)を上梓し,臨床の場で「死にゆく患者」を見つめてきた臨床医である國頭氏の対談を企画。対談には本書に登場する,國頭氏の教え子で現在は現場で働く2人の看護師も同席した。
人が生きる上で最大の難問である「死」をどう考え,どう臨むべきか。知の巨人たちが導き出した答えとは。
村上: コロナ禍で著名人の死がセンセーショナルに報道されました。COVID-19は私たちの死生観に少なからず影響を与えているのでしょうか。臨床医のお立場から,どうご覧になっていますか。
國頭: これまで死への意識が薄くなっていた現代社会で,コロナ禍は人々が直視してこなかった死についての意識を顕在化させたといえるでしょう。
村上: そもそも,人々にとって死の多くは病院内での出来事となり,身近なものではなくなっています。亡くなった家族を自宅で看取る機会は減り,すでに1976年には院内死の件数が自宅死を上回っています。厚労省「人口動態統計」1)によると,2019年には約70%が病院内で死亡しています。
國頭: 死と出合う機会が減少しているために,人々が死を忌むべきものとしてのみ扱い,考えないようにしている現状があります。そしてそれは病院の患者においても同様です。周囲に迷惑を掛けずに突然コロッと亡くなる「ピンピンコロリ」を理想の死に方として挙げる人は多いのですが,しかし,いざ「コロリ」が近いとわかると「心の準備ができていない」と大慌てします。ほとんどの人は「ピンピン」ばかりで,「コロリ」のことは考えていないように思います。
村上: 本来,死とは人が次第に衰えて亡くなる瞬間までの長い時間を含んだ「プロセス」なのです。決してある一瞬だけをとらえた「点」ではない。しかし今や死は極めて非日常的な特異点となり,人々がそのプロセスについて考える機会さえほとんどなくなってしまった。他者の死のプロセスを見つめなければ,自分の死について考えることも難しいと思います。
國頭: そうですね。私が以前に担当した患者さんは,入院していた40歳前の男性で小学校高学年と低学年くらいの子どもがおり,ご両親は健在でした。そのご両親は子ども(つまりお孫さん)が父親の苦しむ姿を見るとトラウマになるからと,患者の面会になるべく来させないようにされていました。
村上: 親が亡くなるまでのプロセスを見ることが子どもにとってトラウマになると考えてしまうこと自体が,死から遠く引き離されていることの証ですね。
國頭: その通りです。当時,私は患者と年齢が近く,「自分の子どもに会えずに最期を迎えるのはつらいだろう」と考え,患者の奥さんと相談して,子どもさんには面会に来てもらいました。患者の両親は父親の死という「嫌なもの」を孫に見せたくないと思ったのでしょう。これが多くの日本人の感覚なのではないでしょうか。
村上: そうですね。かつては,身近な人を看取る中で,先人が連なる死者の列にいつか自分も加わることはごく自然なこととして理解されていました。しかし,身近な人の死を見つめる機会が少なくなった今では,その感覚はかなり希薄化しています。
「患者が死なないこと」を前提としている急性期医療
國頭: わが国の急性期病院では,例えば肺炎や心不全での急変時などであれば,まずは人工呼吸器を装着して治療を行うことがほとんどデフォルトの処置になっています。それは高齢患者でも例外ではありません。
村上: 昨今の病院の目的は,終末期であっても実施できる全ての医療をできる限り投入して患者を1日でも長生きさせることですね。しかし,医療が本当に戦うべき相手は患者の死ではなく,患者の苦しみであるはずです。急性期医療では,患者の死は「医療の敗北」として,忌避すべきものとして扱われているように感じます。
國頭: 私は急性期病院においては,そもそも患者が亡くなることがほとんど想定されていないと考えています。急性期病院では,治療としてできることをやり,回復が見込まれない場合には慢性期の施設に移す。また末期がんなどに罹患して治療が難しい場合には緩和ケア病棟に送る。「患者が死なないこと」を前提に提供される医療が人生の終末期にふさわしくないのは明らかですが,急性期病院では「それは自分の仕事ではない」となる。
緩和ケアでは,2018年度の診療報酬改定で従来のがんとHIVに加えて末期心不全も保険適用の対象となりました。しかし心不全の緩和ケアにはがんの緩和ケアと異なる点があります。現在のがんの緩和ケアは予後についての影響は限定的です。一方で心不全の場合は症状緩和の治療で予後も改善しますから,「緩和ケア」と通常の治療の区別は不明瞭です。
村上: さらなる高齢化に伴い心不全患者の増加が予想されることなどを考えると,心不全の緩和ケアは難しい問題を多く含んでいますね。
加えて現代医療では,本人の意思確認の問題も重要です。2019年に人工透析中止で亡くなった女性の遺族が公立福生病院を提訴する事件が大きく報道されました。これは患者が真摯な意思で人工透析の中止を選んで意思確認の書類に署名をした後,苦しみに耐えかねてその決定を撤回する発言をしたものの,担当医は苦痛緩和の治療を行い人工透析が再開されずに亡くなったとされ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

村上 陽一郎(むらかみ・よういちろう)氏 東京大学名誉教授/国際基督教大学名誉教授
「医師には人の命を救おうと全力を尽くす覚悟が必要であり,同時に患者の苦しみを思いやって慈悲の死を与える覚悟も必要だ。」
1962年東大教養学部卒。同大大学院人文科学研究科博士課程修了後,東大教養学部教授,国際基督教大教養学部教授,東洋英和女学院大学長などを歴任。2015年に瑞宝中綬章を受章。『ペスト大流行――ヨーロッパ中世の崩壊』(岩波新書),『〈死〉の臨床学――超高齢社会における「生と死」』(新曜社)など著書多数。近著に『死ねない時代の哲学』(文春新書),『コロナ後の世界を生きる――私たちの提言(編)』(岩波新書)。
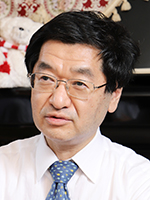
國頭 英夫(くにとう・ひでお)氏 日本赤十字社医療センター化学療法科部長
「医療者はその職業使命として人の死に触れることは避けられず,「死への臨み方」は学んでおかねばならない必修科目である。」
1986年東大医学部卒。横浜市立市民病院,国立がんセンター中央病院,三井記念病院などを経て2014年より現職。『誰も教えてくれなかった癌臨床試験の正しい作法』(中外医学社),『医学の勝利が国家を滅ぼす』『「人生百年」という不幸』(里見清一名義,いずれも新潮社),『死にゆく患者と,どう話すか』(医学書院)など著書多数。近著に『「治る」ってどういうことですか?――看護学生と臨床医が一緒に考える医療の難問』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
