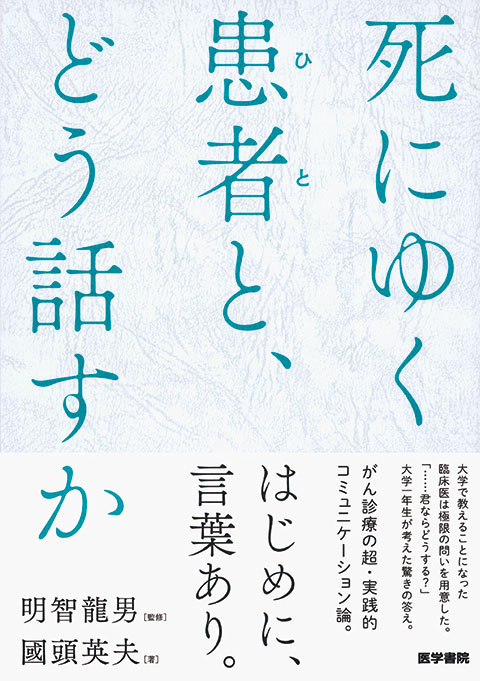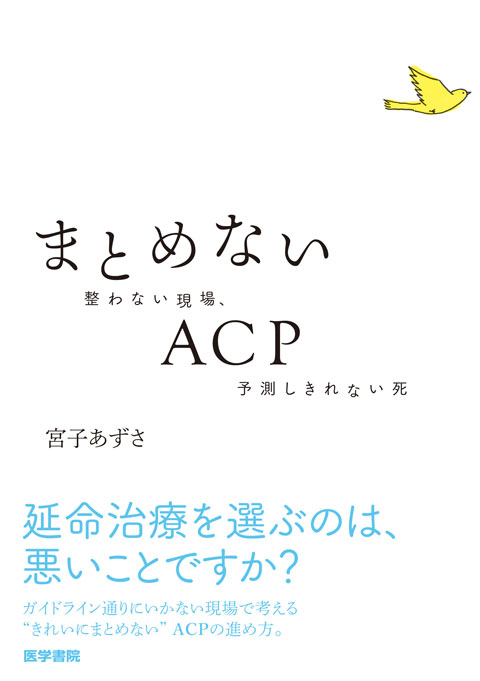死にゆく患者(ひと)と、どう話すか
……君ならどうする?
もっと見る
臨床医が看護学生と考える「死にゆく患者(ひと)といかに語るか」についての超・実践的コミュニケーション論。がん告知と積極的治療の中止(Breaking Bad News)の方法、DNR(Do Not Resuscitate;心肺蘇生を行わないでください)の限界、インフォームドコンセントのあるべき姿とは。臨床の泥沼で最善のものを見つけるために知っておきたい信用と信頼のコミュニケーション・スキルを学ぶ全7講。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに 臨床現場でのコミュニケーション・スキルの本当のところ
こんにちは。今年から、基礎ゼミⅡのひとつを担当することになった國頭です。このゼミは、日本赤十字看護大学一年生後期の必修科目のひとつだそうですが、十数人の講師がいろんなテーマで行うことになっているようです。ともあれその中から13人の学生さんが私の「コミュニケーション論」を選択してくれて、まずはお礼を申し上げます。
さて、みなさんも一年生でまだ大学に慣れていないところがあるかもしれませんが、私も日本赤十字社医療センター(以下、日赤医療センター)に赴任してから日が浅く、いきなり看護大学のゼミを担当しろと言われましたところで、何をやったらいいのかよく分かりません(笑)。学長先生から、「何が得意ですか?」と聞かれ、「最も得意なのは生物統計学」と答えたのですが、「それはダメです」とあっさり却下されました(笑)。じゃあ、というわけで苦し紛れに捻り出したのがこの題目です。
基礎ゼミⅡの中には、他にもコミュニケーション論を扱ったコースがあるようです。それと私のとは何が違うか、というのを先にお話ししましょう。
私は日赤医療センターで化学療法科という、つまりは進行がんの治療を専門とする医者です。がんの治療は進歩し、その予後は良くなりましたが、それでも、私が扱う患者さんは、ほぼ必ずがんで亡くなります。世の中には、治る病気なら治療をしてもよいが、治らなければやっても仕方がないなどと悟ったようなことを言う人がいますが、もちろんそんなわけにはいきません。患者さんはみんな、治らずとも、いずれ死んでしまうとしても、不安と闘いながら闘病されています。私も、病棟や外来の看護師さんも、「どうせ治らないから」といって、患者さんを見放すことは許されません。そういう「死んでいく」患者さんといかに向き合い、どうやって少しでもベターな「ライフ」を過ごしてもらえるか、というのが我々の使命です。ちなみにあえて「ライフ」とカタカナにしたのは、英語のlifeには生活、生命、人生というような意味があり、ここではそれを全部含むからです。
みなさんは、そういう暗い話は嫌だ、と考えるでしょうか? ですが、がんであってもなくても、入院患者さんの多くは重症で、そのまま死んでしまうことも多いのです。というより、人間は絶対に一度は死にますから、別にがんだけが暗いのではありません。ちょっと前に私は、自分の仕事を『見送ル』(新潮社)という小説にまとめました。それについて、私が学生時代に解剖学を教わった養老孟司先生が、「出て来る患者はみんな死んでしまうが、別に暗くない。人間はみんな死んでしまうから」と書評に書いてくださいました。だから、私は、医療の中で、特別なことをやっているわけではなく、私の仕事にとって大事なことは、医療全体でも重要なことなのです。
そして、コミュニケーションというのは、医療において決定的な重要性をもちます。医学の祖と言われるヒポクラテスの言葉に、「医者には三つの武器がある。第一に言葉、第二に薬草、第三にメスである」というのがあるそうです。薬草(内科的治療)やメス(外科的治療)の前に、「言葉」があるのです。
しかしながら、死に臨んだ患者さんを前にして、我々は何をどう話せばいいのでしょうか。考えれば考えるほど怖くなります。患者さんは怒り、悲しみ、嘆きなどの感情を我々にぶつけてきます。その思考はしばしば非合理的で、錯乱することもあります。
私がやってきたことは、高邁な理論ではなく、そういう臨床の泥沼で、いかにして最善の、それができなければ次善のものを見つけていくか、という作業でした。結局うまくいかなかった、ということも頻繁にあります。実社会は受験勉強のように、「正解」が用意されているのではありません。どうやったって成功することもあれば、なにをやっても必ず失敗する、という場面もあります。ただ我々はその時も、少しでもマシな失敗ですむような努力をしなければなりません。
学問としての「コミュニケーション論」が、仮にノーベル賞を取るような原子力物理学だとしたら、私のそれは、爆発した福島原発で瓦礫を片付けるような、地味で辛い作業でしょう。だけど、今の日本にとっては、瓦礫の片付けは「誰かがやらねばならないこと」です。
そうは言っても、今、自分がいるのがどういう場所で、この仕事が次にどうつながるのかが分からないと、瓦礫の片付けの意味も理解できません。そのために、大きく分けて、二つのことをお話ししていきます。一つは、臨床でのコミュニケーション一般に関すること。もう一つは、末期患者のターミナルケアで問題になること。ただし、話は具体的と言えば聞こえはいいですが、生々しい現場のぐちゃぐちゃした実例が主体で、あっちこっち話が飛ぶことは勘弁してください。
コミュニケーションという言葉は、communicareというラテン語から出たとされています。この言葉は「共有する」という意味だそうで、何を共有するか、というと、情報ということになりますね。
さて、このコミュニケーションはどうやってとるかというと、普通は言葉でとる、つまり言葉を通して情報を共有するのだ、と考えます。ところが有名な研究があって、医療者と患者のコミュニケーションにおいて、言葉が果たす役割はわずか7%で、残りは表情・姿勢・身振りなどが55%、声の調子が38%、つまり9割以上が言語以外の要素で決まっているのだ、と報告されています。
どうやってその「55%」なんて数字が出て来たのか知りませんが、とにかく、言葉以外のことが決定的に重要だ、ということですよね。これを見ると、ほとんど第一印象で決まってしまうような感じがします。ちなみに新潮新書に『人は見た目が9割』というベストセラーがありますが、その「9割」もこの論文からの引用のようです。
さて、がん医療に携わる私なんかは、日々患者さんやご家族とのコミュニケーションをとらねばなりませんが、そうした日常の診療や挨拶レベルとは別に、何段階も難しいものがあります。一番難しいのは、たとえば患者さんが病状を認めようとしない「否認」や、やり場のない「怒り」などに支配されている時が一つ。こういうのはある程度時間をおかないと仕方がない。またこちらが何かミスしてしまった時もそうですけど、それはがん医療に限ったことではありません。もう一つ、患者さんが精神疾患などを併発していて、まともに話ができないような場合は非常に困ります。こういうのは、往々にして精神科の先生に助けてもらわなければいけません。
それとは別に、その一つ前段階にはなりますが、困難なコミュニケーションがあります。「悪い知らせを伝える」という言葉で表されるのが代表的なもので、英語ではそのまま「breaking bad news」といいます。たとえば、予後の悪いがんを診断して病名を告げる。あなたは肺がんだとか、膵がんだとか告知する場合ですね。あと、がんの再発を告げる。今やがんでも治るものは治ると、多くの人は知っています。ただ自分は治らなかった。いろんなバッドニュースの中でも、患者さんにとっては、最初に再発を告げられる時が一番辛い、と言われています。
あと、最近の私が一番辛いのは、治らないまでもいろいろやってきたのだけれど、もう限界だ、もうこれ以上はやめよう、という、積極的治療の打ち切りの時ですね。治らない、と分かっていても、患者さんは死ぬ気なんて全然ないんですね。今までも治療をやってきた。それは効いたり効かなかったり、効いてもまた悪くなったりしてきた。けれども私は常に、患者さんに、「今度はこういう治療をしよう」と提案していた。それなのに、この期に及んで、一転して「もうやめようか」とは何事であるか。先生、あんたは俺を裏切るのか。そう言われるのは目に見えていて、だけれどもやっぱりこれ以上はやるべきではないと伝えなければいけない場合がある。これはそのうちまた取り上げます。
こういう「breaking bad news」で相手は落ち込んだり悲しんだり怒ったりしますが、そういう反応は病的ではないんですね。普通の人間ががんだと言われ、再発だと言われ、もう治療法はないと引導を渡されて、いい気分がするはずがない。それをいちいち精神科の先生に相談するわけにもいかない。
私が医者として独り立ちして肺がんを専門にやっていくことになったのは平成2(1990)年からですが、その時、私の上司の部長とともに「肺がんの患者には病名を伝えよう」という方針を決めました。当時はがんの告知はタブーに近いような時代で、どうかするとがんセンターでもはっきりとは言っていなかった。私がいたのは普通の市民病院でしたから、私と部長の二人きりの呼吸器内科以外では、がんの告知なんて誰もやらなかった。おおっぴらには邪魔されませんでしたけれど、随分と好奇の目で見られました。「先生、(患者に)がんって言うんだってね」、とかよく言われました。考えてみるとその部長は偉い人でしたね。病院のバックアップもなしにそこまで先鋭的な方針に踏み切ったのですから。従うのは直属の部下一人だけで、その部下の私はまだ20歳代のペーペーです。
その当時、肺がんだと言われてうつ状態になった患者さんのことを、精神科のドクターに相談に行ったら、「それは精神科の対象ではない」とあっさり門前払いにされました。要するに、病気ではない、と言うんですよ。「精神科というのはたとえば統合失調症とか躁うつ病などの、精神を病んだ『患者』を診るのである。がんと言われて落ち込むのは正常人の正常な反応で、病気でもなんでもない。だから精神科では扱えない」と。
今でも覚えています。こう言われました。「先生、この患者にがんだって言っちゃったんでしょ? うつになるのは当然ですよ。がんを治してやればいいんじゃないですか。そうしたら気分も良くなります」。25年以上も経って覚えているのだから、よほど恨みが深かったのが分かりますよね(笑)。
ちなみに今では精神科もそういう「正常の反応」も扱ってくれます。言われてふさぎ込むのは仕方がないにしても、その後なかなか立ち直れないのは「適応障害」という名前がついていますし、そこから本物の「うつ」として治療の対象になる場合もある、ということになっています。
さてそれで、アメリカでは日本より一足先にがんの告知が一般的になっていました。なぜアメリカではそうなっていたか、というと、患者の知る権利、とか、自己決定権、とか言われていますけど、そんなのは建前で、本音は訴訟が怖いからですよね。「どうして知らせてくれなかったのだ。おかげで自分は治療法を選べなかった。また人生の計画をし損ねた。訴える」というのを回避するための、医者側の自己防衛の要素が強い。だけどまあアメリカ人は自立傾向が強いから、「知らせてほしい」という欲求が高まったのも、嘘ではないでしょう。
それではアメリカ人はその悪いニュースを知ってどうなるか。彼らはキリスト教の神様を信じているからといって笑って運命を受け容れるか、というと、そんなことはないのですよ。いくら神様を信じていたって、死ぬのは嫌だし怖い。だからそういう「breaking bad news」も、事実を淡々と伝えて終わり、ではなくて、ちゃんと伝え方の工夫を考えています。考えるまでもなく人情は欧米人も日本人も、そんなに変わりはないのですね。
そのような「伝え方の工夫」を、コミュニケーションスキル、といいます。「スキル」というのは技能もしくは技術、という意味ですよね。よく、心がこもっていれば小手先の技術なんて要らない、とか言う人がいますが、何も考えずに裸一貫でぶちあたれ、というのですから、大概は馬鹿です(笑)。ちょっと以前に、そういう馬鹿の一人が総理大臣になって、「友愛」を連呼した挙句に日本を滅ぼしそうになりました。我々はプロですから「技術」を持たねばなりません。
代表的な伝え方の技術がSPIKESです。ロンドン生まれでカナダの大学の腫瘍内科医であったロバート・バックマン先生と、テキサスのMDアンダーソンがんセンターの精神科医のウォルター・ベイル先生が中心となってまとめられました。これは情報を伝える時に留意すべきこととして
Setting (面談の場の設定)
Perception (相手がどのくらい認識しているか)
Invitation (どのくらい知りたがっているか)
Knowledge (知識や情報を伝える)
Emotion and Empathy (相手の感情を受け止め、共感を示す)
Strategy and Summary (今後の方針を示す)
という6項目の頭文字をとったものです。
これを日本人に合わせて一部改変したSHAREプロトコールを、当時国立がんセンター東病院におられた内富庸介先生たちが作られました。ちょっと項目を見てみましょうか。
S:Supportive environment (支持的な環境設定)
H:How to deliver the bad news (悪い知らせをどのように伝えるか)
A:Additional information (医学的、社会的付加的情報)
RE:Reassurance and Emotional support (安心感と情緒的サポートの提供)
どうでしょうか。みなさんにはあまり違和感がないかもしれませんが、私なんかはこういうのを読むと、「それはそうなんだろうけどさ……」と溜息をつきたくなりますね。
バックマン先生は自分でがんの患者を診ている医者だそうですけど、彼は例外で、大体こういう決まり事みたいなのを作るのは、精神腫瘍の専門家、つまり精神科の先生なんですね。ですから、ご自分で患者に、「あなたはがんだ」とか「もう治らない」とか言う立場ではないのですよ。ただ、我々臨床の医者が患者に向かってそう説明するのをわきで聞いていて、やれお前の話し方は下手だとか、言葉遣いがなっていないとか文句つけるわけですね(笑)。だったらあんたやってくれよ、と私なんかは言いたくなります(苦笑)。もちろん、わきに座ってあれこれ「指導」してくださるのは有難いことなんでしょうけど。これだけでは実際の役にはあまり立ちそうにない。ではどうすればいいのでしょう。
こんにちは。今年から、基礎ゼミⅡのひとつを担当することになった國頭です。このゼミは、日本赤十字看護大学一年生後期の必修科目のひとつだそうですが、十数人の講師がいろんなテーマで行うことになっているようです。ともあれその中から13人の学生さんが私の「コミュニケーション論」を選択してくれて、まずはお礼を申し上げます。
さて、みなさんも一年生でまだ大学に慣れていないところがあるかもしれませんが、私も日本赤十字社医療センター(以下、日赤医療センター)に赴任してから日が浅く、いきなり看護大学のゼミを担当しろと言われましたところで、何をやったらいいのかよく分かりません(笑)。学長先生から、「何が得意ですか?」と聞かれ、「最も得意なのは生物統計学」と答えたのですが、「それはダメです」とあっさり却下されました(笑)。じゃあ、というわけで苦し紛れに捻り出したのがこの題目です。
基礎ゼミⅡの中には、他にもコミュニケーション論を扱ったコースがあるようです。それと私のとは何が違うか、というのを先にお話ししましょう。
私は日赤医療センターで化学療法科という、つまりは進行がんの治療を専門とする医者です。がんの治療は進歩し、その予後は良くなりましたが、それでも、私が扱う患者さんは、ほぼ必ずがんで亡くなります。世の中には、治る病気なら治療をしてもよいが、治らなければやっても仕方がないなどと悟ったようなことを言う人がいますが、もちろんそんなわけにはいきません。患者さんはみんな、治らずとも、いずれ死んでしまうとしても、不安と闘いながら闘病されています。私も、病棟や外来の看護師さんも、「どうせ治らないから」といって、患者さんを見放すことは許されません。そういう「死んでいく」患者さんといかに向き合い、どうやって少しでもベターな「ライフ」を過ごしてもらえるか、というのが我々の使命です。ちなみにあえて「ライフ」とカタカナにしたのは、英語のlifeには生活、生命、人生というような意味があり、ここではそれを全部含むからです。
みなさんは、そういう暗い話は嫌だ、と考えるでしょうか? ですが、がんであってもなくても、入院患者さんの多くは重症で、そのまま死んでしまうことも多いのです。というより、人間は絶対に一度は死にますから、別にがんだけが暗いのではありません。ちょっと前に私は、自分の仕事を『見送ル』(新潮社)という小説にまとめました。それについて、私が学生時代に解剖学を教わった養老孟司先生が、「出て来る患者はみんな死んでしまうが、別に暗くない。人間はみんな死んでしまうから」と書評に書いてくださいました。だから、私は、医療の中で、特別なことをやっているわけではなく、私の仕事にとって大事なことは、医療全体でも重要なことなのです。
そして、コミュニケーションというのは、医療において決定的な重要性をもちます。医学の祖と言われるヒポクラテスの言葉に、「医者には三つの武器がある。第一に言葉、第二に薬草、第三にメスである」というのがあるそうです。薬草(内科的治療)やメス(外科的治療)の前に、「言葉」があるのです。
しかしながら、死に臨んだ患者さんを前にして、我々は何をどう話せばいいのでしょうか。考えれば考えるほど怖くなります。患者さんは怒り、悲しみ、嘆きなどの感情を我々にぶつけてきます。その思考はしばしば非合理的で、錯乱することもあります。
私がやってきたことは、高邁な理論ではなく、そういう臨床の泥沼で、いかにして最善の、それができなければ次善のものを見つけていくか、という作業でした。結局うまくいかなかった、ということも頻繁にあります。実社会は受験勉強のように、「正解」が用意されているのではありません。どうやったって成功することもあれば、なにをやっても必ず失敗する、という場面もあります。ただ我々はその時も、少しでもマシな失敗ですむような努力をしなければなりません。
学問としての「コミュニケーション論」が、仮にノーベル賞を取るような原子力物理学だとしたら、私のそれは、爆発した福島原発で瓦礫を片付けるような、地味で辛い作業でしょう。だけど、今の日本にとっては、瓦礫の片付けは「誰かがやらねばならないこと」です。
そうは言っても、今、自分がいるのがどういう場所で、この仕事が次にどうつながるのかが分からないと、瓦礫の片付けの意味も理解できません。そのために、大きく分けて、二つのことをお話ししていきます。一つは、臨床でのコミュニケーション一般に関すること。もう一つは、末期患者のターミナルケアで問題になること。ただし、話は具体的と言えば聞こえはいいですが、生々しい現場のぐちゃぐちゃした実例が主体で、あっちこっち話が飛ぶことは勘弁してください。
コミュニケーションという言葉は、communicareというラテン語から出たとされています。この言葉は「共有する」という意味だそうで、何を共有するか、というと、情報ということになりますね。
さて、このコミュニケーションはどうやってとるかというと、普通は言葉でとる、つまり言葉を通して情報を共有するのだ、と考えます。ところが有名な研究があって、医療者と患者のコミュニケーションにおいて、言葉が果たす役割はわずか7%で、残りは表情・姿勢・身振りなどが55%、声の調子が38%、つまり9割以上が言語以外の要素で決まっているのだ、と報告されています。
どうやってその「55%」なんて数字が出て来たのか知りませんが、とにかく、言葉以外のことが決定的に重要だ、ということですよね。これを見ると、ほとんど第一印象で決まってしまうような感じがします。ちなみに新潮新書に『人は見た目が9割』というベストセラーがありますが、その「9割」もこの論文からの引用のようです。
さて、がん医療に携わる私なんかは、日々患者さんやご家族とのコミュニケーションをとらねばなりませんが、そうした日常の診療や挨拶レベルとは別に、何段階も難しいものがあります。一番難しいのは、たとえば患者さんが病状を認めようとしない「否認」や、やり場のない「怒り」などに支配されている時が一つ。こういうのはある程度時間をおかないと仕方がない。またこちらが何かミスしてしまった時もそうですけど、それはがん医療に限ったことではありません。もう一つ、患者さんが精神疾患などを併発していて、まともに話ができないような場合は非常に困ります。こういうのは、往々にして精神科の先生に助けてもらわなければいけません。
それとは別に、その一つ前段階にはなりますが、困難なコミュニケーションがあります。「悪い知らせを伝える」という言葉で表されるのが代表的なもので、英語ではそのまま「breaking bad news」といいます。たとえば、予後の悪いがんを診断して病名を告げる。あなたは肺がんだとか、膵がんだとか告知する場合ですね。あと、がんの再発を告げる。今やがんでも治るものは治ると、多くの人は知っています。ただ自分は治らなかった。いろんなバッドニュースの中でも、患者さんにとっては、最初に再発を告げられる時が一番辛い、と言われています。
あと、最近の私が一番辛いのは、治らないまでもいろいろやってきたのだけれど、もう限界だ、もうこれ以上はやめよう、という、積極的治療の打ち切りの時ですね。治らない、と分かっていても、患者さんは死ぬ気なんて全然ないんですね。今までも治療をやってきた。それは効いたり効かなかったり、効いてもまた悪くなったりしてきた。けれども私は常に、患者さんに、「今度はこういう治療をしよう」と提案していた。それなのに、この期に及んで、一転して「もうやめようか」とは何事であるか。先生、あんたは俺を裏切るのか。そう言われるのは目に見えていて、だけれどもやっぱりこれ以上はやるべきではないと伝えなければいけない場合がある。これはそのうちまた取り上げます。
こういう「breaking bad news」で相手は落ち込んだり悲しんだり怒ったりしますが、そういう反応は病的ではないんですね。普通の人間ががんだと言われ、再発だと言われ、もう治療法はないと引導を渡されて、いい気分がするはずがない。それをいちいち精神科の先生に相談するわけにもいかない。
私が医者として独り立ちして肺がんを専門にやっていくことになったのは平成2(1990)年からですが、その時、私の上司の部長とともに「肺がんの患者には病名を伝えよう」という方針を決めました。当時はがんの告知はタブーに近いような時代で、どうかするとがんセンターでもはっきりとは言っていなかった。私がいたのは普通の市民病院でしたから、私と部長の二人きりの呼吸器内科以外では、がんの告知なんて誰もやらなかった。おおっぴらには邪魔されませんでしたけれど、随分と好奇の目で見られました。「先生、(患者に)がんって言うんだってね」、とかよく言われました。考えてみるとその部長は偉い人でしたね。病院のバックアップもなしにそこまで先鋭的な方針に踏み切ったのですから。従うのは直属の部下一人だけで、その部下の私はまだ20歳代のペーペーです。
その当時、肺がんだと言われてうつ状態になった患者さんのことを、精神科のドクターに相談に行ったら、「それは精神科の対象ではない」とあっさり門前払いにされました。要するに、病気ではない、と言うんですよ。「精神科というのはたとえば統合失調症とか躁うつ病などの、精神を病んだ『患者』を診るのである。がんと言われて落ち込むのは正常人の正常な反応で、病気でもなんでもない。だから精神科では扱えない」と。
今でも覚えています。こう言われました。「先生、この患者にがんだって言っちゃったんでしょ? うつになるのは当然ですよ。がんを治してやればいいんじゃないですか。そうしたら気分も良くなります」。25年以上も経って覚えているのだから、よほど恨みが深かったのが分かりますよね(笑)。
ちなみに今では精神科もそういう「正常の反応」も扱ってくれます。言われてふさぎ込むのは仕方がないにしても、その後なかなか立ち直れないのは「適応障害」という名前がついていますし、そこから本物の「うつ」として治療の対象になる場合もある、ということになっています。
さてそれで、アメリカでは日本より一足先にがんの告知が一般的になっていました。なぜアメリカではそうなっていたか、というと、患者の知る権利、とか、自己決定権、とか言われていますけど、そんなのは建前で、本音は訴訟が怖いからですよね。「どうして知らせてくれなかったのだ。おかげで自分は治療法を選べなかった。また人生の計画をし損ねた。訴える」というのを回避するための、医者側の自己防衛の要素が強い。だけどまあアメリカ人は自立傾向が強いから、「知らせてほしい」という欲求が高まったのも、嘘ではないでしょう。
それではアメリカ人はその悪いニュースを知ってどうなるか。彼らはキリスト教の神様を信じているからといって笑って運命を受け容れるか、というと、そんなことはないのですよ。いくら神様を信じていたって、死ぬのは嫌だし怖い。だからそういう「breaking bad news」も、事実を淡々と伝えて終わり、ではなくて、ちゃんと伝え方の工夫を考えています。考えるまでもなく人情は欧米人も日本人も、そんなに変わりはないのですね。
そのような「伝え方の工夫」を、コミュニケーションスキル、といいます。「スキル」というのは技能もしくは技術、という意味ですよね。よく、心がこもっていれば小手先の技術なんて要らない、とか言う人がいますが、何も考えずに裸一貫でぶちあたれ、というのですから、大概は馬鹿です(笑)。ちょっと以前に、そういう馬鹿の一人が総理大臣になって、「友愛」を連呼した挙句に日本を滅ぼしそうになりました。我々はプロですから「技術」を持たねばなりません。
代表的な伝え方の技術がSPIKESです。ロンドン生まれでカナダの大学の腫瘍内科医であったロバート・バックマン先生と、テキサスのMDアンダーソンがんセンターの精神科医のウォルター・ベイル先生が中心となってまとめられました。これは情報を伝える時に留意すべきこととして
Setting (面談の場の設定)
Perception (相手がどのくらい認識しているか)
Invitation (どのくらい知りたがっているか)
Knowledge (知識や情報を伝える)
Emotion and Empathy (相手の感情を受け止め、共感を示す)
Strategy and Summary (今後の方針を示す)
という6項目の頭文字をとったものです。
これを日本人に合わせて一部改変したSHAREプロトコールを、当時国立がんセンター東病院におられた内富庸介先生たちが作られました。ちょっと項目を見てみましょうか。
S:Supportive environment (支持的な環境設定)
| —— | プライバシーが保たれた、落ち着いた環境(たとえば、部屋、椅子、患者との距離、医師の服装などに配慮する)と十分な時間を設定する |
| —— | 患者は信頼できる、なじみのある医師に伝えられることを望んでいるため、初対面で悪い知らせを伝えることは可能な限り避ける |
| —— | 家族の同席を勧める |
H:How to deliver the bad news (悪い知らせをどのように伝えるか)
| —— | 正直に、わかりやすく、丁寧に伝える |
| —— | 患者の納得が得られるように説明をする |
| —— | 表情や口調をまったく変えずに事務的に伝えることはしない。大げさな感情的な表現や言動を使うことは避ける。断定的な口調で伝えてほしいかどうかなど、患者の意向はさまざまなので、患者の反応を見ながら伝える |
| —— | はっきりと伝えるが「がん」という言葉を繰り返し用いない |
| —— | 言葉は注意深く選択し、適切に婉曲的な表現を用いる |
| —— | 質問を促し、その質問に答える |
A:Additional information (医学的、社会的付加的情報)
| —— | 今後の治療方針のみならず患者個人の日常生活への病気の影響などについて話題にする |
| —— | 患者が相談や関心事を打ち明けることができる雰囲気を作る |
| —— | その他、患者の希望があれば代替療法やセカンド・オピニオン、余命などの話題を取り上げる |
RE:Reassurance and Emotional support (安心感と情緒的サポートの提供)
| —— | 患者に対して優しさと思いやりを示す |
| —— | 家族に対しても患者同様配慮する |
| —— | 患者の希望を維持する |
| —— | 「一緒に取り組みましょうね」と言葉をかける |
| —— | 患者に感情表出を促し、患者が感情を表出したら受け止める(例:沈黙、「どのようなお気持ちですか?」、うなずく) |
どうでしょうか。みなさんにはあまり違和感がないかもしれませんが、私なんかはこういうのを読むと、「それはそうなんだろうけどさ……」と溜息をつきたくなりますね。
バックマン先生は自分でがんの患者を診ている医者だそうですけど、彼は例外で、大体こういう決まり事みたいなのを作るのは、精神腫瘍の専門家、つまり精神科の先生なんですね。ですから、ご自分で患者に、「あなたはがんだ」とか「もう治らない」とか言う立場ではないのですよ。ただ、我々臨床の医者が患者に向かってそう説明するのをわきで聞いていて、やれお前の話し方は下手だとか、言葉遣いがなっていないとか文句つけるわけですね(笑)。だったらあんたやってくれよ、と私なんかは言いたくなります(苦笑)。もちろん、わきに座ってあれこれ「指導」してくださるのは有難いことなんでしょうけど。これだけでは実際の役にはあまり立ちそうにない。ではどうすればいいのでしょう。
目次
開く
はじめに 臨床現場でのコミュニケーション・スキルの本当のところ
第1講 がんの告知
-何を伝えてはいけないか
第2講 インフォームドコンセント
-医者というやっかいなパターナリズム的存在
第3講 「がんの告知」実践編
第4講 終末期におけるコミュニケーション
-医療者と患者のアブない関係
第5講 DNRの限界とコミュニケーション
-どうする、どう考える
対話の1 「死ぬ(べき)場所とそこにいる(べき)人」
対話の2 「末期患者の希望とは何か、それをどうつなぐか」
対話の3 「DNRをとるべきタイミング」
第6講 信用と信頼のためのコミュニケーション・スキル
第7講 死にゆく患者(ひと)と、どう話すか
課外授業 明智先生と考えるがんのコミュニケーション
あとがき
第1講 がんの告知
-何を伝えてはいけないか
第2講 インフォームドコンセント
-医者というやっかいなパターナリズム的存在
第3講 「がんの告知」実践編
第4講 終末期におけるコミュニケーション
-医療者と患者のアブない関係
第5講 DNRの限界とコミュニケーション
-どうする、どう考える
対話の1 「死ぬ(べき)場所とそこにいる(べき)人」
対話の2 「末期患者の希望とは何か、それをどうつなぐか」
対話の3 「DNRをとるべきタイミング」
第6講 信用と信頼のためのコミュニケーション・スキル
第7講 死にゆく患者(ひと)と、どう話すか
課外授業 明智先生と考えるがんのコミュニケーション
あとがき
書評
開く
ヒエラルキーに抗する「可憐さ」を獲得するために
書評者: 佐藤 恵子 (京大附属病院臨床研究総合センターEBM推進部特任准教授)
本書は,著者の國頭先生が「死に臨んだ患者さんにどう対応したらよいか」について,看護大学の一年生,つまり,ついこの前まで高校生だった人達と問答したり対話したりした様子をまとめたものである。死にゆく患者さんと話をするのは,がん領域の医療者であっても,しんどいことである。私も昔,乳がんで骨転移のある患者さんに「良くならないのだったら,いっそのこと早く死にたい」と言われて往生した。医療者がへどもどする姿がみっともないのは自明であり,なるべく避けているのが無難でもある。「この病院ではできることがなくなりましたので,転院をお勧めします」という常套句は患者さんが言われたくないセリフの一つであるが,医療側にとっては救いの抜け道であるが故に,今日もどこかで「がん難民」が生まれているのだろう。
しかし,「それをやっちゃあ,おしめえよ」と國頭先生は言う。「“どうせ治らないから”といって患者を見放すことは許されない。死んでいく患者といかに向き合い,少しでもベターな“ライフ”を過ごしてもらえるか,というのは我々の使命である」と序盤から活を入れる(「はじめに」より)。理由も単純明快で,患者さんは死を迎えるその日まで生き続けるわけだし,果てしない孤独と山のような不安を抱えながら歩くのはつらかろう,だからそれを理解している人が三途の川の手前まで付いて行かなきゃいけないのは道理でもあり,人情でもある。それに,心を穏やかに保てさえすれば限られた時間を豊かに過ごすことができるだろう。おお,シャクにさわるくらいかっこいいではないか。実際は,かわいい学生たちに囲まれて,やに下がっているひひジジイにしか見えないのだけれど。それはともかく,問題はどうやって実現するかだ。出される課題は,先生が監修されたTVドラマ『白い巨塔』(平成版)などに登場する,「恩知らずで,気紛れで,偽善者で,尊大で,臆病で,自分勝手で,欲張りで,厚かましくて,けちで助平で馬鹿」な(p.248)患者や家族と医療者が織りなす,リアルでややこしい事例である。さあ,みんなどうする?
正解のない難題を次から次へとふっかけられて,学生たちもさぞかし困ったに違いない……と思いきや,彼らは医療者として何を大事にすべきかについて,命とはなんぞやという深いところまで降りて行って考え,自分の言葉で語っている。医療現場に出たこともなく,問題には必ず正解が一つあってそれを探して答えればよいという受験勉強に慣れきっているはずなのに。しかし,そういう彼らだからこそ生き死にの問題を自分の頭で考えることが新鮮で,血がたぎるような刺激的な経験になったことは想像に難くない。彼らにとってそれが快だったか不快だったかはわからないが,彼らが出ていく先の医療現場もまた例外なく,「恩知らずで,気紛れで(中略)馬鹿な」人間が運営しているが故に,“患者の呼吸器を止めてよいという同意書に家族の署名をもらう” “技術がある限り延命治療を続ける”という行動原理が日常である可能性は大だ。その状況で“褒められはしないけれど不満や怒りも呼ばず,まあまあ納得してもらえる”道筋を立てるには,心のよりどころをたよりに自分のアタマで考え抜く力,ダークサイドをさらけ出して他者と対話する技能,矛盾を抱える不快さに耐えるしなやかさ,そして自分をも客観視してきちんとパフォーマンスできる胆力が必要であり,これを各人の自家薬籠中に持たせることがひひジジイの深慮遠謀なのである。特に医療機関のようにヒエラルキーが支配する場所では,このようなしたたかで可憐な人の存在そのものが,患者さんも医療者自身も守り,息苦しい現場を心地よい風が通り抜ける快適な空間に変える鍵になるだろう。そして,全編を通して読者にも,ちょっと立ち止まって考えてみてはどうか,腹をくくって行動してみてはどうか,とささやきかけてくるのである。“オレが後ろ盾になってやるからさ”というおまけ付きで。
教職が本務ではない國頭先生にここまでやられてシャクにさわることこの上ないが,本書は,日々の臨床で“この治療は患者の利益になっているのかな”という疑問が脳裏をよぎりまくっている人や,終末期医療にかかわる人,医療者の教育を担当する人全てにお勧めしたい。國頭先生の語り口を知る人はニタニタしながら,そうでない人も見学者として講義室に座っているような臨場感を味わいながら,「人を診る,人を育てる,人を慈しむ」意味を噛みしめられること請け合いである。
「人が生きること,死ぬこと」に深く思いをはせる
書評者: 垣添 忠生 (日本対がん協会会長/元国立がんセンター総長)
本書は,「人間國頭英夫」の全てをさらけだした書物といえよう。これだけ重く,困難で複雑なテーマをこれほど多面的に,かつ毒舌とユーモアを混えながら論じ尽くした書物を私は識らない。
これは國頭先生の30年余にわたる,日々の臨床の積み重ねに加え,多くの書物や音楽,知的関心事に継続的に目配りしてきた,人生経験と思索の豊かさから来たものであることを忘れる訳にはいかない。
そう,このように難しいテーマに真正面から向き合うと,その人の人間性と頭脳の明晰性が如実に炙り出されてくる。
國頭先生は永年にわたる国立がんセンター時代の同僚であり,現在は私がEditor in Chiefを務めるJapanese Journal of Clinical Oncology(JJCO)の編集上のキーパーソンである。加えて,國頭先生は私の妻の母の肺がんを,先生がまだ若かりしころ,東大分院から国立がんセンターに研修に来ていた時に看取ってくれた。あろうことか,その娘,つまり私の妻が小細胞肺がんになり,国立がんセンターで1年半にわたり闘病したときの担当医でもあった。つまり親子二代にわたる担当医だった訳である。それに妻の希望で私が家で妻を看取った際の,死亡診断してくれた医師も國頭先生だった。
そうした個人的な関係で本書を薦めるのでは毛頭ない。この関係性から以後親しく國頭君と言わせてもらうが,例えばp.176~180の「大きな希望,小さな希望」についての議論で,パスカル,カントからヴォルテール,仁義なき戦い,曽野綾子,親鸞,細胞増殖メカニズムなど,多岐にわたる引用と思索の縦横に展開する様子一つとってみても國頭君の該博な知識と,明晰な思考力の一端がうかがわれる。
けだし,この世の中で最も困難で深淵な課題に向き合うには,自らの人間性をここまで高める必要があるのだ。誠に,臨床とは人間性の極限を問われる行為の一つと思う。
同時に國頭君の挑発や恫喝を混じえた講義に臆せずついてきた,13名の日赤看護大の1年後期の諸君の,真摯で熱心で誠実な対応は誠に瞠目すべきである。國頭君も「あとがき」の中で,彼女たちを見ていると「この国もまだ捨てたものじゃない」,との感想があった。それは正しく,私の感想でもある。これは國頭君対彼女たちのバトルの軌跡ともいえる書物である。
本書は全ての医学生,看護学生,医師(老若を問わず),看護師(老若を問わず)の必読書といえる。この内容で2,100円はいかにも安い。数日かけて読み通し,「人が生きること,死ぬこと」に深く思いを致すことは,皆さまのその後の人生に多大なインパクトを与えることは必定,と私は思う。
書評者: 佐藤 恵子 (京大附属病院臨床研究総合センターEBM推進部特任准教授)
本書は,著者の國頭先生が「死に臨んだ患者さんにどう対応したらよいか」について,看護大学の一年生,つまり,ついこの前まで高校生だった人達と問答したり対話したりした様子をまとめたものである。死にゆく患者さんと話をするのは,がん領域の医療者であっても,しんどいことである。私も昔,乳がんで骨転移のある患者さんに「良くならないのだったら,いっそのこと早く死にたい」と言われて往生した。医療者がへどもどする姿がみっともないのは自明であり,なるべく避けているのが無難でもある。「この病院ではできることがなくなりましたので,転院をお勧めします」という常套句は患者さんが言われたくないセリフの一つであるが,医療側にとっては救いの抜け道であるが故に,今日もどこかで「がん難民」が生まれているのだろう。
しかし,「それをやっちゃあ,おしめえよ」と國頭先生は言う。「“どうせ治らないから”といって患者を見放すことは許されない。死んでいく患者といかに向き合い,少しでもベターな“ライフ”を過ごしてもらえるか,というのは我々の使命である」と序盤から活を入れる(「はじめに」より)。理由も単純明快で,患者さんは死を迎えるその日まで生き続けるわけだし,果てしない孤独と山のような不安を抱えながら歩くのはつらかろう,だからそれを理解している人が三途の川の手前まで付いて行かなきゃいけないのは道理でもあり,人情でもある。それに,心を穏やかに保てさえすれば限られた時間を豊かに過ごすことができるだろう。おお,シャクにさわるくらいかっこいいではないか。実際は,かわいい学生たちに囲まれて,やに下がっているひひジジイにしか見えないのだけれど。それはともかく,問題はどうやって実現するかだ。出される課題は,先生が監修されたTVドラマ『白い巨塔』(平成版)などに登場する,「恩知らずで,気紛れで,偽善者で,尊大で,臆病で,自分勝手で,欲張りで,厚かましくて,けちで助平で馬鹿」な(p.248)患者や家族と医療者が織りなす,リアルでややこしい事例である。さあ,みんなどうする?
正解のない難題を次から次へとふっかけられて,学生たちもさぞかし困ったに違いない……と思いきや,彼らは医療者として何を大事にすべきかについて,命とはなんぞやという深いところまで降りて行って考え,自分の言葉で語っている。医療現場に出たこともなく,問題には必ず正解が一つあってそれを探して答えればよいという受験勉強に慣れきっているはずなのに。しかし,そういう彼らだからこそ生き死にの問題を自分の頭で考えることが新鮮で,血がたぎるような刺激的な経験になったことは想像に難くない。彼らにとってそれが快だったか不快だったかはわからないが,彼らが出ていく先の医療現場もまた例外なく,「恩知らずで,気紛れで(中略)馬鹿な」人間が運営しているが故に,“患者の呼吸器を止めてよいという同意書に家族の署名をもらう” “技術がある限り延命治療を続ける”という行動原理が日常である可能性は大だ。その状況で“褒められはしないけれど不満や怒りも呼ばず,まあまあ納得してもらえる”道筋を立てるには,心のよりどころをたよりに自分のアタマで考え抜く力,ダークサイドをさらけ出して他者と対話する技能,矛盾を抱える不快さに耐えるしなやかさ,そして自分をも客観視してきちんとパフォーマンスできる胆力が必要であり,これを各人の自家薬籠中に持たせることがひひジジイの深慮遠謀なのである。特に医療機関のようにヒエラルキーが支配する場所では,このようなしたたかで可憐な人の存在そのものが,患者さんも医療者自身も守り,息苦しい現場を心地よい風が通り抜ける快適な空間に変える鍵になるだろう。そして,全編を通して読者にも,ちょっと立ち止まって考えてみてはどうか,腹をくくって行動してみてはどうか,とささやきかけてくるのである。“オレが後ろ盾になってやるからさ”というおまけ付きで。
教職が本務ではない國頭先生にここまでやられてシャクにさわることこの上ないが,本書は,日々の臨床で“この治療は患者の利益になっているのかな”という疑問が脳裏をよぎりまくっている人や,終末期医療にかかわる人,医療者の教育を担当する人全てにお勧めしたい。國頭先生の語り口を知る人はニタニタしながら,そうでない人も見学者として講義室に座っているような臨場感を味わいながら,「人を診る,人を育てる,人を慈しむ」意味を噛みしめられること請け合いである。
「人が生きること,死ぬこと」に深く思いをはせる
書評者: 垣添 忠生 (日本対がん協会会長/元国立がんセンター総長)
本書は,「人間國頭英夫」の全てをさらけだした書物といえよう。これだけ重く,困難で複雑なテーマをこれほど多面的に,かつ毒舌とユーモアを混えながら論じ尽くした書物を私は識らない。
これは國頭先生の30年余にわたる,日々の臨床の積み重ねに加え,多くの書物や音楽,知的関心事に継続的に目配りしてきた,人生経験と思索の豊かさから来たものであることを忘れる訳にはいかない。
そう,このように難しいテーマに真正面から向き合うと,その人の人間性と頭脳の明晰性が如実に炙り出されてくる。
國頭先生は永年にわたる国立がんセンター時代の同僚であり,現在は私がEditor in Chiefを務めるJapanese Journal of Clinical Oncology(JJCO)の編集上のキーパーソンである。加えて,國頭先生は私の妻の母の肺がんを,先生がまだ若かりしころ,東大分院から国立がんセンターに研修に来ていた時に看取ってくれた。あろうことか,その娘,つまり私の妻が小細胞肺がんになり,国立がんセンターで1年半にわたり闘病したときの担当医でもあった。つまり親子二代にわたる担当医だった訳である。それに妻の希望で私が家で妻を看取った際の,死亡診断してくれた医師も國頭先生だった。
そうした個人的な関係で本書を薦めるのでは毛頭ない。この関係性から以後親しく國頭君と言わせてもらうが,例えばp.176~180の「大きな希望,小さな希望」についての議論で,パスカル,カントからヴォルテール,仁義なき戦い,曽野綾子,親鸞,細胞増殖メカニズムなど,多岐にわたる引用と思索の縦横に展開する様子一つとってみても國頭君の該博な知識と,明晰な思考力の一端がうかがわれる。
けだし,この世の中で最も困難で深淵な課題に向き合うには,自らの人間性をここまで高める必要があるのだ。誠に,臨床とは人間性の極限を問われる行為の一つと思う。
同時に國頭君の挑発や恫喝を混じえた講義に臆せずついてきた,13名の日赤看護大の1年後期の諸君の,真摯で熱心で誠実な対応は誠に瞠目すべきである。國頭君も「あとがき」の中で,彼女たちを見ていると「この国もまだ捨てたものじゃない」,との感想があった。それは正しく,私の感想でもある。これは國頭君対彼女たちのバトルの軌跡ともいえる書物である。
本書は全ての医学生,看護学生,医師(老若を問わず),看護師(老若を問わず)の必読書といえる。この内容で2,100円はいかにも安い。数日かけて読み通し,「人が生きること,死ぬこと」に深く思いを致すことは,皆さまのその後の人生に多大なインパクトを与えることは必定,と私は思う。