MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.07.13
Medical Library 書評・新刊案内
尾身 茂 著
《評者》井戸田 一朗(しらかば診療所院長)
国際保健のレジェンドと私,そして生涯初のバズり体験
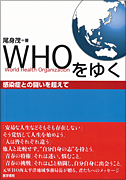 私は,現在は一介の開業医ですが,2003~05年にWHO南太平洋事務所にて,結核対策専門官として南太平洋15か国における結核感染症対策に携わる機会がありました。赴任前の2002年10月,当時WHO西太平洋地域事務局(WPRO)の事務局長だった尾身茂先生の面接を受けました。ちなみに私をWHOに誘ったのは,現WPRO事務局長の葛西健先生です。葛西先生は私を事務局長室に連れて行き,尾身先生を紹介してくださいました。当時の私は30歳代前半で,WHO内の右も左もわからず,国際保健業界で既にレジェンドの尾身先生を前に,カチコチに緊張しました。尾身先生は,テレビの印象とは異なり,どちらかというと親分肌の方でした。緊張でろくに返事もできない私を,葛西先生が助けてくれたのを覚えています。
私は,現在は一介の開業医ですが,2003~05年にWHO南太平洋事務所にて,結核対策専門官として南太平洋15か国における結核感染症対策に携わる機会がありました。赴任前の2002年10月,当時WHO西太平洋地域事務局(WPRO)の事務局長だった尾身茂先生の面接を受けました。ちなみに私をWHOに誘ったのは,現WPRO事務局長の葛西健先生です。葛西先生は私を事務局長室に連れて行き,尾身先生を紹介してくださいました。当時の私は30歳代前半で,WHO内の右も左もわからず,国際保健業界で既にレジェンドの尾身先生を前に,カチコチに緊張しました。尾身先生は,テレビの印象とは異なり,どちらかというと親分肌の方でした。緊張でろくに返事もできない私を,葛西先生が助けてくれたのを覚えています。
*
COVID-19流行による混乱のさなかにある2020年5月11日,参議院予算委員会にて国会議員の質問に対する尾身茂先生の答弁があり,優しい口調で語り掛けるように丁寧にお答えになる姿を動画で見ました。国内外の会議において雄弁で大胆にご発言をされる尾身先生を私は知っているので,「ちょっと意外……」と思いつつ見ていたところ,答弁を妨げるようなやじや,期待した内容の答弁が得られなかったことに対するいら立ちの声が上がり驚きました。
あの尾身先生がこんなに優しくお話をされているのに,その国会議員は尾身先生がどのような方かご存じないのかと思い,尾身先生に初めてお会いしたときのエピソードをツイートしたところ,2万以上の「いいね」と1万近いリツイートがなされ,生涯初めてバズってしまいました(https://twitter.com/itochama/status/1260012057451061249)。出版社によると,このツイートの翌日には本書の在庫が尽きてしまったそうです。
WHOで活躍した尾身先生が日本に帰国され,新型インフルエンザ,COVID-19と,わが国の感染症危機に要所要所で携わっているのは極めて幸運なことです。前述の国会議員をはじめ多くの日本人にその事実を知っていただきたいという思いでした。ここまで拡散するとは予想しませんでしたが,私が国際保健を離れてしばらく経ち,ツイッターのおかげとはいえ,WHOや国際保健とのかかわりを思い起こす機会になったことに,不思議な縁を感じます。
2011年に出版された本書は,尾身先生の半自伝的エッセイです。青春時代の彷徨に始まり,WPRO地域のポリオ根絶に向けたゼロからのスタートと達成,SARS対策のためWHOが中国と香港に渡航延期勧告を出す際のスリリングな展開,中国政府とのあつれきを覚悟しながらも筋を通された姿勢と,これだけのスケールの危機や困難をくぐり抜けて来た日本人がどれだけいるのでしょう。リーダーたるもの,人の立場に立って考える能力が必要であり(これは私もツイートした内容),また口の堅さも重要と,ニヤリとしてしまうエピソードも紹介されています。
パンデミック対策の主要ポイントとして,まず封じ込めを試み,発生初期のピークの到来を避けることで,社会機能を維持し死亡者を最小限に食い止めることが挙げられます。現在COVID-19対策において日本が取っている戦略は,新型インフルエンザ流行前の2008年には既に立てられており,このセオリーに基づく日本のCOVID-19対策が今のところうまく行っていることは周知の通りです。本書には,パンデミック対策の教訓が明快にまとめられていますが,「喉元過ぎれば熱さ忘れる」です。尾身先生による提言が,果たしてどの程度,その後の感染症対策の準備に活用されたのか,私たちは振り返る必要があると思います。文明と感染症の関係についての記述では,「文明が続く限り,新たな感染症を含む健康被害が発生することは不可避である」とはっきりと述べられており,私たちの生き方や哲学にまで問い掛けられています。
*
2005年3月,私がWHOを退職することになり,マニラでディブリーフィングを行うことになりました。その最中に結核地域アドバイザーだったDong Il Ahn先生という韓国人の方が,「Ichiro(私の名前)はよくやってくれたから,WHOを去る前に事務局長に会ってもらう資格がある」と,多忙な尾身先生の時間を捻り出す交渉をしてくださり,尾身先生にお目に掛かりました。対面では2度目です。
WHOで南太平洋諸国を2年間わたり歩いたことを報告すると,尾身先生は「そうか,それはお疲れさま」と,初めてお会いした時よりはくだけた調子で声を掛けてくださいました。前回に比べると私なりに自信が付いた状態でしたがそれでも緊張していて,手にしたデジカメで尾身先生との記念のツーショットをAhn先生に撮ってもらうのをすっかり忘れてしまいました。いつかまた尾身先生にお会いできる機会があれば,本書にサインをいただきたいと思っています。
A5・頁176 定価:本体2,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-01427-4


小橋 元,近藤 克則,黒田 研二,千代 豪昭 編
《評者》武田 裕子(順大教授・医学教育学)
「SDH」の視点を重視したポストコロナ時代の必読書
 新型コロナウイルスの出現により,私たちの社会はさまざまな影響を受けました。医学的には,感染症(COVID-19)の診断と治療,予防のためのワクチン開発など多くの議論がなされています。一方,今回のパンデミックは,感染症が医療・医学の専門的な閉じた世界にとどまらず,人の行動や暮らし,経済活動など社会と密接につながっていることをまざまざと映し出しました。さらに,こうした社会的な要因が,健康を大きく左右することも示されました。例えば,COVID-19の死亡率には所得や人種などにより差があることが欧米各国の統計で明らかになっています。
新型コロナウイルスの出現により,私たちの社会はさまざまな影響を受けました。医学的には,感染症(COVID-19)の診断と治療,予防のためのワクチン開発など多くの議論がなされています。一方,今回のパンデミックは,感染症が医療・医学の専門的な閉じた世界にとどまらず,人の行動や暮らし,経済活動など社会と密接につながっていることをまざまざと映し出しました。さらに,こうした社会的な要因が,健康を大きく左右することも示されました。例えば,COVID-19の死亡率には所得や人種などにより差があることが欧米各国の統計で明らかになっています。
こうした構造的な問題を「健康の社会的決定要因(Social Determinants of Health:SDH)」といいます。「SDH」が医学教育で取り上げられるようになったのはこの数年ですが,本書は1999年に初版が出版された時から,その序に「医療を理解するためには,先端科学の進歩にのみ目を奪われてはなりません。思想や政治経済など,社会的背景を理解することが特に大切です」と述べられ,SDHの視点が一貫して取り入れられてきたことがわかります。
本書の第1章は,医療の基本に「人権」を据え,国際人権から書き起こされています。「患者の権利」はどの教科書にも当たり前に書かれていますが,自由と平等が平和の礎であり,健康は一人ひとりの権利であることを明確に述べている医学書はほとんどありません。第2章に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
