MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.01.13
Medical Library 書評・新刊案内
これでわかる!
抗菌薬選択トレーニング
感受性検査を読み解けば処方が変わる
藤田 直久 編
《評者》青木 眞(感染症コンサルタント)
「菌トレ」本で,今こそ感受性結果の見かたを鍛えよう
 2016年5月に開催された先進国首脳会議,通称「伊勢志摩サミット」で薬剤耐性(AMR)の問題が取り上げられ,当時の塩崎恭久厚労大臣のイニシアチブの下さまざまな企画が立ち上げられた。国立国際医療研究センターにある国際感染症センターの活動も周知の通りである。
2016年5月に開催された先進国首脳会議,通称「伊勢志摩サミット」で薬剤耐性(AMR)の問題が取り上げられ,当時の塩崎恭久厚労大臣のイニシアチブの下さまざまな企画が立ち上げられた。国立国際医療研究センターにある国際感染症センターの活動も周知の通りである。
にもかかわらず,広域抗菌薬の代表とも言えるカルバペネム系抗菌薬の消費が,日本だけで世界の7割を占めるという状況から,(一部の意識の高い施設を除いて)大きく変わった印象が現場に少ない。もちろん,最大の原因は「感染症診療の原則とその文化」の広がりが均一でないことによる。しかし,さらに突き詰めると,実は「抗菌薬感受性検査の読み方」が十分に教育できていないことも大きな理由の一つである。感受性検査の結果をS,I,Rに分類して単純に「Sを選ぶ」ことに疑問を抱かない問題と言ってもよい。一つひとつの症例で,ある抗菌薬が選ばれる背景には,感受性が「S」であること以外にも,微生物学的・臨床的・疫学的など多くの理由がある。その理解なしに,適切な抗菌薬の選択は不可能あるいは危険なのである。評者も,群馬大におられた佐竹幸子先生らとともにNPO法人EBIC研究会でのセミナーの一環として「抗菌薬感受性検査の読み方」シリーズを10年以上にわたり講義してきた。その講義は現在,日本感染症教育研究会(通称IDATEN)に引き継がれている。しかし,そのエッセンスを伝える書物は本書の発行まで皆無であった。
以下に,本書よりポイントの一部を紹介しよう。
①経口薬での狭域化の際には,腸管吸収率を勘案した上で,抗菌スペクトラムの狭い抗菌薬を選択する(主な経口セファロスポリン系,ペニシリン系抗菌薬の薬物動態の表なども有用)。〔pp.57-58〕
②同じグラム陰性桿菌(Klebsiella pneumoniae)による感染症で,かつ同じ感受性検査結果であっても,「尿路感染症」「肝膿瘍」などのように病態が異なれば,選択すべき抗菌薬も変わる(本書は一見,単なる症例集に見えるが,かなり丁寧に作り込まれている。例えば,ある「ツボ」の部分の設定のみを変更した全く同一の2症例を意図的に並べ,その「ツボ」の理解の重要性を際立たせる工夫もされている)。〔pp.65-68〕
③感受性検査結果で全ての抗菌薬が「S」であっても,菌種によっては耐性化が予想されるため,選択すべき抗菌薬が決まっていることもある(特に染色体性にAmpC型βラクタマーゼ産生遺伝子を有する細菌Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp.の場合)。〔pp.75-76〕
④患者の状態は改善傾向だが,培養で現在使用中の抗菌薬に耐性の菌が検出された症例(抗菌薬使用中に培養で検出された菌が原因微生物とは限らない。非常によくある臨床の風景)。〔pp.91-92〕
本書の愛称は「菌トレ」だそうだ。「ベテランの自分に,今さら“キントレ”など必要ない」と思われる方も,ぜひお手に取って症例問題に挑戦いただきたい。思いの外正解できず慌てるに違いない。「菌トレ」本が,多くの読者を得ることを願うばかりである。
評者が,藤田直久先生のおられる京都府立医大に年数回伺い,感染症の勉強をさせていただくようになって早いもので15年ほどになる。抗菌薬適正使用の文化を育てることが困難な「大学」という施設で,忍耐強く教育・啓発活動を行い,耐性菌対策を続けてこられた本書執筆陣の藤田先生,中西雅樹先生,小阪直史先生らのご尽力に,あらためて敬意を表する次第である。
B5・頁192 定価:本体3,600円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03891-1


花輪 壽彦 編
《評者》松田 隆秀(聖マリアンナ医大教授・総合診療内科学)
いかなる診療科の専門医にも薦める座右の解説書
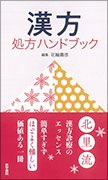 西洋医学の知恵では十分に対応できない患者さんに対し,漢方の知恵を加えることができればどれだけ素晴らしいことだろうか――私が日常診療で感じていることの一つである。これまで漢方の解説書を手にする時には,これから漢方の世界に入ることに対しての気持ちの切り換えが必要であった。このような現象は私だけであろうか? 電車の中で本書を手にしてパラパラと数ページを眺めてみたが,本書に吸い込まれるように自然体で全ページを速読することとなった。漢方専門医ではない私にとって,心構えなしで目を通せる漢方解説書との初めての出合いであった。
西洋医学の知恵では十分に対応できない患者さんに対し,漢方の知恵を加えることができればどれだけ素晴らしいことだろうか――私が日常診療で感じていることの一つである。これまで漢方の解説書を手にする時には,これから漢方の世界に入ることに対しての気持ちの切り換えが必要であった。このような現象は私だけであろうか? 電車の中で本書を手にしてパラパラと数ページを眺めてみたが,本書に吸い込まれるように自然体で全ページを速読することとなった。漢方専門医ではない私にとって,心構えなしで目を通せる漢方解説書との初めての出合いであった。
本書を薦める理由として,以下の点を挙げてみたい。
①北里大東洋医学総合研究所のスタッフおよび同門会メンバーが執筆しているため,漢方の概念と用語が一貫して統一されている。
②編者の花輪壽彦氏が執筆されている「漢方の基本知識」の章はコンパクトな解説文でありながら,漢方の概念が自然に身につくような工夫がなされている。
③非漢方専門医である読み手でも違和感なく漢方の世界に入っていくことができるように熟考された,熱意のこもった力作である。
④症状や疾患の項では,まず西洋医学に基づいたそれぞれの病態や疾患概念,治療が示され,その後に東西両医学の長所を生かした漢方処方が解説されている。いきなり漢方を全面に押しつけない構成がお見事である。
⑤本文に加えてcolumn,memo,Advanced Courseの項目があり,漢方のさま...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
