MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2019.10.14
Medical Library 書評・新刊案内
坂本 穆彦 編
《評者》菅間 博(杏林大教授・病理学/日本甲状腺病理学会理事長)
甲状腺細胞診に携わる検査技師,病理医,臨床医に
 このたび,坂本穆彦氏の編集による『甲状腺細胞診アトラス――報告様式運用の実際』が発行された。
このたび,坂本穆彦氏の編集による『甲状腺細胞診アトラス――報告様式運用の実際』が発行された。
編集の坂本氏は細胞診断学の重鎮であり,これまでさまざまな細胞診に関する書籍を発行している。特に甲状腺の細胞診に関しては,坂本氏は本邦のパイオニアと言っても過言ではない。本書の目玉である「診断カテゴリーに特徴的な細胞所見」は,坂本氏の教授を受け,甲状腺細胞診の第一線で活躍する細胞検査士が執筆を担当している。選び抜かれた多数の細胞写真とともに,日々の業務の中で役に立つ診断のポイントが解説されている。甲状腺に特化した細胞診アトラスとして価値が高く,甲状腺の細胞診に携わる全ての検査技師,病理医,臨床医にとって有用と考えられる。
本書の「診断カテゴリー」は,「甲状腺癌取扱い規約」第7版(2015年)の細胞診の報告様式の判定区分である。甲状腺細胞診の報告様式は,国内の施設間で差が見られる。取扱い規約第7版の報告様式は濾胞性腫瘍を「鑑別困難」から切り分け,その良悪性判定を保留するべセスダシステム報告様式に準じている。「総論」で編者が主張するように,第7版の報告様式が,現時点では本邦の甲状腺診療に最も適していると考えられる。この報告様式の運用の実際を詳述する本書が,その普及に貢献し,国内の報告様式が統一されることが望まれる。
本書の「総論」の後半は,廣川満良氏が担当している。廣川氏は甲状腺の超音波ガイド下に穿刺吸引細胞診検査を自ら行い,診断する病理専門医である。甲状腺細胞診の検体採取と検体処理の具体的な方法を解説している。甲状腺の細胞診の初心者が陥りやすい基本的過ちについても記載している。甲状腺の細胞診症例の少ない施設において大いに参考になる。さらに,液状処理法(liquid-based cytology;LBC)の導入についても解説している。LBCはさまざまな利点があるが,蛋白の免疫染色による発現解析や遺伝子DNAの変異解析にも有用である。今後,LBCは普及すると考えられるが,その際の鏡検上の注意点についても触れている。
本書の第3章では,「NIFTPをめぐる諸問題」について解説されている。2017年に刊行された甲状腺腫瘍のWHO分類(第4版)では,新たに「境界悪性腫瘍」の概念が導入された。この概念の流布が,本邦の甲状腺診療に混迷をもたらす可能性が指摘されている。このため「境界悪性腫瘍」のうち特にNIFTPについては,米国における導入の経緯と,本邦における診断と治療上の問題点が,甲状腺を専門とする病理医と臨床医の立場から整理,解説されている。今後,NIFTPを含む「境界悪性腫瘍」の扱いについては,本解説事項を参考に,遺伝子異常などのデータを加味して検討されるものと考えられる。
現在,「甲状腺癌取扱い規約」の改訂作業が進められている。第8版でも第7版の細胞診の報告様式の判定区分は維持される予定である。本書の甲状腺細胞診の手引きとしての有用性は変わらない。
B5・頁256 定価:本体10,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03909-3


蛍光眼底造影ケーススタディ
エキスパートはFA・IA・OCTAをこう読み解く
飯田 知弘 編
《評者》髙橋 寛二(関西医大主任教授・眼科学)
見事な写真と解説で実践的な蛍光眼底造影を学べる
 近年,眼底疾患に対してさまざまな原理に基づいた画像検査法が発達してきており,一つの眼底疾患に対して多面的に種々の画像検査を行うことによって,より確かに,そして精密に臨床診断を行うmultimodal imagingが主流となってきている。眼底疾患に対して造影剤を用いて異常を検出する蛍光眼底造影は,フルオレセイン蛍光眼底造影ではおおよそ60年,インドシアニングリーン蛍光眼底造影では約40年の歴史を持つ画像検査であるが,これらの造影は,現在まで実に多くの眼底疾患の疾患概念の確立や病態解明,治療評価に深く寄与し,眼底画像診断のgold standardとしての歴史を誇ってきた。しかし近年,精度の高い光干渉断層計(OCT)や光干渉断層血管撮影(OCT angiography)をはじめとする新しい画像診断に目を奪われ,蛍光眼底造影の読影の系統的な学習はなおざりにされる傾向がある。
近年,眼底疾患に対してさまざまな原理に基づいた画像検査法が発達してきており,一つの眼底疾患に対して多面的に種々の画像検査を行うことによって,より確かに,そして精密に臨床診断を行うmultimodal imagingが主流となってきている。眼底疾患に対して造影剤を用いて異常を検出する蛍光眼底造影は,フルオレセイン蛍光眼底造影ではおおよそ60年,インドシアニングリーン蛍光眼底造影では約40年の歴史を持つ画像検査であるが,これらの造影は,現在まで実に多くの眼底疾患の疾患概念の確立や病態解明,治療評価に深く寄与し,眼底画像診断のgold standardとしての歴史を誇ってきた。しかし近年,精度の高い光干渉断層計(OCT)や光干渉断層血管撮影(OCT angiography)をはじめとする新しい画像診断に目を奪われ,蛍光眼底造影の読影の系統的な学習はなおざりにされる傾向がある。
本書では,蛍光眼底造影の基礎が学べる総論に続き,25項目の疾患・病態について,「Point」,「疾患の概要」,「ケースで学ぶ所見の読み方」,「押さえておきたい読影ポイント」,「バリエーションとピットフォール」の5つの面から蛍光眼底造影の読影ポイントと知識がエキスパートの筆者の先生方によって要領よくまとめられている。提示症例とその造影写真,その他の画像検査写真は全て文句の付けようがない典型的で綺麗な画像である。このテキストを通読することによって,見事な写真と解説を基に,極めて実践的な形で蛍光眼底造影の知識を自然に学ぶことができる。さらにかなりの項目では,眼底自発蛍光や最新のOCT angiographyの画像も解説の中に組み入れられており,multimodal imagingの観点から病態の新しい解釈を学ぶこともできる。
蛍光眼底造影を初めて学ぶ方,そしてmultimodal imagingの観点からいま一度系統的に蛍光眼底造影を学び直し,診断力をアップしたい先生方に広くお薦めしたいニューテキストである。
B5・頁312 定価:本体9,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03841-6


山下 康行 著
《評者》柴田 綾子(淀川キリスト教病院産婦人科)
画像診断を超えた200個のクリニカルパール
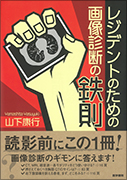 「画像検査を学ぶ本だ」という予想をはるかに超えていた。救急室や外来で出合う疾患の特徴的な画像が次々と登場し,経験知が詰まったクリニカルパールがテンポよく紹介された本であった。画像診断は「知っていれば診断できる」ことが多い。逆に言うと,知らなければ見過ごしてしまう所見がたくさんある。この本は,あなたの「診断できる」を確実に増やしてくれる一冊である。
「画像検査を学ぶ本だ」という予想をはるかに超えていた。救急室や外来で出合う疾患の特徴的な画像が次々と登場し,経験知が詰まったクリニカルパールがテンポよく紹介された本であった。画像診断は「知っていれば診断できる」ことが多い。逆に言うと,知らなければ見過ごしてしまう所見がたくさんある。この本は,あなたの「診断できる」を確実に増やしてくれる一冊である。
この本がすごいのは,画像診断の「周辺」までクリニカルパールでカバーしているところだ。第1章「画像診断総論」で取り上げられている以下などは,普段なら難しくて読み飛ばしてしまいそうな内容だが,簡潔なメッセージ(鉄則)とまとめで読みやすくなっている。
・画像検査法の基礎(CT/MRIの仕組みや設定,オーダーのしかたは?)
・画像検査の選びかた(PETやシンチグラフィーが必要なときは?)
各章は臓器別になっており「これは...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
