MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2018.12.03
Medical Library 書評・新刊案内
森山 寛 監修
大森 孝一,藤枝 重治,小島 博己,猪原 秀典 編
《評者》甲能 直幸(佼成病院院長/杏林大特任教授・耳鼻咽喉科・頭頸科)
今日からの臨床に自信を与えてくれる
 第一線の診療にすぐに役立つ,最新の総合診療事典として出版された本書は約700ページの中に322項目を収載し抜群の網羅性を誇り,実に読みやすく理解しやすい構成となっている。事典の本来の目的である調べたい項目をチェックするだけでなく,現在のこの領域での医療の状況を確認する目的で通読しても良い。まさに耳鼻咽喉科・頭頸部外科の最良の治療指針である。
第一線の診療にすぐに役立つ,最新の総合診療事典として出版された本書は約700ページの中に322項目を収載し抜群の網羅性を誇り,実に読みやすく理解しやすい構成となっている。事典の本来の目的である調べたい項目をチェックするだけでなく,現在のこの領域での医療の状況を確認する目的で通読しても良い。まさに耳鼻咽喉科・頭頸部外科の最良の治療指針である。
総論として,患者の診かた(1章)や基本となる検査(2章)が記述されている。診療科の特殊性,専門性が再確認され,症状に合わせてどのように診断を進めるかをよく理解することができる。この領域の専門医のみならず,他科の医師にも非常に参考になると思われる。続いて3~8章では,本書の大部分を占める疾患の解説,治療方法,薬の使い方の具体例,予後,患者説明のポイントが領域別に,詳細かつ簡潔に記述されている。限られた紙面に,よくこれだけの情報をまとめたものだと感嘆する。著者たちの英知の結集である。要所に挿入された写真や図表も疾患の特徴,診断の要点などをまとめており,理解に役立つ。次の9章では,本領域で扱う疾患の大部分が感覚器であるが故の機能低下・損失に対する医療機器による機能の代償が記述されている。この分野の進歩は近年目覚ましいものがあるが,現状での最先端の機種が紹介されている。そして10章で述べられているリハビリテーションも,機能回復には重要な医療であり,超高齢社会がもたらす問題点でもある加齢による嚥下機能低下への対策も記述されている。すなわち疾患の治療のみならず,治療後の各種機能の保持に対する対応策の現状が解説されている。最後に付録として,研修カリキュラム,用語・手引き・診断基準,公的文書作成の補助が書かれている。至れり尽くせりである。
本書では項目の配置に工夫がなされており,症状に対する診断の進め方,疾患の治療法,続発する機能低下への対応,リハビリテーションと進んでいく。流れるように読み進むことができ,理解することができる。これが本事典の特徴であり,見事なアイデアである。この一冊で本領域で研修する医師に必要とされる知識の全てが網羅されているし,耳鼻咽喉科専門医をめざす医師に必要な標準的な治療法も示されている。加えて,各項目では丁寧にしかも要領よくポイントを押さえた解説がなされており,耳鼻咽喉科・頭頸部外科医となって45年が経過した評者にとっても非常に参考になり,ためになる一冊である。ハンディタイプで持ち運びに便利であり,診察スペースにチョコンと置いても邪魔にならない。今日からの臨床に自信を与えてくれる一冊であると思う。
A5・頁736 定価:本体16,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03452-4


Kenneth A. Ellenbogen,Karoly Kaszala 編
髙野 照夫,加藤 貴雄 監訳
伊原 正 訳
《評者》澤 芳樹(阪大大学院教授・心臓血管外科学)
世界的に高名なDr. Ellenbogenによる原書を万全の体制で日本語訳
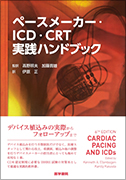 このほど,医学書院から上梓された『ペースメーカー・ICD・CRT実践ハンドブック』は,植込み型デバイス治療では世界的に第一人者とされる米バージニア・コモンウェルス大のDr. Ellenbogenの編集により版を重ねている名著『Cardiac Pacing and ICDs』の第6版を翻訳した書籍である。原書の名前を聞いて,500ページを超える英文版を苦労して読み解いたことを思い出す,不整脈のデバイス治療にかかわる医師は少なくないはずである。
このほど,医学書院から上梓された『ペースメーカー・ICD・CRT実践ハンドブック』は,植込み型デバイス治療では世界的に第一人者とされる米バージニア・コモンウェルス大のDr. Ellenbogenの編集により版を重ねている名著『Cardiac Pacing and ICDs』の第6版を翻訳した書籍である。原書の名前を聞いて,500ページを超える英文版を苦労して読み解いたことを思い出す,不整脈のデバイス治療にかかわる医師は少なくないはずである。
原書の『Cardiac Pacing and ICDs』第6版は改訂に際し,植込み型デバイス治療に関する数多くの新知見を取り入れて大幅なリニューアルを行ったようである。随所に心電図,X線写真,シェーマを取り入れた解説は非常にわかりやすく,ペーシングモードなどの複雑で細かい内容もイメージがしやすい。米国アマゾンのレビューでは,星5つを付けているレビューアーもいるくらいである。
いくら原書の評価が高いとしても,日本語訳が読みづらくては読者にとって役に立つ書籍にはならないであろう。しかしながら,本書については最初の数ページを読めば,その心配は杞憂に終わると思われる。というのも,翻訳は自ら医療者向けの英語の教科書も手掛ける,医用工学の研究・臨床工学の教育に長年携わってこられた伊原正先生(鈴鹿医療科学大教授)がお一人で担当されており,文章に一貫性が保たれている。その上で,循環器医として豊富な経験をお持ちの髙野照夫先生(日医大名誉教授),加藤貴雄先生(国際医療福祉大三田病院特任教授)が医学用語や手技の翻訳に関して監訳者としてアドバイスしたようである。ご存じの通り植込み型デバイスは医学と工学が高度に統合された技術であるため,本書の翻訳体制はとても望ましいといえる。
循環器疾患の治療は,薬物治療,心臓血管外科手術,カテーテル検査治療と合わせて植込み型デバイスが重要な役割を果たしている。その先にある循環器再生医療も単独で治療が行えるわけでなく,相互に補完して初めて有効な治療となる。中でもデバイス治療は,徐脈性不整脈から始まり,頻脈性不整脈,心不全とその適応が大きく広がった。特に心不全に関してはCRTによる心室逆リモデリングについても述べられており,本書の広汎な内容と奥行きの深さを感じさせるものである。
デバイスは日々進歩し,臨床現場への普及は進んでいるものの,実は機器メーカーごとに仕様が異なる部分も多い。そのため,病態に応じた設定などについてはメーカーからの情報に依存する部分が大きかった。本書ではその弱点を補うため,おのおののメーカーの仕様を一覧表にまとめ,各デバイスのメリット,デメリット,植込み時のコツなど臨床的な視点からポイントを絞ってわかりやすく記載されている。さらに技術的仕様の違いだけでなく,デバイス使用による血行動態の変化,デバイスモードの選択方法なども体系的にまとめられており,最終的なアウトカムにつながる指針が示されている。
昨今,循環器疾患の治療に際してハートチームの重要性が唱えられている。デバイスの植込みには主に循環器内科医がかかわるが,リード抜去や合併症の治療の際にはわれわれ心臓外科医もハートチームの一員としてオペ室に入ることもある。本書により植込み型デバイスに対する総合的な理解が深まり,医師,看護師,コメディカルスタッフがチームとしてよりレベルの高い医療をめざしていくことを期待する。
B5・頁544 定価:本体13,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03599-6


八幡 紕芦史 編著
竹本 文美,田中 雅美,福内 史子 著
《評者》徳田 安春(群星沖縄臨床研修センター長)
つい見入ってしまう動画と,学会や講演会の違いは?
 言いたいことを言うと伝わらない,というサブタイトル。衝撃的ですね。故・日野原重明先生は,「医師は聞き上手になりなさい,患者は話し上手になりなさい」と講演でよくおっしゃっていました。話し上手な医師が多いように思われていますが,実は言いたいことが伝わっていないケースが多いのも事実です。その原因が,単に言いたいことを言っていたからだ,というのが本書の主張です。
言いたいことを言うと伝わらない,というサブタイトル。衝撃的ですね。故・日野原重明先生は,「医師は聞き上手になりなさい,患者は話し上手になりなさい」と講演でよくおっしゃっていました。話し上手な医師が多いように思われていますが,実は言いたいことが伝わっていないケースが多いのも事実です。その原因が,単に言いたいことを言っていたからだ,というのが本書の主張です。
読者の皆さんも,学会や講演会などで医師のプレゼンテーションを聞く機会があると思います。複雑で大量のスライドを次々とめくりながらものすごい勢いで話す講師,体全体をスクリーンに向けて自分の世界に夢中になっている講師など,さまざまなケースが思い出されます。一方で,世界的なプレゼンテーションをTED TalksやYouTubeなどで見ると,面白くてかつ勉強にもなるので,つい何時間も見てしまうことがあると思います。これは一体,何が違うのでしょうか。
それは,セオリーとテクニックにありました。まずは,徹底した聴き手の分析であり,聴き手は誰で,何を聴きたがっているか,どんな話にメリットを感じるか,を分析することである,と本書は述べています。そして,目的を明確化して,伝える場所や環境を考慮に入れる,としています。コンテンツでは,シナリオを作ること。効果的なのは,問題解決型のシナリオで参加者の頭を使ってもらうこと,です。そして,デリバリー。非言語的コミュニケーションも大切なのです。
本書の編著者は八幡紕芦史さん。国際プレゼンテーション協会理事長で,日本におけるプレゼンテーション分野の第一人者です。そして,診療と研究と教育で活躍されている3人の医師が執筆者チームに加わっています。この斬新なチーム構成によって,過去に類書のないブルーオーシャン的イノベーションを本書は提供してくれています。特に,コミカルな4コマ漫画を使っているので,失敗ケースがギャグとして提示されており,ストレスなく楽しく理解できます。徹底した読者分析ですね。本書は普段の医療面接にも役立ちますので,医師や研修医だけでなく,全ての医療従事者に広く読んでいただきたいと思います。
A5・頁192 定価:本体2,600円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03191-2


Robert J. Hilt,Abraham M. Nussbaum 原著
髙橋 三郎 監訳
染矢 俊幸,江川 純 訳
《評者》丸山 博(松戸クリニック院長・小児科/児童精神科)
ポケットサイズに詰まった子どもの精神医
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
