医学生・研修医のための
医学書選びのマイルール
寄稿 安達洋祐,岩田充永,齊藤裕之,上田剛士,市原真,谷口俊文
2018.08.20 週刊医学界新聞(レジデント号):第3285号より
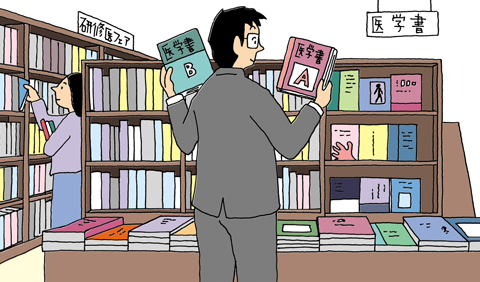
各所で紹介される論文検索の手法は体系化されているのに比べて,医学書の選び方にはこれといった法則がありません。医学生・研修医は先輩や同僚のオススメに従ったり,インターネットで評価を調べて衝動買いしたりと試行錯誤しながら,時に後悔しつつ,良書を探しているのではないでしょうか。
本企画では,研修医と日々接する指導医に,“医学書選びのマイルール”を披露していただきました。先輩方を参考に自分なりのルールを構築し,「良き指導者」となる医学書と出会ってください!

序文や前書きに目を通す
安達 洋祐
久留米大学教授/医学教育研究センター長
論文を選ぶときの基準は,「有名な雑誌の新しい論文」です。同じように,医学書を選ぶときの基準は,「有名な出版社の新しい本」です。書店で棚を眺めるとわかりますが,有名な出版社は幅広い領域で数多くの本を出版しています。新しい本かどうかは奥付の発行年月日を見ます。版数や刷数も大切です。短い間隔で版を重ねているのは新しい情報を取り入れて改訂を繰り返している証拠,刷数が多いのは買った人が多く増刷を重ねている証拠です。
論文同様,医学書を探すときもインターネット検索は便利ですが,関係ない本がたくさん挙がってくるので,取捨選択が大変です。お薦め度や読者レビューも参考になりますが,匿名の個人の感想ですので,信頼できる情報とは言えません。飲食店を選ぶときに「飲み比べ」「食べ比べ」が大切なように,医学書を選ぶときも「読み比べ」が大切です。インターネットで「チラ見」してもいいのですが,実物を手に取ってみないと分量や全体像はつかめず,ページをめくってみないと内容や感触はわかりません。
私が医学書を探すときは,大学の書籍売り場か専門書のある大型書店に行きます。類書が棚に集められているので,読み比べが簡単です。期待に沿った内容か,文が読みやすいか,図表は多いか,写真はきれいか,イラストは好みか,索引は多いかなど,品定めします。必ず目を通すのは序文や前書きです。そこには著者や編者の思いが述べられており,誰に何を伝えたい本なのかわかります。執筆者の所属や経歴にも目を向け,写真があれば人柄を想像しながら評価します。
迷ったときは,伝統ある定番の医学書を選ぶべきです。内科に『Harrison』(Harrison’s Principles of Internal Medicine)があるように,外科には『Schwartz』(Schwartz’s Principles of Surgery)や『Sabiston』(Sabiston Textbook of Surgery)があります。『Schwartz』は初版が1969年で,現在の10版は2069ページ,『Sabiston』は初版が1936年で,現在の20版は2176ページです。
知識は自信になります。知識は年齢や経験と無関係です。医学生はぜひ内科学と病理学の教科書を読んで医学や病気を学びましょう。研修医や専攻医は『Harrison』や『Sabiston』を読んで世界標準を知りましょう。
以上,私の選び方・探し方を書きましたが,大切なのは「相性」です。書店に行って棚を眺めてみましょう。本を手に取ってページをめくってみましょう。「これ,いいな」と感じる本が必ずあります。人も出会い,本も出会いです。
*
私が研修医のとき,指導医だった兼松隆之先生(長崎大名誉教授・長崎市立病院機構理事長)は,「最初の給料で外国の教科書を買いなさい。そして,改訂のたびに買い直しなさい」と言いました。私が初めて『Sabiston』を買ったのは外科医になって数年後でした。改訂のたびに後輩と「教科書勉強会」を行ったのが,今でも私の大きな財産です。

合格するための勉強から,患者のための勉強へ
岩田 充永
藤田保健衛生大学
救急総合内科学講座教授
大学受験では「志望校に合格するための参考書の選び方」という類いの本がよく売れていた気がする。医学生時代は,進級試験や国家試験に効率よく合格できることを目的とした医学書が大人気であった。医師となるまで,勉強の目的は「効率的に試験に合格すること」であった気がする(少なくとも勤勉でない私は……)。しかし,医師となったときから勉強の目的が「試験に合格すること」から「目の前の患者に最善を尽くすこと」に大きく変わる。私たち臨床医は,試験で点数を測定される機会は,専門医取得など限られた機会を除いて,学生時代に比べると格段に減少する。点数で評価されなくなったときにも,目の前の患者のために文字を読んで勉強することをどうか厭わないでほしい。
「目の前の患者に最善を尽くすために勉強する」というのは,もっと単純化すれば「日々の臨床での疑問を解決するために医学書を読む」と言い換えることができる。
僕は,下記のような基準で医学書を選んできた。
❶少しでも質の高い「その場しのぎ」をするためのマニュアル
研修は,目の前の患者に生じた問題についてとりあえずどのように対処するのが適切なのかを考える,いわば「その場しのぎ」の連続とも言える。その場しのぎの蓄積が貴重な経験へと昇華するのだから,決して軽んじてはいけない。長年多くの先輩たちが読んできたエビデンスに基づいて書かれているマニュアルは,「その場しのぎ」の質を高めてくれる。
❷「自分の判断は正しかったのか?」を座って勉強するための成書,総説
「その場しのぎ」だけで研修を過ごしていると,脳幹反射・瞬間芸だけの医師になってしまう。これを回避するためには,一日のうち短時間でも座って成書や総説を読む時間を作るべきである。この時間を作ることで,自分のその場しのぎの知識に学問的な深みが加わる。ただし,医学情報の更新は恐ろしく速くなっているので,成書の改訂が追い付かない時代になっている。電子媒体や信頼できる医学雑誌の総説論文も賢く活用することが求められる。
❸医師としてのセンス,判断力を磨く
医学書を読むだけでは良い医療者になることはできない。実際の臨床では,「この症例では,このマニュアルのここを開けば答えが載っていそうだ……」というような,問題解決のセンス(嗅覚のようなもの)を養うことが求められる。これには,センスの良い先輩に張り付いて真似をすることが王道だが,同じようなことを文章で試みる医学書も増えてきている(日常診療で遭遇することが多い場面を想定して,考え方を述べている書籍)。優秀な医療者のセンス,判断力を知ることができるのは,新米料理人が一流料理人のレシピをいきなり目にできるのと同じで,本当にありがたいことである。
*
その場しのぎ,知識を深める,センスを磨くという3つの視点で医学書を選んでほしい。

多読者となれ
齊藤 裕之
山口大学医学部附属病院
総合診療部准教授
ベッドサイドでの臨床教育や症例カンファレンスを通じて,学生や若手医師と一緒にClinical Question(以下,CQ)を解決する機会が多い。指導医として,「この本の,ここに書いてあるよ」とフットワーク軽く医学書を使いこなす能力は大切だと感じている。筆者は,常日頃から若手医師に「多読者となれ」と伝えている。今回は筆者の医学書の選び方をお伝えしてみたい。
まず前提条件として,表紙や読者レビューをウェブ上で確認するのみで医学書を購入すると定期的に外れを引いてしまうため,なるべくは避けたい。表紙の雰囲気で購入することは,恋愛と似ているところがある。「見た目が良いから,性格は度外視してあの人と付き合ってみたい」と言っているようなもので,少し危険な気がする。医学書は使ってなんぼ,診療に還元されてなんぼなので,自分で内容を確認し,使えそうだという...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
