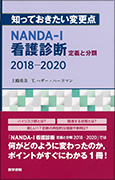MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2018.07.23
Medical Library 書評・新刊案内
中井 俊樹 シリーズ編集
中井 俊樹,小林 忠資 編
《評 者》網野 寛子(帝京平成大教授/看護学科長)
教育学と看護教育のコラボ
 文部科学省は,看護教育をレベルアップするための切り札「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」において,看護系人材として求められる基本的な資質・能力は9つと明言した。今後,各大学はカリキュラムの改正準備を行う中で,これらの資質・能力をどの科目でどのように教えて獲得させるか考えなければならない。変革を迫られたこの時期に,タイミングよく本書が上梓された。
文部科学省は,看護教育をレベルアップするための切り札「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」において,看護系人材として求められる基本的な資質・能力は9つと明言した。今後,各大学はカリキュラムの改正準備を行う中で,これらの資質・能力をどの科目でどのように教えて獲得させるか考えなければならない。変革を迫られたこの時期に,タイミングよく本書が上梓された。
本書は,教育学の視点から看護教育について幅広く解説する「看護教育実践シリーズ」(全5冊)の中の一冊である。授業方法に焦点を当てたのが本書であり,シリーズの第一弾として発刊された。
内容は3部から構成されている。第1部は授業方法の意義と指針の総論。看護教員は,看護学の専門知識と教育学の知識の両方を身につけることが肝心であると論ずる。学生は高卒の伝統的学生のみならず職業経験のある者がおり,学習意欲や学習習慣に差があるなど多様性に富んでいる。教員は自身の偏見に敏感になり,全ての学生の学習を素直に尊重する姿勢を持つ必要を述べている。また,授業は授業の型(導入・展開・まとめ)の各パートの持つ役割を認識し,学生の興味や関心を喚起するような展開をして,学習を評価することが大事と説く。
第2部は授業の技法について紙面が多く割かれている。授業の技法には,説明,発問,スライド,板書,教材などがある。技法を適切にチョイスすることが授業の成功の要素であるとして,それぞれについて詳しい解説がある。発問を例にとると,例えば看護教育の目標「人間の生命と権利を尊重する態度」を学ばせようとするとき,これは教員が一方的に押し付けて身につくものではない。発問を工夫することで学生は深く考えたり,自分なりの答えを見つけたりできる。発問は学習意欲を喚起したり,思考を焦点化したり拡散したり,揺さぶったりと学習を促進する機能を持っているのだ。
第3部はさまざまな場面での授業の工夫を述べている。1回の授業の構成は,前述の授業の型と同じであるが,15回のコマも同様である。初回の授業では,学生のレディネスやアクティブラーニングが可能かどうかの学生の汎用的能力を確認してからスタートするのが肝心で,最終回は習得できた知識や技術,習得できていない内容についても列挙させ,振り返りを通して学生自身に今後の学習の指針を立てさせる。また学生に高等教育機関に属する者としての知的誠実性を求めることも忘れてはならないと,きめ細かい対応を説く。
付録に授業に役立つ資料と用語集があり,著者らの優しい配慮を感じる。一読して感動するのは,教育学の専門家が体系的に授業の基本を押さえた上で,看護教育のオーソリティーたちとコラボして具体を展開しているため,身近で説得性があることだ。近年の理論を踏まえた「看護授業論」であり,活用すればその価値にも気付くはずである。
A5・頁200 定価:本体2,400円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03202-5


あなたの患者さん,認知症かもしれません
急性期・一般病院におけるアセスメントからBPSD・せん妄の予防,意思決定・退院支援まで
小川 朝生 著
《評 者》桑田 美代子(青梅慶友病院/よみうりランド慶友病院看護介護開発室長)
組織全体で認知症ケアに取り組む時代が到来した
 「桑田さんから紹介された小川朝生先生の本,面白くてもう2回も読んだわ。認知症のことわかっていると思っていたけど,改めて勉強になった! すごく読みやすいのよ」と,当法人の看護部長が意気揚々と語ってくれた。面白かったという点は以下の通りである。認知症に関する知識の整理につながった。随所に「ポイント」として,重要な点が簡潔にまとめてあるのも理解の助けになった。そして,皆が疑問に思うことに答えるような書き方になっている。急性期・一般病院で日常起こっている現象だから,「ある・ある」と自然に頭に入る。小川先生の講義を聞いている印象さえすると語っていた。
「桑田さんから紹介された小川朝生先生の本,面白くてもう2回も読んだわ。認知症のことわかっていると思っていたけど,改めて勉強になった! すごく読みやすいのよ」と,当法人の看護部長が意気揚々と語ってくれた。面白かったという点は以下の通りである。認知症に関する知識の整理につながった。随所に「ポイント」として,重要な点が簡潔にまとめてあるのも理解の助けになった。そして,皆が疑問に思うことに答えるような書き方になっている。急性期・一般病院で日常起こっている現象だから,「ある・ある」と自然に頭に入る。小川先生の講義を聞いている印象さえすると語っていた。
認知症患者は,“大変な患者”の一言で語られてしまう現状もある。スタッフは忙しいので対応しきれない。そして,ケアする側が大変と受け取れば,それは“不穏”,“問題”と表現され,その理由に目が向けられない。ケアする側が不安や混乱を増強させていることに気付いていない。だから,根本の原因解決となる対応にはつながらない。本書は,その根本原因の解決につながる知識,現象の見方が書かれている。認知症をもつ人の生活のしづらさ,苦痛や不安に焦点を当て,認知症の知識に基づき,その原因がひもとかれている。だから,「なるほど,そうなんだ!」と合点がいくのである。見方が変わると,現象の受け止め方も変わり,ケアする側の気持ちにも余裕が出てくる。
本書の構成を紹介すると,序章「今急性期病院で起きていること」,1章「一般病院における認知症の問題」,2章「急性期病院における認知症の問題の現れ方」,3章「認知症を知る」,4章「認知症の人が入院時に体験する苦痛・困難とは」,5章「急性期・一般病院で求められる認知症ケアとは」,6章「認知症・認知機能障害をアセスメントする」,7章「認知機能障害に配慮したコミュニケーション」,8章「認知症の人の痛みを評価する」,9章「食事の問題」,10章「行動心理症状(BPSD)の予防と対応」,11章「認知症の人の治療方針を考える(意思決定支援)」,12章「せん妄を予防しよう」,13章「認知症の退院支援:ケアの場の移行を支える」,14章「患者・家族への心のサポート,社会的支援を提供する」,となっている。もちろん,序章から読むのも良いが,私はまず3章と4章を一読し,日頃の実践を想起しながら,最初から読み進めるとより理解が深まるように思う。また,最近「意思決定支援」に注目が集まっている。しかし,認知症患者の意思決定支援は,認知症の知識がなくて行えるわけがない。ケアする側が認知症のことを知って初めて支援できる。本書は,そのための基本的知識が系統的に書かれている。
本書は,急性期・一般病院という「場」に関係なく,誰が手に取っても読む価値がある。その中で,私が最も読んでいただきたいのは,急性期病院の看護管理者の皆さんである。その理由は,看護管理者の方たちの認知症に対するケアの考え方が,スタッフに大きな影響を与えるからである。認知症患者の対応に,倫理的ジレンマを感じているスタッフも少なくない。組織全体で認知症ケアに取り組む時代が到来している。本書は必ず役立つ一冊である。
A5・頁192 定価:本体3,500円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02852-3


知っておきたい変更点
NANDA-Ⅰ看護診断 定義と分類 2018-2020
上鶴 重美,T. ヘザー・ハードマン 著
《評 者》冨澤 登志子(弘前大大学院准教授・看護学)
NANDA-I看護診断の変更点や新たな診断のポイントがよくわかる
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。