MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2018.02.12
Medical Library 書評・新刊案内
衣袋 健司 著
《評 者》佐藤 達夫(前・東京有明医療大学長/東医歯大名誉教授 )
学問の王道を歩んだ成果
 画像機器とカラー写真印刷技術の驚くべき発達により,有用な画像診断アトラスが多数出版され,応接に暇がないほどである。このような状況はもちろん医学の進歩にとって歓迎すべきことではあるが,少し不満を抱かざるを得ないのも事実である。
画像機器とカラー写真印刷技術の驚くべき発達により,有用な画像診断アトラスが多数出版され,応接に暇がないほどである。このような状況はもちろん医学の進歩にとって歓迎すべきことではあるが,少し不満を抱かざるを得ないのも事実である。
19世紀の初め,フランスの内科医ラエンネック(1781~1826年)は聴診器を発明・開発し,当時の医学に大きな進歩をもたらした。彼は,患者の生前の詳しい聴診所見と死後の剖検所見の照合を重ね,その成果を900ページに及ぶ大冊『間接聴診法,または,この新しい探究法に主として基づいた肺と心臓の疾患の診断に関する研究』(1819年)にまとめた。このような間接所見と直接所見を統合した書物が後ろに控えておれば,安心この上もない。
本書の著者・衣袋健司氏が,血管画像で遭遇した珍しい所見について,まだ解剖学教室に勤めていた私のもとに相談に来られたのは,もう30年ほども前のことである。そのとき私は「本当に知りたいことは本には書いていないものだ。自分の手を下ろして解剖することから始めてみなさい」と,半ば突き離し,解剖実習遺体を提供することにより,半ば協力することにした。それ以来,金曜の夜になると,一週間の激務を終えた衣袋氏の姿を実習室の片隅に見ることになった。
本書の序文にあるように,「標準的な血管分岐は半分程度で,残りは亜型」である。血管画像には異常と思われる所見が無数に見いだされるであろう。しかし一見,異常所見なるものも亜型の中に取り込む視野を持つことが望まれる。また血管の問題だけに矮小化できないこともあろう。血管は標的器官があっての存在であるし,周囲の構造物や神経との位置関係に影響を受けることも少なくあるまい。解剖体にすがり付いて,どのような小さな変異でも見逃さずに位置関係も含めて剖出し,その詳細所見の吟味と過去の膨大な文献の渉猟を重ねながら実態の解明に取り組まなければなるまい。
本書にみる,日常の読影所見に問題点を見いだし,実際の剖出を通じて理解を深めていこうという研究態度は,ことのほか貴い。それは,われわれ解剖学サイドからアプローチした局所解剖学に欠落しがちなところでもある。また,世に臨床と解剖学との協力を説く声は多い。実際にここ10年余りの間の臨床解剖学の進歩は著しいものが認められる。しかし,進化はしたが深化は不十分であったのではないか。この労作『腹部血管画像解剖アトラス』をひもとくと,そう感ぜざるを得ない。
著者・衣袋氏の金曜日夜の解剖は現在も続いている。一言でそういうが,これは大変なことであり,類いまれな努力と研さんを称えたい。そして,数多くの画像アトラスの中で最も長い生命を約束されたこの本格書に触発されて,腹部以外の部位でも,画像と解剖を高度に結び付けた研究書を世に問おうとする若い学徒が少しでも増えることを期待している。
B5・頁160 定価:本体10,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03057-1


植村 研一 著
《評 者》松井 秀樹(岡山大大学院教授・神経生理学)
多くの謎が秘められた脳の機能をわかりやすく解説
 優れた大脳生理学者であり,かつ脳神経外科医でもある著者によって,簡潔にかつわかりやすくまとめられた高次脳機能の解説書である。大脳生理学や脳科学を学ぼうとする医学・医療系の学生だけでなく,既に臨床現場で働いている医師や医療従事者が手にしても役に立つ,非常に優れた内容である。そればかりか,脳に関心のある一般の人々や患者さん,そのご家族など専門的な知識がない人達が読んでもわかりやすく,かつ読み物としても面白く解説されている。
優れた大脳生理学者であり,かつ脳神経外科医でもある著者によって,簡潔にかつわかりやすくまとめられた高次脳機能の解説書である。大脳生理学や脳科学を学ぼうとする医学・医療系の学生だけでなく,既に臨床現場で働いている医師や医療従事者が手にしても役に立つ,非常に優れた内容である。そればかりか,脳に関心のある一般の人々や患者さん,そのご家族など専門的な知識がない人達が読んでもわかりやすく,かつ読み物としても面白く解説されている。
本書の最もユニークな点は,大脳半球の機能の解説において,前頭葉,頭頂葉,側頭葉,後頭葉といった従来の分類ではなく,「知」「情」「意」をつかさどる脳の区分という考え方を取っている点である。その結果,外界から情報を取り入れ処理する感覚統合脳(知),その情報を演算して外部出力する表出脳(意),辺縁系(情)に働きをまとめることができているので,非常に理解しやすい。さらにはそれらの異常によって起こる疾患やその症状の解説が納得できる内容となっている。また,表出脳の働きにおいては,最新の知見を盛り込み,運動前野ならびに補足運動野の働きが整然とわかりやすく解説されている点が強く印象に残った。
後半では記憶の機構とうまい学習の方法や,リハビリテーションの意義,教育への提言など広く一般に興味を引く内容が盛り込まれている。難しい内容をここまで簡潔に,かつわかりやすく解説できる著者の力量は素晴らしい。近年特に研究が進んだとはいえ,まだまだ多くの謎が秘められた脳の機能に多くの読者の興味を引きつける役割を担うことができる優れた本である。
A5・頁136 定価:本体2,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03195-0


外科専門医受験のための演習問題と解説
第1集(増補版)・第2集
加納 宣康 監修
本多 通孝 編
《評 者》天野 篤(順大大学院教授・心臓血管外科学)
効率よく問題解決型形式で構成された問題集
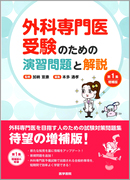 われわれが専門医を取得したころの知識習得方法は,主として臨床の現場で先輩医師の教えを素直に聞き入れて,疑問に感じることや患者さんの容態が思うように改善しない場合に教科書を開くという手続きだった。その上で,所属学会雑誌,海外の専門領域雑誌を読んで,日頃の診療,地方会での症例報告,総会での発表に励み,現場と学会の場で打たれ強くなっていることが実際の執刀医になるための必要条件で,この点に関しては,それほど施設間格差がなかったように感じている。さらに外科認定医(当時)取得に際しての試験は2人の試験官による口頭試問だけだったので,系統的な学習はしなくても抄録集の作成が完了すれば試験の合格は手中に収めたも同然だったように思う。
われわれが専門医を取得したころの知識習得方法は,主として臨床の現場で先輩医師の教えを素直に聞き入れて,疑問に感じることや患者さんの容態が思うように改善しない場合に教科書を開くという手続きだった。その上で,所属学会雑誌,海外の専門領域雑誌を読んで,日頃の診療,地方会での症例報告,総会での発表に励み,現場と学会の場で打たれ強くなっていることが実際の執刀医になるための必要条件で,この点に関しては,それほど施設間格差がなかったように感じている。さらに外科認定医(当時)取得に際しての試験は2人の試験官による口頭試問だけだったので,系統的な学習はしなくても抄録集の作成が完了すれば試験の合格は手中に収めたも同然だったように思う。
しかし,1990年ごろからの情報伝達形式の進化によって,外科医の習得すべき知識も増加してきた。さらに2000年以降,インターネットとPC環境の普及・進化に伴う情報処理の加速は最新知識の公平な取得...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
