MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2018.01.29
Medical Library 書評・新刊案内
≪ジェネラリストBOOKS≫
認知症はこう診る
初回面接・診断からBPSDの対応まで
上田 諭 編
《評 者》宮岡 等(北里大教授・精神科学)
認知症医療にかかわる多くの人に読んでほしい一冊
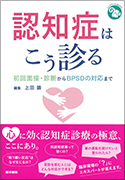 認知症患者数が急増する中,総合診療医,家庭医といった非専門医が,認知症専門医と良好な連携をとって,認知症患者を診ることが求められている。しかし自治体から認知症疾患医療センターを委託されている病院の精神科医である評者は,「物忘れを訴えたら,脳画像検査を実施され,認知機能の十分な評価なしに,抗認知症薬を処方された」「高齢者施設で少し興奮したら,話も聞かれることなく,BPSDと診断され,抗精神病薬を出された」「認知症の治療中に,ゆううつ感と不眠を訴えたら,すぐ抗うつ薬と睡眠薬を処方された。薬の種類は増え,かえってぼーっとしている」「あの医師は認知症を専門に診ていると言うが,生活面のアドバイスを何もしてくれないし,地域にどんな社会資源があるかも知らないようだ」などの不満を,患者,患者家族,認知症ケアに当たる医師以外のスタッフから聞くことが多い。問題は認知症の過剰診断,抗認知症薬の過剰処方,薬物療法以前の基本的な対応不足などに集約されるであろう。各自治体ではかかりつけ医を対象とした認知症対応力向上研修が開催され,認知症に関する書籍も数多くあるが,認知症の診断と治療における課題はなかなか改善されない。
認知症患者数が急増する中,総合診療医,家庭医といった非専門医が,認知症専門医と良好な連携をとって,認知症患者を診ることが求められている。しかし自治体から認知症疾患医療センターを委託されている病院の精神科医である評者は,「物忘れを訴えたら,脳画像検査を実施され,認知機能の十分な評価なしに,抗認知症薬を処方された」「高齢者施設で少し興奮したら,話も聞かれることなく,BPSDと診断され,抗精神病薬を出された」「認知症の治療中に,ゆううつ感と不眠を訴えたら,すぐ抗うつ薬と睡眠薬を処方された。薬の種類は増え,かえってぼーっとしている」「あの医師は認知症を専門に診ていると言うが,生活面のアドバイスを何もしてくれないし,地域にどんな社会資源があるかも知らないようだ」などの不満を,患者,患者家族,認知症ケアに当たる医師以外のスタッフから聞くことが多い。問題は認知症の過剰診断,抗認知症薬の過剰処方,薬物療法以前の基本的な対応不足などに集約されるであろう。各自治体ではかかりつけ医を対象とした認知症対応力向上研修が開催され,認知症に関する書籍も数多くあるが,認知症の診断と治療における課題はなかなか改善されない。
本書は「イントロダクション――認知症診療 こう進めたい」と,「診療のためにまず知るべきこと」「認知症診療,こんなときどうする?」「知っておきたい,MCIとさまざまな認知症」の3章からなり,さらにPros and Consとして議論が分かれている2つの問題(「本人への病名告知はどうする?」と「抗認知症薬は効く? 効かない?」)を取り上げている。
評者が本書を認知症医療にかかわる多くのスタッフに読んでほしいと思うのは,特に以下の2点からである。
第一に,よくBPSDと呼ばれる症状を含む行動の変化や生活の困難さへの非薬物的対応に多くのページが割かれている。しばしば参照される厚労省研究班による図(本書,p.136)は,確かに「非薬物的介入を最優先する」としているが,薬物に関する記載が多いため,かえって現場の適切な対応の妨げになっているのではないかと気にしていた。非薬物的介入について,本書が教えるさまざまな事例と対応はまさにすぐ活用すべき知識である。ただ評者もかつて述べたことがあるが1),薬物療法を第一と考えず,これほど症例ごとの対応が求められるとき,BPSDという診断名とも症状名ともつかない用語は不要に思える。
第二に,Pros and Consで,それぞれの問題について賛否の立場から2人が執筆し,編者がその議論をまとめている。一定の指針を決めるよりも読者が自ら考えて対応すべきと強調しているように思え,臨床家の姿勢として重要である。ただ抗認知症薬を勧める立場から「著効例では意欲が向上しADLが改善」のような記載があるのは気になった。添付文書に記載されている効能・効果は「認知症症状の進行抑制」である。意欲低下やADL低下の改善が目的であれば,それは適応外使用と言えるかもしれない。
編者である上田諭氏の認知症観,医療観は「イントロダクション」に凝縮されており,教えられることが多い。認知症医療が混乱しているこの時期に本書を編集してくださったことに感謝したい。また本書は総合診療医や家庭医に有用であるのは言うまでもないが,実は精神科医こそ本書を読み,患者の心と暮らしをみようとする初心を取り戻さねばならない。
1)日経メディカル Online.連載:宮岡等の「精神科医のひとりごと」BPSDという用語は使わない方がいい!.2015年6月16日.
A5・頁264 定価:本体3,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03221-6


Markus Reuber,Steven Schachter 編
吉野 相英 監訳
《評 者》重藤 寛史(福岡山王病院てんかん・すいみんセンター長)
明日からのてんかん診療に役立つ最新のガイドブック
 てんかん診療を行っていて痛感するのが,いかに多くの“てんかんのようでてんかんでない疾患”がてんかんと診断され,治療されてしまっているか,ということである。てんかんと診断されることによって患者が被る社会的損失,そして抗てんかん薬治療によって生じる身体的損失を考えるとき,常に「てんかんではない」可能性を念頭に診断することは基本的かつ極めて重要な姿勢である。しかし,てんかん専門医にとっても「てんかん」と「非てんかん」の鑑別は困難なことが多い。本書はその鑑別に重点を置き,図や表を用いてわかりやすく解説した,最新かつ唯一のガイドブックであり,本邦の神経学の第一線で活躍する訳者らが,豊富な臨床経験に基づいて的確に訳した名著である。
てんかん診療を行っていて痛感するのが,いかに多くの“てんかんのようでてんかんでない疾患”がてんかんと診断され,治療されてしまっているか,ということである。てんかんと診断されることによって患者が被る社会的損失,そして抗てんかん薬治療によって生じる身体的損失を考えるとき,常に「てんかんではない」可能性を念頭に診断することは基本的かつ極めて重要な姿勢である。しかし,てんかん専門医にとっても「てんかん」と「非てんかん」の鑑別は困難なことが多い。本書はその鑑別に重点を置き,図や表を用いてわかりやすく解説した,最新かつ唯一のガイドブックであり,本邦の神経学の第一線で活躍する訳者らが,豊富な臨床経験に基づいて的確に訳した名著である。
本書は,神経学の父であり,てんかんを神経疾患として独立させようとしていたGowersが100年以上も前に記した“Border-land of Epilepsy”を原型とし,神経学の黎明期から存在する「てんかんとその境界領域」を,現代医療の知見をもって「再訪する」という形で構成されている。各章のはじめにある「要約」と「はじめに」には,各疾患に対するGowersの時代の理解と現代における理解との比較が記述してあり面白い。本文では,ビデオ脳波,筋電図,心電図,脳画像検査,超音波検査,遺伝子検査など新たなテクノロジーを得た現代の専門家によって,てんかんの境界領域である疾患の発症メカニズムと鑑別のロジックを詳細に解説していて,なるほど,とうなずいてしまう。失神,心因性発作,パニック発作,めまい,頭痛,一過性脳虚血,一過性健忘,睡眠関連の発作,アルコール関連の発作,不随意運動などのてんかんと鑑別を要する疾患に加え,自己免疫介在性てんかん,非けいれん性てんかん重積,自閉症,抑うつなど,現在のてんかん学でトピックになっている疾患にも多くのページを割いており最新の知見を得ることもできる。
単に教科書的で平板なガイドブックと異なり,Gowersが多大な症例観察に基づいた記述をしていたのと同様に,本書でも多くの具体的な症例を取り上げて,それらの症例を科学的に解説しているため,推理小説的な面白さも併せ持っている。また,てんかんの境界領域である疾患の治療を,最新の情報に基づいて総括的,具体的に提示している唯一のテキストであるので,明日からの臨床に,すぐに...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
