MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2017.01.09
Medical Library 書評・新刊案内
若林 俊彦 監修
夏目 敦至,泉 孝嗣 編
《評 者》髙橋 淳(国立循環器病研究センター病院脳神経外科部長)
執筆陣の熱意が詰まった,渾身の臨床マニュアル
 本書『脳神経外科レジデントマニュアル』を,レジデントのみならず全ての脳神経外科医に薦めたい。
本書『脳神経外科レジデントマニュアル』を,レジデントのみならず全ての脳神経外科医に薦めたい。
本書の特徴は,①脳神経外科実臨床に必要とされる膨大な知識を大胆に取捨選択し,ポケットサイズのB6変型判わずか384ページの中に集約したこと,②単なるデータブックではなく,内容に深く「血が通っている」ことである。
前半1~3章では基本診察手順や画像読影手順,疾患別のポイントが簡潔に述べられており,従来のマニュアル本の形を踏襲している。しかし本書では,書の後半になるほど内容の深みが猛烈に増してくる。
第4章「基本的術前術後の管理」では,鎮痛薬の選択,手術創の管理など,通常の教科書には記載されない実践的な知識が網羅されている。第5章「各種疾患を有する患者の管理」では,呼吸器疾患患者への低容量換気のプロトコールやFiO2とPEEPの至適調整表,急性腎障害の鑑別ポイント,そして疼痛を訴える患者に対する執筆陣の体系的アプローチなど有益な情報が詳細に網羅され,読者はナルホドと膝を打つこと請け合いである。第7章「薬剤の管理」はNOACsをはじめとする多くの新規薬剤の実践的使用法を示すとともに小児の投薬量にも明確に言及し,まさに痒いところに手が届く構成となっている。第8章「代表的手術アプローチ」は単なる基本術式の羅列かと思いきや,ヘッドピン刺入位置やクラニオトームの刃の傾け方,脳べらの正しい使用方法など,毎日手術室でシニアスタッフがレジデントに逐一教える内容が,全て具体的に書かれているのである。
最終第9章「緩和医療」はまさに本書の白眉である。脳神経外科における終末期緩和医療の特性,鎮痛剤使用の5原則などが解説されている。なんと,臨終の看取り方にまで言及されている(!)。さらに,「患者から『自殺したい』と言われたら」というコラム(Side Memo)を読むに至り,本書はもう,「レジデントマニュアル」というシリーズ名のレベルを超越していることを確信した。最終付録「データファイル」を見て,本書がマニュアル本であったことにはっと気付く。
本書は海外の優れたレジデントマニュアルと堂々と渡り合える,渾身の一冊である。医学書院の同名のシリーズの中でも,特に輝いている。名大脳神経外科若林俊彦教授の監修コンセプト,そして執筆に当たった同教室員の熱意と労力に心から敬意を表したい。熱い思いは,多くの読者に間違いなく届くであろう。
本書はシニアスタッフにとっても,十分に読み応えがある。実は私も,院内ではポケットに入れて頻繁に持ち歩いている。素晴らしい書の完成に,心から賛辞を送りたい。
B6変型・頁384 定価:本体4,800円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02533-1


Danielle Ofri 原著
堀内 志奈 訳
《評 者》平島 修(徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター長)
うごめく感情の渦の中で,あるべき医師像とは
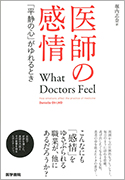 「医療現場をこれほどまでに赤裸々に,リアルに書いていいものだろうか」という驚きがこの本を読んで生じた感情だった。いてもたってもいられず,本書の書評を書かせてほしいと編集担当者にお願いしてしまった。「医師はいかなる時も平静の心を持って患者と向き合うべきである」と説いた臨床医学の基礎を作ったウィリアム・オスラー先生の「平静の心」を揺るがす内容なのである。
「医療現場をこれほどまでに赤裸々に,リアルに書いていいものだろうか」という驚きがこの本を読んで生じた感情だった。いてもたってもいられず,本書の書評を書かせてほしいと編集担当者にお願いしてしまった。「医師はいかなる時も平静の心を持って患者と向き合うべきである」と説いた臨床医学の基礎を作ったウィリアム・オスラー先生の「平静の心」を揺るがす内容なのである。
「医師は患者に必要以上に感情移入してはいけない」
医師なら一度は耳にした言葉であると思うが,医師は感情を意識的に心に押し込んでおくことが本当に正しいのだろうか。本書はこのタブーとさえされてきたような感情の問題を,医師にはどのような感情が生まれ,どのように反応してしまうのかを,掘り下げてゆく。命を扱う医師という職業は他の職業と違い,さまざまな感情の波が患者本人や家族だけでなく押し寄せる職業である。医療の主役は患者であり,疾患を患った患者がいかなる感情を抱くかに関してはこれまで何度も議論されてきたが,医師が受ける感情に関する議論はほとんどされてこなかった。
「不安・恐怖・悲しみ・恥・怒り・困惑・幻滅」といった感情は,医師が臨床現場で日常的に感じる感情である。このような感情についてエピソードを交えて述べられているが,筆者の壮絶な経験と心の中で揺れ動く葛藤は,臨床医なら身近に感じられる内容で描かれており,どんどん引き込まれてゆく。医師がアルコール依存症患者や肥満患者に軽蔑の念を抱くことや,寝たきり患者が発熱を主訴に救急外来に運ばれると“gomer”(go out of my ER)と差別的な用語で呼ばれる現状をありのままに指摘し,医学生が持つ純粋な気持ちがどのようになくなっていくのかについても冷静に分析している。また本書は医療ミスの原因となる感情も指摘している。医師の不安や恐れといった感情はあたかもひた隠しにされ,ミスのない完璧な医術を要求される。しかしミスが大きかれ,小さかれ,なくなることはない。
医療機器は発展してもそれを扱う医師が血の通う人間であるならば,システムだけを指摘するのではなく,背景となった感情にまで言及しなければ医療ミスを明らかにすることすらできない。本書で書かれているエピソードは,筆者が訴える「平静な心」ではいられないという言葉に非常に納得させられる内容である。
「医師の感情」はこれまであまり認識されてこなかった内容であるが,医師-患者関係を良好にする意味で非常に重要な基盤となる。これから医療現場に臨む医学生か...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
