MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2015.05.18
Medical Library 書評・新刊案内
崎山 弘,本田 雅敬 編
《評 者》五十嵐 隆(国立成育医療研究センター理事長)
子どもの重症疾患の診断過程が手に取るようにわかる
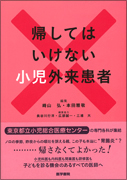 吉田兼好の「命長ければ恥多し」の言葉どおり,小児科医は誰しも臨床経験が長いほど臨床現場で「痛い」思いをした経験を持つ。私自身もプロとして恥ずかしいことではあるが,救急外来など同僚・先輩医師からの支援がなく,臨床検査も十分にできない状況にあり,しかも深夜で自分の体調が必ずしも万全ではない中で短い時間内に決断を下さなくてはならないときに,「痛い」思い,すなわち診断ミスをしたことがあった。かつての大学や病院の医局などの深い人間関係が結べた職場では,上司や同僚から心筋炎,イレウス,気道異物,白血病などの初期診療時の臨床上の注意点やこつを日々耳学問として聞く機会があり,それが救急外来などの臨床現場で大いに役立ったと感謝している。質の高い医療情報を獲得する手段が今よりも少なかった昔は,そのようにして貴重な臨床上の知恵が次世代に伝授されていたのだと思う。
吉田兼好の「命長ければ恥多し」の言葉どおり,小児科医は誰しも臨床経験が長いほど臨床現場で「痛い」思いをした経験を持つ。私自身もプロとして恥ずかしいことではあるが,救急外来など同僚・先輩医師からの支援がなく,臨床検査も十分にできない状況にあり,しかも深夜で自分の体調が必ずしも万全ではない中で短い時間内に決断を下さなくてはならないときに,「痛い」思い,すなわち診断ミスをしたことがあった。かつての大学や病院の医局などの深い人間関係が結べた職場では,上司や同僚から心筋炎,イレウス,気道異物,白血病などの初期診療時の臨床上の注意点やこつを日々耳学問として聞く機会があり,それが救急外来などの臨床現場で大いに役立ったと感謝している。質の高い医療情報を獲得する手段が今よりも少なかった昔は,そのようにして貴重な臨床上の知恵が次世代に伝授されていたのだと思う。
今回,崎山弘先生と本田雅敬先生が編集された『帰してはいけない小児外来患者』を拝読した。本書では,見逃してはならない小児の重症疾患の実例が,多岐にわたり丁寧に解説されている。
初期診断時に重症疾患をどうして正しく診断できなかったか,そして,どのようなちょっとした契機により重症疾患の診断に気付かされたかが手に取るようにわかる。読んでいる途中で,昔のように自分が医局のこたつで上司や同僚から臨床上の貴重な知恵や注意点を伝授されている気がしてきた。
日本小児科学会は「小児科専門医は子どもの総合医である」と宣言した。そして,小児科専門医としての到達目標を掲げ,最近数年間は主として若手小児科医を対象とした小児科専門医取得のためのインテンシブコースを毎年開催している。本書を拝読して,本書のような切り口で初期診断時に見逃される小児の重症疾患について教育する方法も有効ではないかと深く感じ入った。
本書には,東京都立小児総合医療センターの職員が経験された貴重な実例の数々が示されており,まさに同センターの総力を挙げての壮大な仕事である。さらに,編集と執筆とを兼ねた崎山先生は同センターの前身ともいえる都立府中病院小児科にかつて勤務され,退職後も開業の傍ら同小児科で当直と夜間の救急外来を定期的に担当され,長い期間地域医療に絶大な貢献を果たしてこられた。同院小児科では本書に記載されているような,すぐには診断できなかった重症疾患の症例検討会が,横路征太郎部長の下で施設外の関連する小児科医と一緒に定期的に開催されていた。おそらく本書の企画には,このときの症例検討会の精神が深く反映されていると私は勝手に推測している。
本書は日常の小児医療に従事する者にとって,臨床上の頂門の一針ともいうべき貴重な示唆を与えてくれる。臨床現場で小児医療に携わる者にとって本書は極めて有益であり,一人でも多くの関係者が手に取って愛読されることを祈る。
A5・頁224 定価:本体3,600円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02138-8


今井 博久,福島 紀子 編
《評 者》徳田 安春(地域医療機能推進機構(JCHO)本部顧問)
高齢者ポリファーマシーにおける脱処方時の参考書
 ポリファーマシーは患者に不利益をもたらす。コストが増大するだけでなく,副作用のリスクも高まるからだ。特に高齢者でリスクが高く,欧米ではそのエビデンスも蓄積してきている。急速に超高齢社会となったわが国でも問題となっており,われわれの一連の研究でもそのリスクが示されている。急性期病院への入院の原因となる急病のうち少なく見積もっても5%は薬の副作用によるものであった1)。STOPP基準(Screening Tool of Older Person’s potentially inappropriate Prescriptions criteria)によると,在宅医療の患者の約1/3の人々が不適切処方(Potentially Inappropriate Medication:PIM)を受けていたと報告されている2)。
ポリファーマシーは患者に不利益をもたらす。コストが増大するだけでなく,副作用のリスクも高まるからだ。特に高齢者でリスクが高く,欧米ではそのエビデンスも蓄積してきている。急速に超高齢社会となったわが国でも問題となっており,われわれの一連の研究でもそのリスクが示されている。急性期病院への入院の原因となる急病のうち少なく見積もっても5%は薬の副作用によるものであった1)。STOPP基準(Screening Tool of Older Person’s potentially inappropriate Prescriptions criteria)によると,在宅医療の患者の約1/3の人々が不適切処方(Potentially Inappropriate Medication:PIM)を受けていたと報告されている2)。
このような状況で,ポリファーマシー患者の入院を受け入れている全国の急性期病院では,脱処方(De-Prescribing)の業務を行う役割を担っている。患者の利益と不利益をてんびんにかけながら処方分析を行い,不適切処方を減らす。退院時には,かかりつけ医師に電話で直接連絡を取り,退院時薬剤処方確認(Discharge Medication Reconciliation)を伝える。このような脱処方の任務を行うことが,ホスピタリスト医師の日常業務のうちの大きな部分を占めるようになった。
典型的なケースを示す。介護施設でフレイルな状態に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
