MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2012.07.02
Medical Library 書評・新刊案内
樋口 輝彦,市川 宏伸,神庭 重信,朝田 隆,中込 和幸 編
《評 者》髙橋 清久(精神・神経科学振興財団理事長)
精神科医師が待望していた実践書の誕生
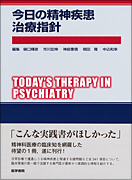 『今日の治療指針』という書名は多くの医師にとってなじみの深いものであろう。私も日常診療の中でそれをひもといた経験は数知れない。しかし,精神科医師の私がそのページを繰るのは,ほとんどが他科の疾患項目であって,精神科関係のものはごくまれであった。そのまれにしか見なかった精神科疾患に関する治療指針の解説は正直言って物足らないものであった。
『今日の治療指針』という書名は多くの医師にとってなじみの深いものであろう。私も日常診療の中でそれをひもといた経験は数知れない。しかし,精神科医師の私がそのページを繰るのは,ほとんどが他科の疾患項目であって,精神科関係のものはごくまれであった。そのまれにしか見なかった精神科疾患に関する治療指針の解説は正直言って物足らないものであった。
このたび新たに出版された本書を手にして,これこそ精神科の日常診療に役立つものだと実感した。初めて精神科医師にとって日常診療で実際に役立つ治療指針が世に出たわけだが,考えてみるとなぜこのような書物が今まで出版されなかったのか不思議に思えてくる。裏返していうと,まさに精神科医師が待望していた実践書と言えよう。
本書が出版されるに至った背景を考えてみると,今日ほど精神科医療が重要であることの認識が高まった時代はない,という事実があると思われる。うつ病,PTSD,不安障害,睡眠障害,不登校,虐待,自殺など数多くのこころの健康問題に社会的関心が高まっており,さらに東日本大震災で生じたこころの健康問題はそれを大きくクローズアップした。それもあって国は精神疾患を五大疾患の一つとしたのである。
本書は1000ページ余りの大著であり,取り上げられたテーマは23の項目にわたっており,300人以上もの第一線で活躍する人々によって最新の情報が書かれている。統合失調症や気分障害を始め,ICD-10,DSM-IV-TRなど国際診断基準で取り上げられている全ての疾患についてそのスタンダードとなる治療指針が述べられている。
精神疾患に関する治療は単に薬物療法だけでは効果がなく,精神療法や環境調整,さらに社会的な支援までも視野に入れなければならない。そのような包括的医療が的確かつ網羅的に記述されているのが本書の特色の一つである。また,ある特定の疾患について薬物療法,精神療法,家族との関係を含めての環境調整などの記述があると同時に,それらの治療法を中心とした記述がまた別の項で適切に記述されている。いわば,治療指針を立体的に俯瞰しているといってよいだろう。一例を挙げれば,精神療法については実に17種類もの治療法についてわかりやすい解説が加えられている。
もう一つの本書の特徴は,身体疾患にはみられない精神疾患特有の重要事項あるいは社会的観点をも取り入れている点である。例えば精神疾患の身体合併症について実際の臨床で有用と思われる解説が行われている。また,社会的支援の資源についても有用な情報が盛られており,さらにはアンチスティグマ,ジェンダー,外国人のメンタルヘルス,医療関係者の精神保健といった項目まである。
このように多岐にわたる精神疾患の治療指針を,実際の臨床現場での必要な知識と共にその背景にある多彩な課題を,かくも網羅的に,しかも要点を簡潔に解説するという本書を生み出された編者および執筆者の努力に敬意を表したい。と同時に,新しい薬剤の登場が盛んであり,疾病概念も時代と共に移り変わり,環境調整や社会的支援の在り方の変化も急である精神医療の現状を思うと,本書の内容は遠からず追補・修正する時が到来すると予想されるが,本書に見られる豊かな最新情報を網羅的に提供し,実践上高い有用性を持つ,という編集方針を今後とも堅持していただきたいと願う次第である。
A5・頁1,012 定価14,700円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01380-2


矢谷 令子 シリーズ監修
小林 夏子,福田 恵美子 編
《評 者》近藤 知子(帝京科学大教授・作業療法学)
作業療法の幅広い問いに応える一冊
 「作業」は作業療法にとって,専門性,独自性の核となるものであり,作業について学ぶことは,作業療法そのものについて学ぶことでもある。この意味で,本書『基礎作業学』は,「標準作業療法学」シリーズの中でも,作業療法の基礎学問的役割を担っている。
「作業」は作業療法にとって,専門性,独自性の核となるものであり,作業について学ぶことは,作業療法そのものについて学ぶことでもある。この意味で,本書『基礎作業学』は,「標準作業療法学」シリーズの中でも,作業療法の基礎学問的役割を担っている。
本書は,「はじめに」で触れられているように,「作業とは何か」「作業がなぜ治療になり得るのか」「作業を治療にどう活用するのか」という,幅広い問いに応えようとしている。これは,作業療法の哲学的背景と共に,作業療法実践の全過程を概略するという難解な課題に挑むものである。
内容をみると,第1章では,作業療法における「基礎作業学」の範疇,「作業療法と作業」「作業の適用方法」が,先人の視点を用いつつ多彩な方面から説明される。次いで第2章では,人を身体運動機能,認知技能,心理社会的技能,感覚統合,作業遂行の面から捉え,それらに関連する作業分析法が,それぞれの拠り所とする理論と共に紹介される。最後の第3章では,心身機能や身体構造の障害により活動制限・参加制約をもたらされた対象者を例とし,作業療法場面で多用されてきた革細工,モザイク,ゲームなどを用いて,それらの作業分析や作業適用方法が解説されている。
本書は,作業療法が培ってきた作業の分析法や,治療への適用方法を,既存の分野を念頭に置きつつ,確実に修めるために,有用な知識を提供する。作業療法を学ぶ学生は, 作業療法で用い得る多様な分析方法を知り,人が行う作業を,技能や機能の視点から分析・理解し,治療的に段階付ける方法を身につけることに活用できるであろう。特に,第2版では,作業療法に関心を持つ学生が,その関心をより深め,主体的に学習することを第1版よりさらに意識して著されたという。各章のはじめに記された学習目標,学習後の修得チェックリスト,そして,章の終わりに載るキーワードは,知識の確認のために大いに役に立つ。また,学生だけでなく,すでに作業療法士となった人にとっても,機能・分野別に,関連する作業分析や作業の段階付けの方法を確認する際に有用であろう。
今日,作業療法は,障害を持つ人だけでなく,災害・貧困・差別なども含め,健康な作業への従事が妨げられた人,その可能性がある人のすべてを対象としつつあり,このような新しい作業療法領域に関心を持つ人にとっては,本書で著される知識と技術が,その領域にどのような広がりをもって適用できるかを考えながら読み進めると興味深いに違いない。
B5・頁216 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01492-2


矢冨 裕,横田 浩充 シリーズ監修
谷口 信行 編
《評 者》種村 正(心臓血管研究所臨床検査室長・技師長)
卒業前に身につけておきたい知識をコンパクトにまとめた渾身の一冊
 とかく教科書は難しい。筆者の立場では,難しいことを難しく書くのは簡単であるが,わかりやすい言葉を使って簡潔に書くことは非常に難しい。一方,学生諸氏が求めているのは基礎から応用まで幅広く網羅していて実習にも役立ち,図説や写真が...
とかく教科書は難しい。筆者の立場では,難しいことを難しく書くのは簡単であるが,わかりやすい言葉を使って簡潔に書くことは非常に難しい。一方,学生諸氏が求めているのは基礎から応用まで幅広く網羅していて実習にも役立ち,図説や写真が...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
