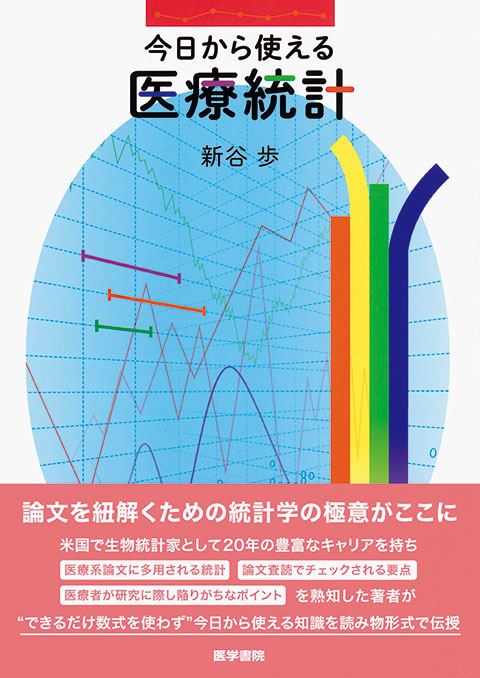同等性・非劣性の解析(新谷歩)
連載
2012.03.26
医療統計学講座
【Lesson11】
同等性・非劣性の解析
新谷歩(米国ヴァンダービルト大学准教授・医療統計学)
(2967号よりつづく)
臨床研究を行う際,あるいは論文等を読む際,統計学の知識を持つことは必須です。
本連載では,統計学が敬遠される一因となっている数式をなるべく使わない形で,論文などに多用される統計,医学研究者が陥りがちなポイントとそれに対する考え方について紹介し,臨床研究分野のリテラシーの向上をめざします。
通常の解析では,P値が0.05より小さければ「差がある」,0.05以上であれば「差がない」としますが,「差がない」という事実のみに着目して,「比較群が同等である」と判断してはいないでしょうか? これは統計的にみて,絶対にしてはいけません。P値では,差があることは証明できても同等であることを証明することはできないのです。
では,どうすれば統計的な同等性を示すことができるのでしょうか? 今回は,同等性(または非劣性)を示す解析について説明します。
■"同等性"を示すにはどのような手続きが必要か
| 【例1】新薬と既存薬に10人ずつ割り付けた研究において,アウトカムの死亡率が新薬群で30%,既存薬群で20%でした。仮説検定を行い,この差に統計的な有意差があるかどうか調べたところ,P値は0.6でした。仮説検定は,"新薬と既存薬の死亡率の差が等しい"という帰無仮説を棄却するかどうかとなりますが,P値が0.05以上なので帰無仮説を棄却することはできませんでした。次のうち,この解析結果を正しく表しているのはどれでしょうか?
A.新薬群の死亡率は既存薬群と同じである。
|
例1の答えはBです。通常の解析では,P値が0.05未満であれば有意差がある,つまり新薬は既存薬に比べて優れているという差(優越性)を示す解析が行われます。この優越性を示す解析の帰無仮説は"新薬群と既存薬群の死亡率の差が等しい(同等である)"ですが,棄却できなかったからといって,帰無仮説を採択できるわけではないのです。
この場合は,"帰無仮説を棄却するに十分なエビデンスがない"ということに過ぎず,"同等性がある"と言えるわけではありません。今回の例では,サンプル数が各群10と非常に少ないために解析がパワー不足となり,有意差が出なかったに過ぎません。95%信頼区間はこの場合[-30%,50%]となります。つまり同様の研究が繰り返された場合,新薬群の死亡率が既存薬群の死亡率より50%も高くなることもあれば,その逆で新薬群の死亡率が既存薬群の死亡率より30%低くなることもあると解釈できます。差が50%となれば同等性を言うことはできないのは明らかですね。では,下記のような場合はいかがでしょうか。
| 【例2】新薬と既存薬に1000人ずつ割り付け,死亡率が新薬群,既存薬群ともに20%であったとします。この場合,2群間の差がゼロなのでP値は1.0となり,この例でも帰無仮説は棄却されません。では,この例では同等性を示すことはできるでしょうか? |
この場合,95%信頼区間は[-3.5%,3.5%]と計算できます。同様の研究が繰り返された場合,新薬群の死亡率は良い場合で既存薬群よりも3.5%低くなり,悪い場合で既存薬群より3.5%高くなる,と解釈できます。この場合も,P値を用...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。