新春随想2012(門田守人,寺岡慧,辻哲夫,色平哲郎,楠木重範,坂本すが,藤田郁代,中板育美,山浦玄嗣)
2012.01.02
新春随想
2012
がん対策推進基本計画――新たな5か年に向けて
門田 守人(がん研有明病院副院長/がん対策推進協議会会長) がんは1981年以来わが国の死因の第1位を占め,国民の半数ががんにかかり,3分の1が死亡している。これを背景に,2006年に「がん対策基本法」が成立し,2007年4月の施行となった。この法律の基本理念は,(1)がんの克服をめざし,がんに関する専門的,学際的または総合的な研究を推進するとともに,がんの予防,診断,治療などに係る技術の向上,その他の研究などの成果を普及,活用,および発展させること,(2)がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること,(3)がん患者の置かれている状況に応じ,本人の意向を十分尊重してがんの治療方法などが選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること,とされている。この法律に基づき,2007-2011年度の5年間の「がん対策推進基本計画」が策定・実行されてきたが,第1期は2012年3月をもって終了する。
がんは1981年以来わが国の死因の第1位を占め,国民の半数ががんにかかり,3分の1が死亡している。これを背景に,2006年に「がん対策基本法」が成立し,2007年4月の施行となった。この法律の基本理念は,(1)がんの克服をめざし,がんに関する専門的,学際的または総合的な研究を推進するとともに,がんの予防,診断,治療などに係る技術の向上,その他の研究などの成果を普及,活用,および発展させること,(2)がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること,(3)がん患者の置かれている状況に応じ,本人の意向を十分尊重してがんの治療方法などが選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること,とされている。この法律に基づき,2007-2011年度の5年間の「がん対策推進基本計画」が策定・実行されてきたが,第1期は2012年3月をもって終了する。
厚生労働省は,2010年6月に第1期基本計画の中間報告書を公表したが,それによると全体目標の一つの「10年でがんの年齢調整死亡率(75歳未満)を20%減少する」としたことについては,おおむね目標どおりに進んでいる。
一方,もう一つの全体目標である「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」において,量的な目標についての計画は進んでいるものの,苦痛や療養生活のいわゆる「質」の面については,いまだに指標の設定さえも明確にされていない。
がん患者があらゆる時期に経験する身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することは患者や家族の願いであり,医療者には科学的な視点に立った対応が求められる。協議会の意見としても,適切で測定可能な指標を早期に設定することの必要性が強調されている。
次期計画では,種々の領域において形式的な数値で表される「量」よりも,「質」を表すことのできる指標を定め,その実行をめざすことが重要だろう。
移植医療のこれから
寺岡 慧(国際医療福祉大学熱海病院院長/前・日本移植学会理事長) 改正臓器移植法が施行され1年有余が経過した。法改正は臓器不全のため移植を待ち望んでいた多くの患者にとって悲願とも言えるものであった。思い起こせば1997年に臓器移植法が制定されたが,極めて限定的なものであった。それは臓器不全との絶望的な闘病生活を強いられてきた患者にとって,いちるの希望をもたらすものではあったが,年間10件前後の臓器提供では,その恩恵に浴する患者は極めて少数にすぎないという厳しい現実には変わりなかった。
改正臓器移植法が施行され1年有余が経過した。法改正は臓器不全のため移植を待ち望んでいた多くの患者にとって悲願とも言えるものであった。思い起こせば1997年に臓器移植法が制定されたが,極めて限定的なものであった。それは臓器不全との絶望的な闘病生活を強いられてきた患者にとって,いちるの希望をもたらすものではあったが,年間10件前後の臓器提供では,その恩恵に浴する患者は極めて少数にすぎないという厳しい現実には変わりなかった。
この半世紀の医学の進歩により,臓器移植の成績は飛躍的に向上した。しかし,わが国においては,治療法は存在してもその治療を受けられないために多くの患者が生を奪われていった。医学・医療の大きな目標のひとつは,治せるはずの患者を確実に治すこと,治せない疾患をやがては治せるようにすることであるはずではないだろうか。
臓器移植法の改正で,本人の意思が不明でも家族の書面による承諾により,脳死後,臓器の提供が可能になった。移植を待ち望む患者にとっては大きな福音と言えよう。2010年7月の改正法施行以来69件(2011年12月1日時点)の尊い,善意による臓器の提供が行われ,多くの生命が救われ,健康を取り戻している。しかし,それでもなお多くの患者が移植を待ち望んでいることに変わりはない。臓器提供を増加させ,一人でも多くの患者を救うためには,社会の移植医療への理解・信頼の確保,提供施設の負担軽減など,課題が山積している。さらに生命の大切さ,尊厳について,特に次世代を担う若い世代への啓発が重要だろう。
現代ほど生命の尊厳が軽んじられている時代はないだろう。自殺,虐待,いじめ,テロ,戦争,飢餓,災害などのため,「救えるはずの多くの生命」が失われている。生命は有限であり,一度限りのものである。だからこそかけがえのないものであろう。またどの生命にも必ず終わりがあり,生の終わりに際しての選択肢のひとつとして臓器の提供があり得る。より普遍的な,生命の根源にかかわる問題として,終末期医療,延命治療,尊厳死などの問題とともに,臓器提供について考え,話し合い,自身の意思を表示する運動を進めたいと考えている。今生きている生命を大切にし,治せるはずの,救えるはずの多くの生命を救うために。
団塊の世代の老後を考える
辻 哲夫(東京大学高齢社会総合研究機構特任教授) 団塊の世代の代表(1947年生まれ)が2012年に65歳を迎える。この世代の多くはサラリーマンで,これを機に会社との縁が切れ,住まいのある地域を中心とする生活に移行するだろう。そして,2022年には彼らも後期高齢者となり,日本の後期高齢者は激増する。これが主に大都市圏のベッドタウンで起こるのである。
団塊の世代の代表(1947年生まれ)が2012年に65歳を迎える。この世代の多くはサラリーマンで,これを機に会社との縁が切れ,住まいのある地域を中心とする生活に移行するだろう。そして,2022年には彼らも後期高齢者となり,日本の後期高齢者は激増する。これが主に大都市圏のベッドタウンで起こるのである。
あえて悲観的なシナリオから述べる。「生活不活発病」という言葉があるように,やがて彼らは家に閉じこもりがちとなり,多くの人が要介護となる。と同時に,大都市圏の急性期病院は入院患者急増で機能停止する。一方,残念ながら日本は増税に失敗し,社会保障が拡充できず,多くの高齢者は地価の安い遠隔の地に追いやられ,孤独死が増える。そんな暗い社会になる恐れがある。もちろんこんなことがあってはならない。
東京大学高齢社会総合研究機構では,首都圏ベッドタウンの典型である千葉県柏市で,「柏プロジェクト」に取り組んでいる。高齢者は地域で生きがいを持って就労でき,人と人との触れ合いを楽しんで,できる限り元気でいてほしい。たとえ弱っても,在宅医療を含めた24時間在宅ケアシステムの下で,地域内に整備された高齢者向け住宅も活用して,住み慣れた地域で安心して住み続けてほしい。そんな地域をめざすものだ。全国に普及するには増税の国民的コンセンサスを取り付け,社会保障にさらに財源を投入することも不可欠だろう。
超高齢社会は,経済が急速に発展したことに伴い生じるものと言える。それが暗いものになるとしたら,「戦後の経済発展とは一体何であったのか」ということになりかねない。日本の経済発展を支えてきた団塊の世代が,営々として獲得した自分の住まいのある地域で,子どもたちとも交流しながら安心して老いることのできるシステムがつくれるか。この世代が後期高齢者になるまでの今後十数年間が日本の一つの歴史的な勝負時と言える。
新年のご挨拶――大震災2年 元旦
色平(いろひら) 哲郎(JA長野厚生連佐久総合病院地域医療部地域ケア科医長)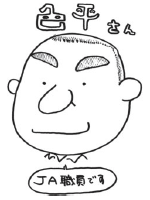 新年,明けましておめでとうございます。
新年,明けましておめでとうございます。
今年はかつてない「政治の年」になる予感がいたします。震災と津波,原発事故からの復旧・復興,野田政権が表明したTPP「事前協議」への参加,増税と社会保障改革など,政治のウェイトはますます高まっています。
政治には長い年月をかけて培われた「流れ」があります。日々のトピックに目を奪われ,政府の流す情報に一喜一憂するばかりでは,流れを読み誤りかねません。そこで,上質の現代政治史を学び直すことが大切になってきます。といっても,忙しい医療従事者が専門書を読み解く余裕はなさそう。まずは一般向けの新書本が手引となりましょう。
例えば,ノンフィクション作家・山岡淳一郎氏が立て続けに出版した『国民皆保険が危ない』(平凡社)と『原発と権力――戦後から辿る支配者の系譜』(筑摩書房)。いずれも現代日本の重要テーマを政治の流れに沿って解説した好著です。
『国民皆保険が危ない』は,明治維新後,医師・後藤新平の奮闘で「疾病保険法」が論議され,「国民健康保険」が生まれたこと。そして戦後,GHQ改革を経て,国保を「最後の砦」に国民皆保険が達成された経緯を詳述しています。「日本の宝」と呼ばれる皆保険が「無保険者の増加」,加えてTPPなど「医療市場化の圧力」,これら「内と外」ふたつの大波で解体の危機に瀕している状況が,医療現場のドキュメントを通じて赤裸々に記されています。
『原発と権力――戦後から辿る支配者の系譜』は,歴代政権がなぜ原...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


