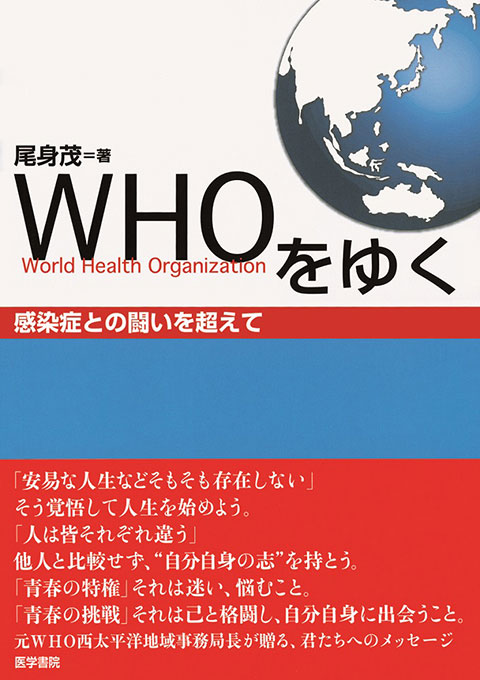シリーズ:この先生に会いたい!!
悩み,失敗して“個性”を獲得する医師の道を歩んでほしい
感染症との闘いを経て,君たちへのメッセージ
インタビュー 尾身 茂,渡邊 稔之
2011.11.07 週刊医学界新聞(レジデント号):第2952号より
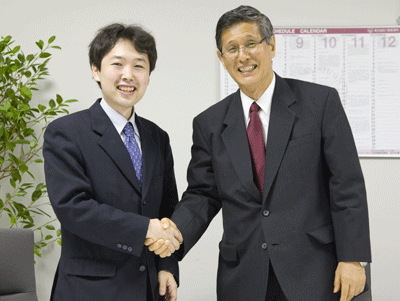
WHOアジア地域における小児麻痺(ポリオ)の根絶を達成し,2003年のSARS対策では陣頭指揮をとるなど,世界の保健医療の発展に貢献してきた尾身茂氏。氏の天職とも言える感染症対策や公衆衛生との出合いに至る背景には,自分探しに明け暮れた"彷徨の青春時代"と"自己との格闘の日々"がありました。
「悩む」ことは若者の特権とも語る氏が,感染症との闘いを経た今だから伝えたいメッセージ。自分を知り,自分の個性を確立するためにはどうすればよいのか。悩める医学生・研修医に贈ります。
渡邊 約20年間WHOに勤務されたなかで,最も印象的なことは何ですか。
尾身 いろいろな経験をしましたが,あえて挙げるとすればアジアにおけるポリオの根絶とSARS対策の2つです。
1990年にWHOに着任してからの7年間は,休日も休まずポリオ根絶に夢中になった時期でした。体力が最もあった40代でのことです。多くの関係者の懸命な努力の甲斐あって,97年を最後に新規のポリオ患者は発生せず,3年後の2000年にアジアでの根絶が証明されました。
一方,WHO西太平洋地域事務局長という立場で対応に当たったSARS対策は,わずか6か月間の出来事でしたが,組織のトップとしての責任もあり緊張の連続でした。WHOの判断,一挙手一頭足が世界の人々の生死にかかわるため,当時は毎日がつま先立って歩いている気分でした。

渡邊 長期にわたって感染症との闘いを続けられた先生のモチベーションとは,何だったのでしょうか。
尾身 人にはそれぞれ異なる好みがあると思いますが,私にとってはたまたま公衆衛生や感染症対策が性に合い,結果的に長く続いたということです。
ポリオ根絶に至る過程ではたくさんの障害に遭遇しましたが,その多くは医学の問題だけではなく,政治的,社会的,経済的な要素が複雑に絡んだものです。こういう障害を乗り越えるためには,細部への注意も大切ですが,全体を考えることも重要です。公衆衛生は対象が多岐にわたる領域ですが,私はこの手の仕事が好きだったので,夢中になれたのだと思います。
渡邊 公衆衛生への興味は,自治医大での学生時代から持たれていたのですか。
尾身 大学時代には特に将来のことは考えていませんでした。ただ,子どものころから人とわいわい交わることが好きでしたし,中・高校時代は生徒会などでまとめ役をすることも多く,そういう意味でも公衆衛生という幅の広い領域と,何となく相性が良かったのかもしれません。
「医者になろう!」
渡邊 先生は,なぜ医師になろうと思われたのですか。
尾身 実は,高校時代には医師という職業を考えたことは全くありませんでした。当時はいわゆる文科系人間で,将来は商社マンか外交官もしくはジャーナリストになりたいと考えていました。
人生にはさまざまな転機がありますが,私の場合,高校3年時の1年間の米国留学でした。当時の彼我の国力の差は明らかで,大きな芝生の庭や各家庭に2台の自家用車といった豊かな生活は鮮烈でした。それまでの日本における18年間の思い出はいわば白黒写真ですが,その1年だけは「天然色」として記憶に残っています。しかし留学後,日本に帰ってみると待っていたのは大学紛争真最中の灰色の世界でした。慶應義塾大学法学部に進んだのですが,商社マンや外交官のような職に就くことは"人民の敵"と見なされる時代です。将来どうしたらいいかわからなくなり,答えを見つけるため通学途中の渋谷の本屋で哲学書,人生論,宗教関係など,さまざまな本を立ち読みするようになりました。

医師になろうと思ったきっかけは,大学2年が終わるころ,クリスチャンとして名高い内村鑑三さんの息子の内村祐之さんによる『わが歩みし精神医学の道』(みすず書房)との偶然の出合いでした。これは医学書ではなく,内村さんの医師としての生涯を振り返った本ですが,読み終えて何かに取りつかれたように「医者になろう!」と思ったことを,今でも鮮明に覚えています。その数か月後,これも偶然,自治医科大学が第1期生を募集していることを新聞紙上で知り,「地域医療」という言葉が将来について悩む心の琴線に触れたのでしょう。自治医科大学を第一志望と決めました。
渡邊 学生時代はどのように過ごされていたのですか。
尾身 私は大学入学時,既に周りの学生に比べ年を取っていたので,大学の先生方も大人として扱ってくれました。そのため,自由におおらかに過ごすことができました。勉強はほどほどで,夜になると医局に行き,先生たちにお酒をごちそうになりながら,いろいろな話を聞く毎日でした。また,大学内の書店の社長さんの家はまさに"学外教養学部"となっており,徹夜でマージャンをしたり,人生論を語り合うサロンのような感じでした。今でも懐かしく思い出します。
渡邊 医学にとどまらない教養を,学生時代に身につけられたのですね。卒業後,WHOで働くことになったのはどのような理由からですか。
尾身 卒業後9年間は,都立病院と伊豆諸島で地域医療に従事しました。大学卒業当時は現在のような多科ローテーション研修システムがあったわけではなく,1期生のため先輩もいないので,研修のルールも決まっていませんでした。1人で伊豆の離島に行くことはわかっていたので,東京都の衛生行政部門との交渉を通じて,都立病院で麻酔科,小児科,外科など救急を中心に研修を受けることができました。幸運だったのは,こうした経験により都の衛生行政部門の人たちとつながりができたことです。彼らとさまざまな交流をするなかで,公衆衛生という世界があることを知りました。
この地域医療への従事の後,当時UNICEFに勤めている友人が勧めてくれたという偶然と,かつて外交官を志望したように潜在的に国際舞台への興味があったという必...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

尾身 茂(おみ・しげる)氏 自治医科大学教授・公衆衛生
慶大法学部中退後,1978年自治医大卒。都立病院,伊豆諸島を中心に地域医療に9年間従事した後,90年WHO西太平洋地域事務局に入る。98-2008年同事務局長。09年より現職。09年の新型インフルエンザ大流行の際には,政府対策本部専門家諮問委員会委員長を務める。WHO執行理事,厚生労働省参与,外務省参与。近著に『WHOをゆく――感染症との闘いを超えて』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。