MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2008.02.18
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


精神障害のある救急患者対応マニュアル
必須薬10と治療パターン40
宮岡 等 監修
上條 吉人 執筆
《評 者》黒川 顯(日医大武蔵小杉病院院長/救命救急センター長)
救急医・精神科医のすき間を埋める一冊
 昨今,精神疾患を有する人が,外傷や疾病になった時の救急医療が大きな問題になっている。この状況に自殺未遂というキーワードが加わると,初期診療をする救急病院を探すことも,身体的問題が解決したあとのフォローアップ医療の担い手を探すことも困難となる。身体科の医師は,精神疾患を診られないから引き取れないといい,精神科の医師は,少しでも身体科の問題が残っている患者は診られないと受け入れを拒否する。結局,何でも引き受けてくれる救命救急センターに運ばれ,身体的問題が解決したり,すべて解決してはいなくても急性期を脱したりした場合に,行く先がないために,いつまでも引き受けざるを得なくなってしまうのである。
昨今,精神疾患を有する人が,外傷や疾病になった時の救急医療が大きな問題になっている。この状況に自殺未遂というキーワードが加わると,初期診療をする救急病院を探すことも,身体的問題が解決したあとのフォローアップ医療の担い手を探すことも困難となる。身体科の医師は,精神疾患を診られないから引き取れないといい,精神科の医師は,少しでも身体科の問題が残っている患者は診られないと受け入れを拒否する。結局,何でも引き受けてくれる救命救急センターに運ばれ,身体的問題が解決したり,すべて解決してはいなくても急性期を脱したりした場合に,行く先がないために,いつまでも引き受けざるを得なくなってしまうのである。
さて本書の随所にみられる薬物動態や病態の解説をみると,著者がそもそもは精神科医だったにもかかわらず,多くの救急疾患の診療にも対応する力を持っていることがよくわかる。それは,東京工業大学理学部化学科を卒業してから医学部に進学したという彼の経歴からすれば当然のこととうなずかされるとともに,持ち前の探求心と,一つひとつの症例を大切にするという日常診療への姿勢によるものであると感心させられる。
近年,精神科医が常駐する救命救急センターが増えているが,精神科医が常駐していない施設もある。そんな施設において,本書は大いに役立つことは必至である。一方,身体科の医師がいない精神科の病院にとっては,精神科医が身体疾患を診たり,病態を考えるきっかけを与えてくれる有用な書といえる。
B6変・頁312 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00496-1


RCA根本原因分析法実践マニュアル
再発防止と医療安全教育への活用
石川 雅彦 著
《評 者》大滝 純司(東医大病院教授・総合診療科)
事故原因の分析だけではなく医療安全教育への活用も
 多くの医療従事者と同様に,私もインシデント・アクシデント事例の報告書を書いた経験が何回かある。それぞれの事例でどのようなことが起き,どのように対処したかを記入して提出するのだが,ちょっと書きにくいと感じるときがある。その事例が生じた原因について記入する欄で,私はいつも少し考えてしまう。疲れていたのか? 急いでいたのか? それとも……まあ,その時々でそれなりに考えて記入してきた。本当にそこで記入したことが原因だったのかなぁ,と少し引っかかりながら。
多くの医療従事者と同様に,私もインシデント・アクシデント事例の報告書を書いた経験が何回かある。それぞれの事例でどのようなことが起き,どのように対処したかを記入して提出するのだが,ちょっと書きにくいと感じるときがある。その事例が生じた原因について記入する欄で,私はいつも少し考えてしまう。疲れていたのか? 急いでいたのか? それとも……まあ,その時々でそれなりに考えて記入してきた。本当にそこで記入したことが原因だったのかなぁ,と少し引っかかりながら。
インシデント・アクシデント事例をもとに,医療のプロセスやシステムに注目し,その問題点を具体的に見つけ出し,対策を立てる。そのような分析を可能にする方法として,米国ではRCA(Root Cause Analysis:根本原因分析法)というのが用いられているのだそうだ。本書は,そのRCAについて詳細に解説したものである。全体で4つの章からなり,最初の「基礎編」ではRCAの概要を,次の第2章「実践編その1」では臨床で実際にRCAを行うやり方について書かれている。
RCAの内容は,あっと驚くようなものではない。米国の教育にしばしば見られるように,言われてみれば当たり前に思える,比較的単純で誰にでもできるような作業の工程が「14のプロセス」として示されている。RCAは組織としてみれば一種の委員会活動であり,「14のプロセス」の中には,委員会の招集のやり方や,その委員会で行う作業手順である「4つのステップ」などが示されている。
第3章「実践編その2」では,このRCAを医療安全教育の体験学習として研修会などで実施する方法を,そして最後の第4章には「応用編」として,RCAのプロセスの中でSAC(Safety Assessment Code)という分類方法により,事例検討の必要性を判定する作業の例題や,研修で用いるための事例などが載っている。
著者の石川雅彦先生は,私のかつての同僚で,現在は国立保健医療科学院で政策科学部長として活躍中である。このRCAを米国で学ばれ,有用性に着目され,その後わが国でもRCAを用いた研修会を数多く実施しながら,このマニュアルをつくり上げたそうである。たしかに本書は,職員の研修などですぐに使えそうな構成になっている。
図表が多用され,硬いテーマであるにもかかわらず,読みやすく理解しやすい点も特筆すべきだろう。インシデント・アクシデントの原因分析に興味がある人や,医療安全教育の具体的な方法を探している人は,ぜひご一読いただきたい。
B5・頁176 定価2,625円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00608-8


新井 達太 編
《評 者》松田 暉(兵庫医療大学長)
若手のみならず指導者にも折りに触れて開いてほしい書
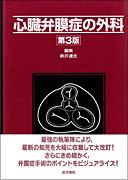 このたび新井達太先生編集の『心臓弁膜症の外科』第3版が刊行された。心臓弁膜症の外科を広くカバーしたユニークなこの教科書も1998年の初版以来10年を経て,今回は先進性,科学性,そして有用性を備えてさらに大きくなった感じがする。
このたび新井達太先生編集の『心臓弁膜症の外科』第3版が刊行された。心臓弁膜症の外科を広くカバーしたユニークなこの教科書も1998年の初版以来10年を経て,今回は先進性,科学性,そして有用性を備えてさらに大きくなった感じがする。
編者の新井先生が序文で述べられているように,今回は新たな項目を加えるとともに,主要な手術については執筆を複数の担当者にして偏りのないように配慮されている。項目としての特徴は,局所解剖と心臓超音波検査エコー診断という外科医にとって重要な基礎的知識にはじまり,各論ではそれぞれの弁膜症の病態生理や自然歴のレビューから,手術適応,遠隔成績まで網羅されていて,読み応...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
