第39回日本医学教育学会開催
卒前卒後の地域医療教育を考える
2007.09.03
卒前卒後の地域医療教育を考える
第39回日本医学教育学会開催
第39回日本医学教育学会が7月27-28日の両日,佐藤俊一会長(岩手医大)のもと,ホテルメトロポリタン盛岡(盛岡市)にて開催された。メインテーマを「地域医療と医学・医療教育」とした今回は,医師不足など地域医療が抱える問題に関し議論が深められた。また,盛岡市出身で国際連盟事務次長などを歴任した新渡戸稲造にちなんだプログラムも企画された。本紙では,卒前卒後の地域医療教育に関するプログラム2題と,昨年から始まった日韓医学教育学会交流事業の一環として企画された招請講演のもようを報告する。
地域基盤型教育の新たな挑戦
 本年3月に取りまとめられた文科省「医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」最終報告では,地域医療臨床実習の強化が提言されている。他方,海外に目を向けると,丸1年間を地域での実習に費やす画期的なプログラムが存在するという。特別講演「Community-Based Medical Education: A New Model for Clinical Education」では,David Prideaux氏(フリンダース大)が,オーストラリア南部における地域基盤型医学教育の取り組みを紹介した。
本年3月に取りまとめられた文科省「医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」最終報告では,地域医療臨床実習の強化が提言されている。他方,海外に目を向けると,丸1年間を地域での実習に費やす画期的なプログラムが存在するという。特別講演「Community-Based Medical Education: A New Model for Clinical Education」では,David Prideaux氏(フリンダース大)が,オーストラリア南部における地域基盤型医学教育の取り組みを紹介した。
フリンダース大では,一部の学生が過疎地域にある総合診療クリニックや小規模病院で1年間の実習を行っている(1グループ8人構成で,計4グループ)。診療科ごとのブロックローテーションはなく,“どのような患者が受診するか”で学ぶ内容も変わる。大学はeラーニングによって,学生の学習をサポート。従来どおり大学病院や市中病院で臨床実習を行う学生もいるが,地域で実習した学生のほうが臨床能力に優れており,学生の満足度も高いという。さらには,卒後に過疎地域で働く医師が増えるなど,労働力としての成果もあがっており,オーストラリア政府もこの地域基盤型教育を推進。他でも同様の試みが始まっていると報告した。
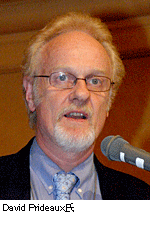 会場からは「教える側の質をどう担保しているのか」との質問が出た。これに対して氏は,臨床医のためのセミナーや修士レベルの教育課程を紹介するとともに,「当初は教育に自信のない一般医もいたが,もともと教育者としての資質があるので大きな支障はなかった」と答えた。また,市内と過疎地域のどちらで実習を行うかは学生の希望をもとに決めているが,過疎地域でのカリキュラムのほうが人気だという。理由は,市内での実習と遜色ない...
会場からは「教える側の質をどう担保しているのか」との質問が出た。これに対して氏は,臨床医のためのセミナーや修士レベルの教育課程を紹介するとともに,「当初は教育に自信のない一般医もいたが,もともと教育者としての資質があるので大きな支障はなかった」と答えた。また,市内と過疎地域のどちらで実習を行うかは学生の希望をもとに決めているが,過疎地域でのカリキュラムのほうが人気だという。理由は,市内での実習と遜色ない...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
