MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.03.12
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


大熊 輝雄,松岡 洋夫,上埜 高志 著
齋藤 秀光,三浦 伸義 執筆協力
《評 者》松浦 雅人(東医歯大大学院教授・生命機能情報解析学)
臨床脳波判読医養成に効果的な標準テキスト
 脳波は波形が複雑に変動するだけでなく,頭蓋上の多くの部位から長時間にわたって記録するため,全体を総合的に把握しなければならない。初学者にとってはどこから手をつけてよいかわからず,取りつきにくいとの印象を持つのも頷ける。本書はこれから脳波判読を習得しようとする人のために書かれたもので,初版が1986年なので20年の歴史を持つことになる。前回の第3版の改定から7年を経過し,今回さらに加筆・増補が行われた。
脳波は波形が複雑に変動するだけでなく,頭蓋上の多くの部位から長時間にわたって記録するため,全体を総合的に把握しなければならない。初学者にとってはどこから手をつけてよいかわからず,取りつきにくいとの印象を持つのも頷ける。本書はこれから脳波判読を習得しようとする人のために書かれたもので,初版が1986年なので20年の歴史を持つことになる。前回の第3版の改定から7年を経過し,今回さらに加筆・増補が行われた。
「入門編」ではステップ1からステップ14まで,段階を追ってていねいに脳波判読の手ほどきをしてくれている。各ステップにはたくさんの練習問題がついており,例えば1週間に1ステップの練習問題をクリアすることを目標にすれば,3-4か月で脳波判読の基本を修得できる。脳波図版は原寸大であり,計測用の脳波スケールがついているのも親切である。手を使って脳波波形にスケールを当てて,実際に計測することではじめて波形の観察力が深まる。ステップ1では周波数や振幅の計測の仕方を体験し,次いでステップ2からステップ3にかけて位相や左右差,分布や局在など,次第に複雑な波形の計測法を学ぶ。さらに,脳波記録法,アーチファクト鑑別法,賦活法,成人脳波,睡眠脳波,異常脳波とステップアップしてゆく。ステップ11からは小児脳波の分野に入り,ステップ14の老年者の脳波判読を終えると,すべての年代の脳波判読をカバーしたことになる。
「症例編」ではステップ1のてんかんから,ステップ11の精神疾患まで,脳波判読にとって重要となる疾患が網羅されている。今回の改訂では,レビー小体病や白質脳症など最近注目されている疾患の脳波や,選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や非定型抗精神病薬による脳波変化が追加されている。最後のステップ12には33個の練習問題がついており,これにチャレンジすることで自らの臨床脳波判読の実力を確認できるように工夫されている。
「入門編」「症例編」に共通する特筆すべき点は,個々の脳波図版の説明として記載されている「脳波所見」が,そのまま脳波記載法の範例となっていることである。脳波判読ができるようになれば,その所見を的確に記載する技術が必要となるが,本書は豊富な記載例を提供してくれていることになる。このような脳波図版が,「入門編」では103枚,「症例編」では178枚もある。長年にわたって貴重な臨床資料を蓄積し,さらに新しい情報を追加しつつある東北大学脳波グループの努力に敬意を表したい。
最近は,臨床脳波を正確に判読できる医師がどんどん減っているように思われる。不正確な脳波判読は誤診の原因となるため,脳波判読医がいない施設は脳波検査をしないほうがよいとの極論もある。脳波指導医は臨床脳波が判読できる若手医師の養成に苦慮していると思われるが,本書を利用することによって判読医養成がより効果的になると思われる。脳波専門医にも目を通してほしい臨床脳波判読のための標準的テキストである。
入門編 B5・頁468 定価7,875円(税5%込)医学書院
症例編 B5・頁404 定価9,450円(税5%込)医学書院


武藤 徹一郎,幕内 雅敏 監修
川崎 誠治,佐野 俊二,名川 弘一,野口 眞三郎,平田 公一 編
渡邉 聡明 編集協力
《評 者》兼松 隆之(長崎大教授・移植・消化器外科)
外科専門医のためのスタンダードテキスト
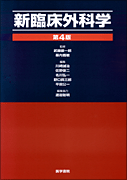 外科教科書のスタンダードとして,定評のある『新臨床外科学』が,このたび第4版として上梓された。この衣替えでさらに魅力的な特徴を打ち出している。
外科教科書のスタンダードとして,定評のある『新臨床外科学』が,このたび第4版として上梓された。この衣替えでさらに魅力的な特徴を打ち出している。
〈第1の特徴〉外科専門医のためのスタンダードテキストとしての位置付け
『新臨床外科学』の初版は医学部の5・6年生や研修医などを対象とした教科書としてスタートした。そのため医師国家試験対策や臨床研修の中でも,外科に必要な基本的な知識を得るのに十分な配慮のもとに編纂されてきたが,第4版でもその方針に揺るぎはない。そのうえでページ数を増加させ,“外科専門医”をめざす者のスタンダードテキストとしても使えるように,内容が高度化されたのが大きな特徴である。
〈第2の特徴〉医学生のチュートリアル・臨床実習教育でも使いやすい内容
医学生諸氏にとっては,最近では与えられる知識より,自らが調べ,学ぶ教育へとシフトしている。それに対応するためには,教科書に掲載されている内容にはそれなりの深みも求められる。今回の改訂版でも,「基礎的知識」の項には十分なスペースを割いている。また,外科治療についても単に手法を述べるにとどまらず,治療成績も最新のものが図示されていることなど,卒前の医学教育においても使いやすく,また重厚さも併せ持った座右の書となった。
〈第3の特徴〉写真・図が豊富で鮮明さは特筆もの
いまや,医学教育には画像診断や病理所見等を理解することは必須である。医師国家試験でもそれらの知識と理解力を求める問題も少なくない。幸い,本書には,典型的なX線,エコー,MRI,内視鏡写真から病理の肉...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
