MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.01.15
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


金澤 一郎,北原 光夫,山口 徹,小俣 政男 総編集
《評 者》高久 史麿(日本医学会長・自治医大学長)
広範な領域をまとめて医学的知の集大成
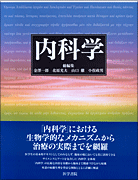 医学書院から最近刊行された金澤一郎,北原光夫,山口徹,小俣政男4氏の総編集による『内科学』の書評を頼まれ,お引き受けした所,早速『内科学I・II』が私の事務室に送られてきたが,まずその量が膨大なのに驚いた。執筆者の数も同様に膨大である。
医学書院から最近刊行された金澤一郎,北原光夫,山口徹,小俣政男4氏の総編集による『内科学』の書評を頼まれ,お引き受けした所,早速『内科学I・II』が私の事務室に送られてきたが,まずその量が膨大なのに驚いた。執筆者の数も同様に膨大である。
その内容を見てみると,I巻のIの「社会の中の内科学」の見出しが目にとまった。確かに医学は理系の学問の中では社会との接点が最も幅広い学問分野であり,その中で内科学が中心であることは周知の如くである。その意味で内科学書の最初の項目として,このような幅広い問題を取り上げたことは高く評価されるべきであろう。
次のIIの「内科学の進歩」では最近の医学の進歩を,内科学を中心にまとめて紹介している。このことも本内科学書の新しい試みであると考えられる。
次に系統ごとの疾患の項目を見てみると,本内科学書の各系統の最初に感染症を持ってきたこと,しかもその内容が従来のわが国の内科学書よりもより充実したものになっていることが注目された。近年民族間の国際的な交流が盛んになり,SARSや鳥インフルエンザ等の新たな感染症の国際的な広がりが大きな話題になっていること,医療の安全と関連して院内感染症が問題になっていること等の昨今の状況を考えると,この試みは時宜を得ているということができるであろう。また各系統の疾患の記載の最初には「理解のために」という項目が必ず設けられ,各系統の疾患の総論的な事項が紹介されている。内科学という広範な領域を一冊の本でカバーしようとするならば,このような系統ごとの総論的な記載は当然なされるべきである。
私はこの書評を書くに当たり,総編集の方々による本書の序文を読ませていただき,皆様方のこの内科学書に対する意気込みと同時に,完成までのご苦労を十分に汲み取ることができた。
本書の完成に貢献された諸氏のご尽力に敬意を表する次第である。


池田 健次,宗村 美江子 編
《評 者》木下 祐加(虎の門病院・後期研修医)
毎日の臨床の場で活きる親しみやすい肝疾患の入門書
 「実践 肝疾患ケア」は,「実践」「ケア」という二つの言葉からわかるように,肝疾患の患者さんをいちばん近くで支える人たちの役に立つように,という思いから書かれた本です。執筆も編集も,現役で肝疾患治療に携わっている医師と看護師によって行われています。
「実践 肝疾患ケア」は,「実践」「ケア」という二つの言葉からわかるように,肝疾患の患者さんをいちばん近くで支える人たちの役に立つように,という思いから書かれた本です。執筆も編集も,現役で肝疾患治療に携わっている医師と看護師によって行われています。
この本は,日本における肝疾患の主要テーマである,ウイルス性肝炎・肝硬変・肝がんに焦点を絞り,それぞれについて診断と治療をわかりやすく示しています。
ひととおりさらっと目を通すだけで大まかな流れをつかむことができるので,これまで肝疾患に関わったことのない人の入門書として最適です。例えば,ウイルス肝炎におけるマーカーの評価方法,肝がんの各種治療方法など,学生時代に一度は習っていても実際にどうしたらいいかわからない時には,この本をぜひ手にとってください。
一方で,「どうしてそうなるのか」という科学的根拠が所々に散りばめられていて,肝臓を専門にする予定の人が読んでも,また新たな知識が得られると思います。最近話題のインターフェロン治療についても,その適応と治療成績がわかりやすくまとめられていて,患者さんからの質問に答える際に役立ちます。ガイドライン,症例報告,臨床試験などがふんだんに盛り込まれており,見た目の親しみやすさから想像できない充実した内容になっています。
虎の門病院の「肝臓科」スタッフによってつくられた最新の肝臓ハンドブックを,ぜひ毎日の診療の場で活用してください。


木田 厚瑞 著
《評 者》川上 義和(KKR札幌医療センター院長)
在宅酸素療法の重要知識を要領よくまとめた実践書
 このたび出版された第2版は,1997年の第1版に続く改訂版である。しかし,単なる改訂版ではなく,ほとんど全面的に書きかえられたことが明瞭であり,木田厚瑞教授のこの本に賭ける情熱と熱気を堪能させるものとなった。
内容をまったく一新した第2版
このたび出版された第2版は,1997年の第1版に続く改訂版である。しかし,単なる改訂版ではなく,ほとんど全面的に書きかえられたことが明瞭であり,木田厚瑞教授のこの本に賭ける情熱と熱気を堪能させるものとなった。
内容をまったく一新した第2版
第2版では疾患の一般的な解説を避け,また原理など基礎的な事項は最低限に抑えられており,実地的なマニュアルとして一新された。コンセプトが明快に書かれていること,在宅酸素療法の関連領域――つまり包括的リハビリテーション,医療連携,医療倫理とインフォームドコンセントを踏まえたうえで,在宅酸素療法の効果など実際的な記載となっている。
第1版ではこれら前段階の記述が少なく,機器の構造や取り扱い方法が比較的多かった印象があるが,第2版ではこれらの機器に関する項目は少なくなっている。医療職としては,構造などは常識として知っていればよく,実際的なことは業者が行うという理由からであろう。「NOTE」として知っておいたほうがよい知識やメモが随所に要領よくまとめられているのも,新しい点である。 重点的に書かれている第2版
第1版は22章からなり,これに統計資料,様式などが参考資料として追加されていた。第2版ではこれら参考資料はよく取捨選択されて章の中に記載されていて,読みやすいように工夫されている。総ページ数は増えているが章の数は15に減っており,それだけ項目と内容を吟味して絞られた結果であろう。
とくに重点が置かれているのは,在宅酸素療法における日常生活の評価と指導,急性増悪への対応,薬物療法などであろう。急性増悪をどう発見するか,専門施設への紹介のタイミングなど詳細に書かれており,薬物療法の重要性も適切に評価されている。これらはいずれも実地医家の参考になることばかりである。 新しい領域について書かれている
在宅人工呼吸療法(NIPPV)が広がりを見せているなか,これについても詳しく書かれているのが第2版の特徴である。病院から自宅へ移る基準,コンプライアンス,長期NIPPVの導入基準など,日常の管理に役立つ記載である。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)についての知見が増えているところから,在宅酸素療法の観点からこれら新しい知見を積極的に紹介して,実地診療に役立てるのに貢献している。実際,在宅酸素療法の導入基準などはCOPDの研究から生まれたものであり,また患者の多数がCOPDで...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
