第7回日本クリニカルパス学会開催
パスのさらなる進化を目指して
2007.01.08
パスのさらなる進化を目指して
第7回日本クリニカルパス学会開催
第7回日本クリニカルパス学会がさる11月17-18日,副島秀久会長(済生会熊本病院)のもと,熊本県立劇場(熊本市),他にて開催された。メインテーマを「クリニカルパスのさらなる進化を目指して」とした今回は,医療の質管理の専門家であるY.Dlugacz氏(North Shore-Long Island Jewish Health System)を特別講演に迎えたほか,連携パスや電子カルテ,記録など話題のテーマでプログラムが組まれた。また新しい試みとして,現場や組織の悩みを本音で語る「全国パス委員長会議」が企画された。本紙では,会長講演とシンポジウム「クリニカルパスと記録」のもようを報告する。
標準化から電子化,医療の質向上へ
 クリニカルパスは1980年代に米国の看護師カレンサンダーによって開発された治療計画表で,現在は医療の質を保証するツールとして発展している。日本では,90年代から普及が始まり,剃毛廃止や抗菌薬の適正使用,NST活動の促進など様々な成果をあげてきた。済生会熊本病院では96年から先駆的にパス活動を開始。2002年にはTQM(総合質管理)センターを立ち上げ,医療の質管理に取り組んでいる。
クリニカルパスは1980年代に米国の看護師カレンサンダーによって開発された治療計画表で,現在は医療の質を保証するツールとして発展している。日本では,90年代から普及が始まり,剃毛廃止や抗菌薬の適正使用,NST活動の促進など様々な成果をあげてきた。済生会熊本病院では96年から先駆的にパス活動を開始。2002年にはTQM(総合質管理)センターを立ち上げ,医療の質管理に取り組んでいる。
同センター長でもある副島氏による会長講演「クリニカルパスの現状と将来」では,冒頭でパスの歴史を回顧。現在は300床以上の病院の8割で,パスが使用されている現状を紹介した。続いて,アウトカム(治療の過程で望ましい結果や目標)とバリアンス(アウトカムどおりいかない状態)の考え方に言及し,「アウトカムが達成されなければ,すべてバリアンス」と定義。中でも,クリニカルインディケーター(治療経過に重大な影響を与えるアウトカム)はチームで共有すべき情報で,バリアンスが出たら早急に対処すべきとした。
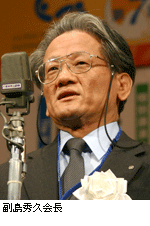 また,記録の電子化によるバリアンス収集分析の効率促進が期待されているが,「その前に医療内容や用語・病名の標準化を進めるべき」と提言。標準化を果たさないままの電子化では,効果的な分析はできないとの見解を示した。将来的には,各施設のパスの比較による標準化作業を実施,さらにバリアンス分析を通してベンチマークを進めることを課題に挙げた。最後に,パスが動きやすい病院組織の改革と,パスを動かす人材の教育を最重要課題として講演を閉じた...
また,記録の電子化によるバリアンス収集分析の効率促進が期待されているが,「その前に医療内容や用語・病名の標準化を進めるべき」と提言。標準化を果たさないままの電子化では,効果的な分析はできないとの見解を示した。将来的には,各施設のパスの比較による標準化作業を実施,さらにバリアンス分析を通してベンチマークを進めることを課題に挙げた。最後に,パスが動きやすい病院組織の改革と,パスを動かす人材の教育を最重要課題として講演を閉じた...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
