市中病院におけるロボット支援下手術の効率化と費用対効果の向上
寄稿 坂本育子
2024.07.09 医学界新聞(通常号):第3563号より
手術支援ロボットは,従来の開腹手術や腹腔鏡下手術と比較して,低侵襲で精密な手術を可能にする革新的な医療機器として,外科医療にパラダイムシフトを起こした。しかし,高額な導入費用に加え,ロボット自体の維持管理費や手術で使用する消耗品の費用などランニングコストも高額であるという課題を抱えている。特に,限られた経営資源の中で医療を提供する地方病院において,高額な医療機器の導入は容易ではなく,その費用対効果を十分に検討する必要がある。
本稿では,当院婦人科における手術支援ロボットの効率的運用と費用対効果向上のための多角的な取り組みについて報告し,地方病院におけるロボット支援下手術の普及に向けた課題と展望を考えたい。
病院経営上の課題
婦人科で一般的な手術である子宮摘出術は,従来経腟あるいは開腹術で行われてきた。近年では低侵襲性と合併症の少なさから腹腔鏡手術に移行してきているものの,腹腔鏡器械の技術的限界などにより手術が制限されることも多い。一方,ロボット支援下手術は腹腔鏡下手術と比較して,3D拡大視野による鮮明な術野,手ぶれ防止機能による安定した手術操作,人間工学に基づいたコンソールによる術者の疲労軽減など,多くの利点が注目されている。これらの利点により,手術時間の短縮,出血量の減少,合併症リスクのさらなる低減,術後の疼痛軽減,早期回復などが期待されている。当院は2016年に手術支援ロボット「da Vinci® Xi Surgical System」を導入した(写真)。18年に子宮良性腫瘍,悪性腫瘍(子宮体がんに限る)におけるロボット支援下手術が保険収載となったことを機に,当院の婦人科領域でも積極的にロボット支援下手術を行うようになり,その件数は年々増加傾向である。

しかし,高額な導入・運用コストやロボットのセッティング・ドッキングに時間がかかることによる手術時間の延長などの課題もある。これらの課題を克服するには手術室全体での取り組みが必要不可欠であると考え,ロボット支援下手術をより安全で効率的に,そして多くの患者に提供することをめざして院内で検討を進めていた。
多角的な戦略による効率化と,費用対効果向上への取り組み
ロボット支援下手術の推進について院内のコンセンサスを得るには,費用対効果の向上が不可欠である。当院では,手術支援ロボットを「高価な医療機器」としてではなく,「汎用性の高い医療機器」としてとらえ,以下の取り組みを通じて,費用対効果の高い運用モデルの構築をめざした。
①手術工程の見直し:手術時間の短縮と標準化を達成する...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
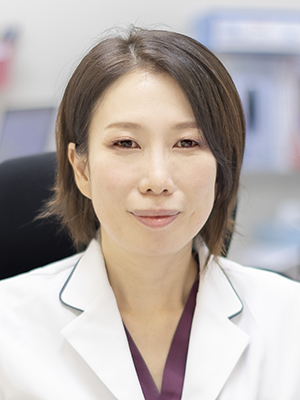
坂本 育子(さかもと・いくこ)氏 山梨県立中央病院婦人科 部長
2002年筑波大医学専門学群卒。国立病院機構名古屋医療センターなどを経て,07年から山梨県立中央病院に勤務。17年より現職。産婦人科専門医。日本ロボット外科学会国内A級専門医。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
