新医師臨床研修制度の20年,変わるものと変えてはいけないもの
対談・座談会 井村洋,福岡敏雄
2024.03.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3557号より

2004(平成16)年にスタートした新医師臨床研修制度により臨床研修が必修化されてから20年が経過した。同制度では「医師としての人格の涵養と基本的な臨床能力の修得」という基本理念と,行動目標・経験目標から成る到達目標が示され,これらに基づいた臨床研修が行われてきた。この20年間,医学生・研修医やスタッフ医師,さらには病院,地域にどのような変化があったのか。今後さらに何が求められるのか。新医師臨床研修制度の創設以前より研修医教育に携わる井村氏と福岡氏が議論を行った。
井村 私たち二人の共通点としては,2004年の臨床研修の必修化以前から研修医教育に携わってきたことが挙げられます。今日の対談を通してこの20年の変化を振り返ると同時に,医学生・研修医やスタッフ医師,さらには病院,地域に与えた影響を検証したいと思います。
必修化がもたらした診療の標準化と地域医療への貢献
井村 新医師臨床研修制度では「医師としての人格の涵養と基本的な臨床能力の修得」という基本理念・到達目標が示されました。2年間の研修プロセスで実施すべきことが明確になり,EPOC(臨床研修評価システム)などを用いておのおのの施設で評価を実施する仕組みが整備されたことは良い変化です。
一方で,臨床研修の必修化による具体的なアウトカムはどうかと言うと,例えば「基本的臨床能力の向上に伴い,非専門医による時間外診療における何らかの改善」などといった確固たるエビデンスがあるわけではありません。必修化の前後を振り返ってみて,どのような変化があったと福岡先生はお考えでしょうか。
福岡 そもそもの臨床研修必修化の背景としては,出身大学やその関連病院での研修が中心で,専門の診療科に偏った研修が行われていたことが挙げられます。当院も,2000年頃は医局からの医師派遣に依存していました。地方にある病院として強い危機感があったことから自前での臨床研修の仕組みを整備し始めたわけです。
20年の間に紆余曲折ありましたが,臨床研修修了後もスタッフとして勤務してくれる医師が増えたことで病院の規模を拡大することができました。救急を含め,地域のニーズに応えられる医療がようやく提供できるようになったと実感しています。
井村 今振り返ると,当院も似たような状況でした。昔は輸液の組み方一つをとっても出身大学の流派があり,抗菌薬の使い方や心肺蘇生の方法さえ標準化されていませんでした。そもそも標準という発想がなかったのかもしれません。この20年間の変化としては,臨床研修が整備されたことで診療が標準化された部分は間違いなくあります。救急や感染症診療といった臓器横断的な領域は特にその傾向が強いですね。
福岡 それは臨床研修だけでなく,卒前教育が変わったことも大きいと思いますよ。今の卒前教育は臨床推論のケースディスカッションがあって,私たちが受けてきた教育とは別物ですから。
井村 そうですよね。国家試験問題を試しに解いてみると,以前よりも正解にたどり着ける問題が増えました。瑣末な医学知識ではなく,実臨床での思考プロセスが問われている印象を受けます。
福岡 医学部は「普通の医師をちゃんと育てる」ということに焦点を絞り,患者に無用のリスクを負わせないという方向性も徹底されました。そのおかげで,従来よりも「患者が診られる」卒業生を受け入れることができて,現場の負担は相当減りました。つまり,卒前から卒後,さらには生涯学習という全体で考えてみると,臨床研修には大きな波及効果があったと思うのです。
研修の標準化による研修医の病院選びの変化
井村 医学生が研修病院を選ぶ際に重視するポイントも変わりました。病院の雰囲気や症例数はもちろん,給与やワークライフバランスも重視されるようになっています。情報収集の手段も,病院のWebサイトに掲載される広報内容だけでなく,在籍する研修医や見学者の声も重視しているようです。
福岡 それで言うと,当院でたまに不満の声として挙がるのは「手技の経験が積みにくい」というものです。臨床研修という枠組みの中で手技の習得と経験をどのレベルで求めるかは十分に考えなければなりません。そのため当院では緊急気管挿管や中心静脈カテーテル挿入などのトレーニングコースを病院として提供しています。「研修医1年目が侵襲性の高い手技をいきなり任される病院に患者として行きたいか」と問われれば答えは当然決まっているでしょう。
井村 わかります。何か問題が起こってからでは遅い。当院では数年前から取り組んでいることではありますが,シミュレーショントレーニングで一定基準をクリアしてから実施するなど,力量と安全を担保した手技の研修体制を整備しておくことが当然と考えるべき時期を迎えていると思います。
福岡 他方,最近は地元や出身地近くの病院で臨床研修を受ける傾向もあるのではと思います。昔は人気研修病院には遠方からも結構な応募がありましたが,今はそれほど多くない。また,臨床研修を修了して専門医研修に進むタイミングで,将来の子育てを考慮して実家近くの病院を選ぶパターンも増えました。
井村 その傾向は全国どの病院でも研修が標準的になり,充実した研修が受けられるようになってきたことの表れで,良い変化なのだろうと思います。
研修医の成長を評価し,不調にも気付く
福岡 新医師臨床研修制度の次のステップとして,2018年度から新専門医制度が始まりました。私は新専門医制度による臨床研修へ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
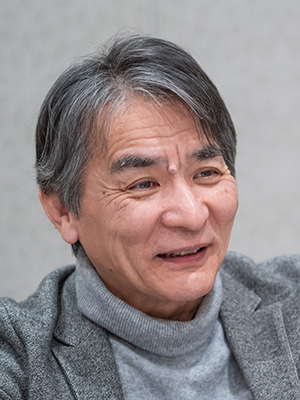
井村 洋(いむら・ひろし)氏 飯塚病院特任副院長 / 研修管理委員長
1981年藤田保衛大(当時)卒業後,同大病院,国立熱海病院(当時)などを経て98年飯塚病院に入職する。当時設立直後で指導医3人,ローテート研修医4人が所属する総合診療科を率いる。以降,特定の臓器に偏らず患者さん全体を診る,総合力を重んじた診療で規模拡大を果たす。新医師臨床研修制度の創設以前より,ローテート方式による臨床研修を採用していた同院で内科研修の指導医として研修医教育に携わり,2007年からは研修管理委員長を務める。現在は総合診療科部長と特任副院長を兼務する。日本内科学会指導医。日本病院総合診療医学会認定特任指導医。日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医。

福岡 敏雄(ふくおか・としお)氏 倉敷中央病院副院長 / 人材開発センター長
1986年阪大卒業後,同大病院,倉敷中央病院を経て91年名大病院に就職。名大病院では卒後臨床研修センターの立ち上げにかかわる。2006年倉敷中央病院へ復職し,総合診療科主任部長兼医師教育研修部長に就任。研修医のリクルートと救急科での研修医教育に携わる。10年より救急医療センター主任部長,13年救命救急センター長を兼務し,同院の救急ICU立ち上げにも尽力する。14年からは同院人材開発センター長に就任し,国内の市中病院では最多クラスの後期研修プログラムの構築に尽力する。16年より集中治療科主任部長兼任。日本救急医学会救急科指導医。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
