BPSモデルを活用して,良医をめざす
寄稿 小坂文昭
2023.05.15 週刊医学界新聞(レジデント号):第3517号より
診療に追われる医師の皆さまは,外来の待ち時間問題,患者満足度や治療効果,服薬アドヒアランスの問題,救急対応など日々,さまざまな課題に直面されていると思います。生物心理社会モデル(Bio-Psycho-Social model,以下BPSモデル)はこれらの問題の解決に有用です。
本稿では,BPSモデルの基礎について解説します。これから慢性疾患の患者の対応をする医師の方々,特に若手医師の方々にぜひ活用していただければ幸いです。
BPSモデルの概要
急性期疾患よりも慢性疾患の患者が増加した現代の医療において,伝統的に行われてきた生物学的なアプローチに加え,患者の社会面や心理面に配慮したアプローチが重要になってきています。そんな中でおよそ40年前にG. Engelによって提唱されたのが,BPSモデルです1)。BPSモデルとは,病気を単なる生物学的な問題としてとらえるのではなく,心理的,社会的背景も重要な要因としてとらえるというものです。医療者は患者の病気の状況だけでなく,その背景にある生活環境や心理的要因なども含めた全体像を把握し,より適切な医療を提供することをめざします。
BPSモデルによって,患者の医療アクセスや健康状態の改善,救急医療・入院の減少2)や医療費の抑制3)などさまざまな効果を得られることがわかっています4~6)。
また,問診時のコミュニケーションにBPSモデルを用いることは患者との信頼関係構築にも役立ちます。患者の心理的背景,社会的背景,環境を掘り下げ,理解することは「薬を処方して終わり」の外来と比較すると時間を要します。ですが,時間をかけて事情を伺い,「自分のことを理解してもらえた」と感じてもらうことは,信頼関係構築に大いに役立ちます。治療がうまくいき,症状が安定する確率を上げられるため,その後の診療時間短縮にもつながります。一回の診察で必要な情報を全て聴取するのが現実的に難しいこともありますが,そうした場合は頻回に受診してもらい,ヒアリングを行いましょう。人が信頼感を抱くには,対象に会っている時間の長さよりも会う回数が重要なため7),診察の回数を重ねることで得られる情報も多いでしょう。
生物・心理・社会を分割せず,総合的に介入する
BPSモデルによくある誤解は,「生物学的な問題は〇〇で,心理学的には××,社会背景は△△である」のように3分割して介入を行う,というものです。もしこのようにそれぞれを分割できれば問題を単純化できてとてもわかりやすいですが,生物・心理・社会の要素は独立した事象ではなく互いに影響し合って現在の問題が起こっているという視点が欠けています。それぞれを分割して考えるのではなく,総合的に理解し包括的に介入することが必要になります。
前述したEngelは,個人を中心にそれぞれマクロとミクロのベクトルへ階層が存在し,相互に影響し合っているとしました。
宇宙⇔地球⇔国⇔都市⇔近隣地域⇔コミュニティ⇔家族⇔個人⇔神経⇔臓器⇔細胞⇔原子
影響力は階層がマクロ(宇宙)からミクロ(原子)にいくにしたがって弱くなり,変化の速度はミクロ(原子)からマクロ(宇宙)にいくにしたが...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
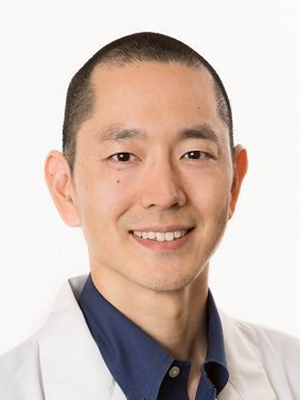
小坂 文昭(こさか・ふみあき)氏 こさか家庭医療クリニック 院長
2005年兵庫医大卒。南部徳洲会病院で初期研修ののち,08年亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科,11年沖縄県立八重山病院での勤務などを経て,14年より現職。家庭医療専門医。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
