安全かつ効率的な病院間搬送の実践をめざして
対談・座談会 川口敦,奈良理,野澤正寛
2023.05.08 週刊医学界新聞(通常号):第3516号より
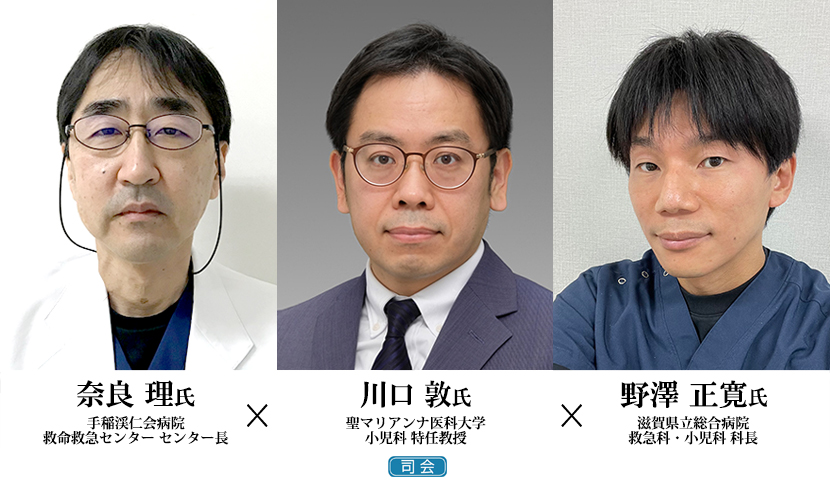
手術室からICUへの搬送,画像診断のための検査室への搬送,あるいは病院間搬送など,搬送には種々の場面があり,携わった経験のない医師はいないだろう。搬送に当たっては,患者の状態,必要物品や人的サポートを含めた環境も多様であることから,準備が特に必要な場面とも言える。搬送にまつわる医療は,北米や欧州を中心に2000年前後から「搬送医学(transport medicine)」として独立した医学分野となった。日本でもまもなく日本集中治療医学会が策定するガイドラインが公開される見込みであり,「搬送」が注目を集めている。そこで本紙では,小児集中治療医として搬送医学に関する研究と診療に10年以上携わってきた川口敦氏を中心に座談会を企画。病院間搬送を取り巻く国内の課題を取り上げ,解決策を見いだしていく。
川口 患者搬送を行う場面はさまざま存在し,病院間搬送と一口に言っても,高次医療機関への搬送,急性期病院から慢性期病院への搬送,予定搬送,緊急搬送と多岐にわたります。ほとんどのケースで合併症は発生せず滞りなく行われますが,万が一搬送中に問題が起こった際の対策を想定できている医療者はどれだけいるでしょうか。「安全に運ぶ」との視点が抜け落ちている方が多いのではと私は懸念しています。特に「余力のない」重篤な状態にある小児患者では,この視点が強調されるべきです。そこで本座談会では,搬送医療,とりわけ問題となりやすい小児領域の病院間搬送の課題に焦点を当てながら,安全で効率的な搬送の実現に向けた議論を進めていきたいと思います。
「搬送」をリスクのある業務と認識しているか?
川口 搬送に当たって押さえるべき大原則は,何らかの「リスク」を伴うということです。北海道で航空搬送業務を含めた救急診療に長年従事してきた奈良先生,そして小児救急医として滋賀県で小児救急システムを構築した野澤先生はじめ,搬送に日々携わる救急・集中治療領域の医師にとって搬送業務の危険性が高いことは共通認識だと思います。その一方で一般の医療者が搬送業務の安全確保に注意を向けづらい理由として考えられることはありますか。
奈良 思いつくのは日本の医療システム上の問題です。重症例であってもある程度診られる病院が複数ある中で,「高次医療機関に運ぶしかない」というギリギリの状況になって初めて病院間搬送が検討されることが多いために,「安全に運ぶ」というよりは,高次医療機関で治療を提供するために「早く運ばなければ」との思いが先走っているのではないでしょうか。私自身も数多く搬送に携わってきたからこそ意識するようになりましたが,そうでなければ「次の施設に何とか運べてよかった」と安堵し,搬送過程の安全性を見直すことはしなかったはずです。
野澤 問題が表面化していないからこそ,その危険性を見過ごしているケースもあると考えます。つまり,「これだけ重症だったら搬送中に亡くなってしまってもしょうがない」「SIDS(乳幼児突然死症候群)だよね」と片付けられた症例の中に,PICU(小児集中治療室)の医師や小児救急医といったスペシャリストが携わっていれば救命可能であった症例が存在する可能性です。多くの症例に当たって経験を積める成人とは異なり,もとより重症の症例数が少ない小児の場合では対応の練度が上がらないのは当然です。こうした経験の差も問題の背景にあるのでしょう。
解決策の1つとしての迎え搬送
川口 では,より具体的な話に移っていきます。誰がどう搬送に携わるかは重要な問題です。特に小児の場合は,搬送経験がほとんどない一般小児科医が関与するケースが多いと言えます。共に対応に当たる看護師も同様で,経験の少ないチームによって搬送を実施せざるを得ない現状です。そうすると,患者が悪化の傾向を示したとしても搬送という選択をすぐに決断できず,施設で対応できる限界まで患者を引き留めてしまいかねません。そこで1つの解決策が「迎え搬送」です。当院でも日中に限りますが,要請を受ければ重症小児患者搬送の専門チームがドクターカーを利用して患者をピックアップしに行きます。
奈良 専門の搬送チームを組織しているわけではありませんが,当院でも最近小児の迎え搬送をするようになりました。搬送元の施設に打診をすると,「迎えに来てくれるんですか!?」と驚かれることもあるようです。そもそもこれまでの搬送の仕組みは,搬送元の医師が消防などに連絡し,搬送車両等の手段を手配してもらい,その医師が同乗する形で行われてきました。搬送経験に乏しい医師であれば戸惑うことは必至です。中でも搬送に航空手段を用いる場合は,機内がどのような仕組みなのか,揺れの程度はどうかもわからないでしょう。それゆえ北海道で運用される固定翼機(メディカルウイング,MEMO①,写真)では,このような情報に加え,当院と札幌医科大学附属病院のメディカルディレクターが搬送に当たっての固定方法や人員,関係機関との調整などを行うことで,安全性を担保しています。

a:使用機体は,左からBeechcraft King Air 200,Cessna 560。b:機内には,医療機器用の電源,酸素供給や吸引装置などが備え付けられている。
川口 野澤先生は,現在の施設で新たな搬送体制を構築されようとしている状況だと思いますが,以前立ち上げられた「滋賀モデル」(MEMO②)の際は,システム面や人材集めはどのような戦略で進められたのでしょう。
野澤 人材については,取り組みの宣伝も含めて搬送に関する論文を和文で数多く執筆したところ,関心を持った医師が集まるようになりました。システムの運用面で意識したことは,近隣の病院への活動の周知と診療支援です。病院間搬送というと,搬送方法の課題を中心に考えがちですが,搬送中の院外環境に耐えられるような全身状態への立ち上げと,その維持ができなければ搬送はかないません。ですから,「困ったらいつでも呼んでください」と各病院にアナウンスして回り,まずは困っている病院へ小児救急医をデリバリーすることを第一に考えていました。コンサルトに基準は特に設けていなかったので,けいれん重積で呼ばれることもあれば,呼吸不全で心臓が今にも止まりそうというギリギリの段階で呼ばれるなど,ケースの重症度は千差万別でしたね。
専門チームによる搬送のメリットを周知する
野澤 ただし,ここでポイントなのはコンサルト元の医師と共に救命救急を行うこと。一緒に取り組むことで,「専門チームがいれば,自分たちでも助けられた」との成功体験を芽生えさせることを念頭に置いていました。
川口 搬送業務を通じてコミュニケーションを取るという手法ですね。素晴らしいです。
野澤 スペシャリストの存在意義を理解してもらわない限り,搬送の重要性を浸透させることは難しいと考えます。そのために,搬送時も座席数が許せば主治医に同行してもらい,筋弛緩薬や鎮静薬を用いて患者の状態をコントロールしたり,EtCO2モニターを付けたりなどの工夫を施しながら搬送する様子を見てもらっていました。搬送が無事に終われば,搬送先の先生も交えて症例の振り返りをし,診療レベルの向上にも努めていました。
川口 一方で迎え搬送については補助金があるわけでもなく,保険点数が高いわけでもありません。この点がネックとなり,意義が高いとわかっていても人員を割けず,導入に二の足を踏む医療機関は多いと言...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川口 敦(かわぐち・あつし)氏 聖マリアンナ医科大学 小児科 特任教授
2003年阪大卒業後,神戸市立中央市民病院(現・神戸市立医療センター中央市民病院),倉敷中央病院で小児科,救急などの研修に励む。07年より静岡県立こども病院に勤務しPICUの立ち上げに携わり,その後10年度末からカナダ・アルバータ大Stollery Children’s HospitalでPICU臨床フェロー。同大公衆衛生大学院では搬送医学に関する研究で疫学博士号を取得する(文献1)。オタワ大 Children’s Hospital of Eastern Ontario小児科,小児集中治療学講師,モントリオール大CHU Sainte Justine研究所シニア研究員などを経て,22年より現職。
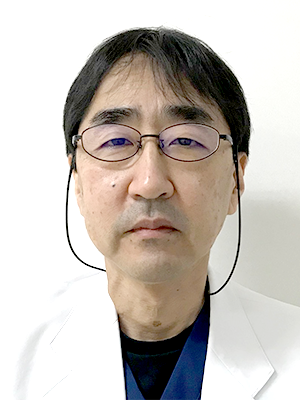
奈良 理(なら・さとし)氏 手稲渓仁会病院 救命救急センター センター長
1992年札医大卒業後,カナダ・アルバータ大に留学した期間を挟みながら,20年以上にわたって同大病院にて救急診療に携わる。2009年手稲渓仁会病院救命救急センター。15年より同センターセンター長。10年に立ち上がった北海道患者搬送固定翼機(メディカルウイング)運航事業では,メディカルディレクターを務める。

野澤 正寛(のざわ・まさひろ)氏 滋賀県立総合病院 救急科・小児科 科長
2005年滋賀医大卒。同大病院にて研修後,草津総合病院,済生会滋賀県病院,近江八幡市立総合医療センター,国立成育医療研究センター等で小児科,救急科の研鑽を積み,15年済生会滋賀県病院救命救急センター救急集中治療科,18年同院小児救命救急科。全国初となる小児救急システム「滋賀モデル」を始動させた。21年より現職。日本小児科学会小児救急集中治療委員会で搬送に関わる研究チームのチーフを務める。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
