関節リウマチ治療薬の費用対効果を検証する
寄稿 田中榮一
2023.02.20 週刊医学界新聞(通常号):第3506号より
日本人の約80万人が罹患しているとされる関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis:RA)は,全身の関節に慢性的な炎症が生じる,進行性の自己免疫疾患である。関節破壊の進行に伴って関節の変形が起こるなどで,身体機能が悪化すれば,QOLの低下を来す上,多大な社会経済的負担の原因となり得る。
近年,生物学的製剤やJAK阻害薬などの新規治療薬の導入や,治療戦略の進歩により,RAの臨床的寛解が現実的な治療目標となった一方,RA治療にかかる医療費の高騰は,患者のみならず重大な社会的負担ともなっている。本邦でも高騰する医療費の適正化を考える上で医療経済的評価は重要であるとの認識が広がりつつある。
高額な薬剤の医療経済的評価(費用対効果)の重要性
本邦において2023年1月現在,3種類のバイオシミラー(バイオ後続品)を除くと現在9種類の生物学的製剤が使用可能である。いずれの製剤も従来の抗リウマチ薬に比して著しく高価であり,RA患者の自己負担額(3割負担)は,多くの製剤で1か月当たり3万~4万円と,薬剤の費用のみでも高額である。RAに対し近年使用可能になったJAK阻害薬も1か月当たり4万2千~4万5千円と同様に高額である。これらの薬剤は医学的には大変有効性が高く,疾患活動性のみならず関節破壊や身体機能障害の進行を有意に抑制することが多くの国内外の臨床研究やコホート調査により示されているが,やはり費用対効果も検討しなければならない。
使用する薬剤の臨床的効果と経済的負担の両面を評価し,薬剤費用に見合った価値があるかどうかを分析することが薬剤経済評価である。欧州を中心に高額な薬剤や医療技術に対する経済的評価は医療政策の決定のためにすでに多く用いられており,特に英国の国立医療技術評価機構(National Institute for Health and care Excellence:NICE)では,薬剤経済評価の結果から,価格への反映や使用に際してのガイダンスを作成している。本邦においても,高額な薬剤や医療技術の増加による医療保険財政への影響についての懸念から,2016年4月に一部の高額な抗がん薬やC型肝炎治療薬に対する費用対効果評価の試行的導入が開始され,2019年4月より本格運用された。
本邦のRA治療における医療経済的評価の実際
RAのような慢性疾患の薬剤経済評価においては,主に費用効用分析(cost-utility analysis)が用いられる。この方法においては,評価対象の医療技術および比較対照の医療技術について,「費用」と「効果」を別々に積算する。この時に使用される概念がQALY(quality-adjusted life year:質調整生存年)であり,1QALY=「完全に健康な状態で過ごす1年間」である。そして1QALYを獲得するために必要な費用がICER(incremental cost-effectiveness ratio:増分費用効果費,新薬による増加費用/新薬による延長QALY)であり,わが国においてはICERが540万円以下であれば医療経済学的に許容し得ると判断されている1)。これらの費用効用分析を用いて,これまでにRAにおける生物学的製剤の費用対効果の評価が欧米を中心になされており,いくつかのレビューにまとめられている2, 3)。生物学的製剤の使用は,従来の抗リウマチ薬による治療と比較して,1 QALY当たりのICE...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
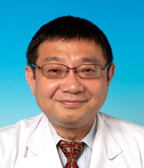
田中 榮一(たなか・えいいち)氏 東京女子医科大学医学部内科学講座膠原病リウマチ内科学分野 准教授
1994年滋賀医大医学部卒。同年,東京女子医大附属膠原病リウマチ痛風センターに入局。2005~08年米スタンフォード大に留学。18年より現職。主な研究分野は,関節リウマチのコホート調査および医療経済的検討。患者会である日本リウマチ友の会の理事も兼務する。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
