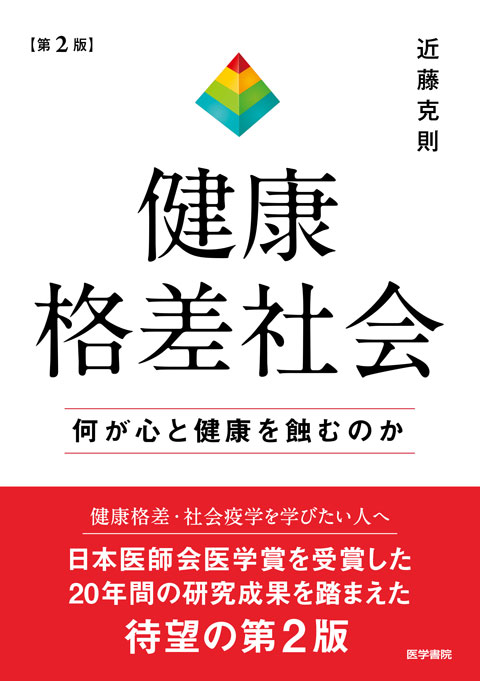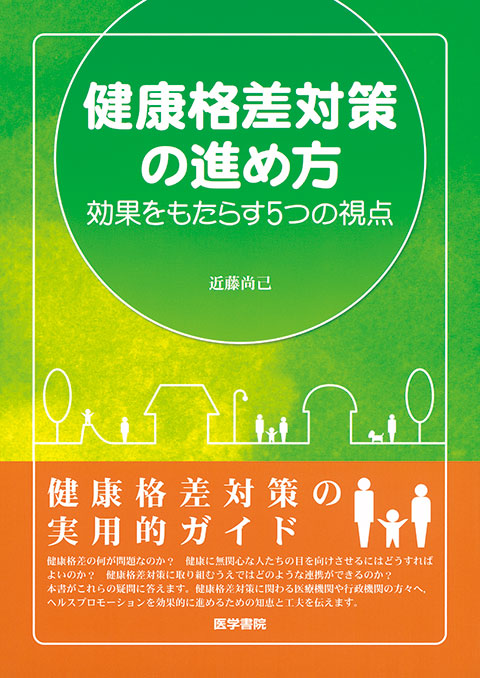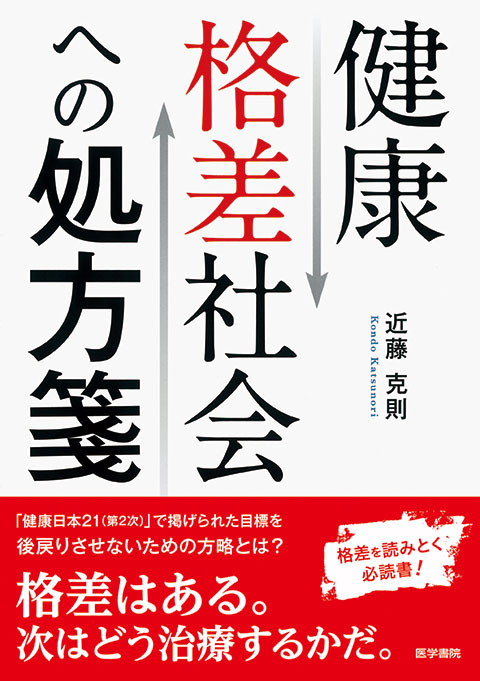「健康格差」の是正に向けて,いま医療者にできること
対談・座談会 近藤克則,近藤尚己
2022.08.22 週刊医学界新聞(通常号):第3482号より

2005年に『健康格差社会――何が心と健康を蝕むのか』(医学書院)を上梓し,「平等な国」という幻想が残る日本に存在する健康格差を俎上に載せ,警鐘を鳴らした近藤克則氏。同書が提起した「健康格差」「健康の社会的決定要因(SDH)」「ソーシャル・キャピタル」といった概念は,後に国の健康政策「健康日本21(第2次)」(2013年)や厚生労働白書(2014年),医学教育モデル・コア・カリキュラム(2016年)などにも登場するようになる。また,SDHを解明する「社会疫学」は,理論と実証を積み重ねながら着実に発展してきた。
このたび,近藤克則氏と共同研究を行い,『健康格差対策の進め方――効果をもたらす5つの視点』(医学書院)等の著作もある社会疫学者・近藤尚己氏を迎えた対談を企画。『健康格差社会 第2版』の出版を機に初版から第2版までの17年間の歩みを振り返るとともに,社会疫学者の立場から医療者への期待をお話しいただいた。
実証的なエビデンスが着実に積み上がった17年間
近藤尚 このたびは,『健康格差社会――何が心と健康を蝕むのか 第2版』の上梓おめでとうございます。
近藤克 ありがとうございます。
近藤尚 初版の出版から17年がたち,健康格差,社会疫学を巡る状況にはさまざまな変化がありました。初版を上梓した2005年当時,反応はどのようなものでしたか。
近藤克 積極的に応援してくれる声ももちろんありましたが,「重要な問題だけど,格差をなくすことは難しい」「医師の仕事ではないのでは」といった批判的,懐疑的なリアクションも多かったですね。海外では,公衆衛生で扱うべき問題との認識が一般的だったのですが。そうした状況の中で,健康格差の縮小に向けた取り組みを展開するのは,一筋縄ではいかないと思ったのを覚えています。
理解を示す先生からも,さまざまな要因が絡み合った根が深い問題だからこそ,健康格差の縮小は難しいのではないかとの声が聞かれました。それに対して私が思ったことは2つ。確かに根深い問題だから簡単にはいかない。しかし,だからといって放っておけない。
近藤尚 「看過できない」「見過ごせない」ということですね。
近藤克 ええ。そうした思いが根本にありました。同時に,何かやりようがあるはずだとの思いもあり,着目したのがソーシャル・キャピタルでした。コミュニティの構成員が,ネットワークに参加することで得られる相互の信頼感や互酬・互助意識,サポートなどの資源のことです。
近藤尚 ソーシャル・キャピタルに対しては批判がさまざまあって,醸成法や介入の仕方がわからないというのはその一つです。この17年間で,醸成法,介入法についてのエビデンスが相当積み上がったと思いますが,どのように受け止めていらっしゃいますか。
近藤克 直感的に「正しそうだ」と思った仮説が,少しずつ実証されてきた17年でした。例えば,愛知県武豊町での介入研究があります。誰もが通えるようにサロンを町内のあちこちに作り,参加者の身体活動量,社会サポート・ネットワークなどを増やして健康を増進する事業です。不健康になりがちな社会的背景を持つ人へアプローチするために知恵を絞りました。参加者は高齢者人口の1割を超え,最終的にはそうした社会参加が介護予防に資することを擬似的な無作為化対照比較研究と言われる方法で実証できました1)。
近藤尚 地域への介入のモデルケースとされる成功例は複数あり,それぞれに素晴らしい。中でも武豊町のプロジェクトはまさにその代表例だと思います。一方で,それらはあくまでもケーススタディですよね。知見としては大事だけど,それだけでは一般性が足りない。事例に含まれるエッセンスを数字で記述し検証する作業が必要です。
近藤克 そうですね。武豊町の事例も1つの町で行っただけなら,「たまたまでは?」という疑問・批判にさらされます。けれど,その後に尚己先生たちが複数の自治体を対象にしたデータ分析をして,介入市町村では社会参加者の増え方が多く,死亡率は低いこと,再現性と一般化可能性を示してくれました2, 3)。そうした地道な研究活動が蓄積された17年でした。
幸せに生を全うすることを支える医療
近藤尚 医療者に何ができるかを考えた時に,ソーシャル・キャピタルに注目したきっかけはあったのですか。
近藤克 ある50歳代の脳卒中患者さんの経験が印象に残っています。その患者さんは,脳卒中発症後1年半くらいで私のリハビリテーション科外来を訪れました。重度の右片麻痺と失語症があり,うつ状態で暗い顔をしていたんです。お子さんがまだ10代で,奥さんは「今後の生活はどうなってしまうのか」と途方に暮れていたそうです。薬と訓練だけでは状況の改善は難しいと私は考え,障害者とボランティアで電車を借り切って旅行に行く「ひまわり号」に誘いました。
近藤尚 私もひまわり号の活動に参加していました。今で言う社会的処方の一種ですね。
近藤克 はい。普段は車椅子で移動しているその患者さんも,旅先では自分の足で歩きたいと言い,実際に歩きだしました。日帰り旅行の夕方,駅が近づく電車の中で参加者が感想を一言ずつ伝え合う場面で,失語症の本人に代わって奥さんが「旅行になんて二度と行けないと諦めていました。でも,今日,旅行だってできるとわかりました。皆さんのおかげで,生きる希望が湧いてきました」と語ったのです。ボランティアや同じ障害を抱える者同士がつながる,いわばソーシャル・キャピ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

近藤 克則(こんどう・かつのり)氏 千葉大学予防医学センター 社会予防医学研究部門 教授/国立長寿医療研究センター 老年学評価研究部長
1983年千葉大医学部卒。船橋二和病院リハビリテーション科長などを経て,97年日福大助教授,2000年英ケント大カンタベリー校客員研究員。03年日福大教授などを経て,14年より現職。国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部長併任。『研究の育て方』『健康格差社会への処方箋』『健康格差社会――何が心と健康を蝕むのか 第2版』(いずれも医学書院)など著書多数。

近藤 尚己(こんどう・なおき)氏 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻国際保健学講座 社会疫学分野 教授
2000年山梨医大(当時)医学部卒。05年同大大学院博士課程修了。06年米ハーバード大公衆衛生大学院研究フェロー,10年山梨大大学院社会医学講座講師,12年東大大学院医学系研究科健康教育・社会学分野/保健社会行動学分野准教授などを経て,20年より現職。著書に『健康格差対策の進め方――効果をもたらす5つの視点』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。