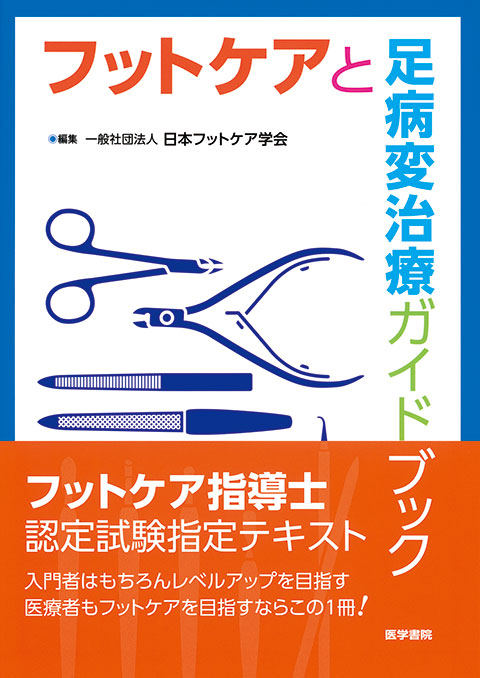フットヘルスを守るため
日本に足病医学を普及させる
対談・座談会 寺師 浩人,菊池 守
2022.08.01 週刊医学界新聞(通常号):第3480号より

足にかかわる疾患を総合的に診る足病医学をご存じだろうか? 米国では,足潰瘍や足部変形,巻き爪などの足の症状を専門的に診る専門医として「足病医(podiatrist)」が存在し,広く臨床現場で活躍している。患者のフットヘルスが維持されると運動量の減少が抑えられ,サルコペニアやフレイルの予防につながるからだ。すなわち,超高齢社会の日本では対象となる人々は多く,医師にとって足病医学の学習は必要不可欠と言えるだろう。しかし,その認知度は十分ではない。
今回,日本フットケア・足病医学会の理事長を務める寺師氏と,日本で唯一の「足と糖尿病の専門病院」である下北沢病院の院長・菊池氏の対談から,足病医学を根付かせるためのヒントを探っていきたい。
寺師 足病とは,日常生活に支障のある非健康的な下肢・足の状態を指します。背景には,形態的・機能的障害(循環障害・神経障害)や感染と付随する足病変があります。欧米には医学や歯学と同じように「足病医学」という学問が古くからあり,中でも米国足病医学会は100年以上の歴史を持ちます。米国では身近な存在として患者にも広く普及している一方で,日本での認知度は発展途上です。足の機能の維持が外出機会を増加させ,サルコペニアやフレイルを予防し心身の健康につながることから,より多くの医療者に足病医学を知ってほしいと私は考えています。
求められる足病のプライマリ・ケア体制
寺師 菊池先生が院長を務める下北沢病院は足病総合センターなどの外来を設ける,日本で唯一の「足と糖尿病の専門病院」ですよね。2016年に同院を開設されたそうですが,足病医学に関心を持つきっかけは何だったのでしょうか。
菊池 2012年に米国に留学した際に足病医(podiatrist)の診療を目の当たりにしたことです。留学先で見た足病診療がとても面白く,そこから足病医学を本格的に学び始めました。
寺師 留学先のpodiatristから何を感じましたか?
菊池 米国のpodiatristは日本のプライマリ・ケア医に近いということです。足潰瘍を診るのであれば,日本では形成外科や皮膚科が対応すると思いますが,米国ではpodiatristがまず診療に当たり,症状に応じて専門医にコンサルトするのが通常の医療体制になっています。「何となく体調が悪ければ内科」といった入口としての診療科があるように,足についても足病医という名のよろず相談窓口があればよいのですが,日本にはそのような医療機関が少ない。日本で家庭医が活躍している状況を考えると,プライマリ・ケアで足病を診る医師がいても良いのではと考えています。
寺師 同感です。足病を診る日本の医師はスペシャリストばかりで,プライマリ・ケアに従事する医師は多くありません。プライマリ・ケアで足病を診る医師が増えないと,結果として診療の質の向上につながりませんよね。
菊池 はい。例えば,高齢者の爪切りのケースにおいて,失敗して傷を作ってしまうのではとの恐怖から家族が爪切りを敬遠し,外来を受診する場合があります。一連の処置を終えるまでに30分程度を要しますが,これを全て専門機関で対応するのは現実的ではありません。高度医療を提供する専門機関,軽症の対応を行うプライマリ・ケア,そしてフットケアを行う民間の役割分担が重要なのです。
寺師 軽症のうちに介入しないと,疾患は重症化し,足を失う可能性すらあるでしょう。
菊池 ええ。巻き爪などはフットケアを行うセラピストが対応できることもあります。医療リソースを考える上では,患者を適切な場所に振り分けていくことが求められます。
診療の質の担保と足病医学の啓発を
寺師 足病のプライマリ・ケア体制を構築していくために,何か手はありますか。
菊池 早急な人材の育成です。そのためには多様な足病の症例を診られる研修機関,プライマリ・ケアを学べる場を増やすことが求められます。日本で足病医学がそこまで普及していない現状に鑑みると,一般病院やクリニックなどでどこまで安全性が担保された治療が行われているのかは専門機関から見えづらいです。足病診療を行える施設を増やすことと並行して,診療の質も担保する必要があるでしょう。
寺師 日本フットケア・足病医学会でも診療の質の担保には力を入れており,『重症化予防のための足病診療ガイドライン』が今夏に発行されることになりました。特定の診療科だけでなく,多科・多職種向けに作られた点が特長です。
菊池 今まで手探りで診療を進めていた医療機関も,ガイドラインが発刊されることでエビデンスに基づいた医療を提供できる可能性が広がるはずです。
寺師 菊池先生は足病診療の質の担保のために何か取り組まれていることはありますか。
菊池 2019年に初代理事長として「一般社団法人 足の番人」を設立しました1)。現在は理事長が変わっていますが,同法人では多くの医師に講師を依頼し,足病,フットケア,靴,歩行に関するセミナーを毎月開催して...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

寺師 浩人(てらし・ひろと)氏 神戸大学大学院医学研究科形成外科学 教授/日本フットケア・足病医学会 理事長
1986年大分医大(当時)を卒業後,同大病院で研修。97年米ミシガン大に留学後,2001年神戸大病院形成外科助教授,07年同大大学院医学研究科形成外科学准教授を経て,12年より現職。日本フットケア学会と日本下肢救済・足病学会が合併し,日本フットケア・足病医学会が設立された19年より同学会の理事長を務める。「日本版の足病医学を学会主導で確立していきたいです」。

菊池 守(きくち・まもる)氏 下北沢病院 院長
2000年阪大医学部を卒業後,同大形成外科学教室に入局。慢性創傷にかかわっていたものの,10年に神戸大で開催された第2回日本創傷外科学会総会・学術集会において,米国の形成外科医と足病医の連携についての講演を聴講し,衝撃を受ける。講演の演者が所属する米ジョージタウン大への留学(12年~)を契機に,本格的に足病医学を学び始める。13年佐賀大病院形成外科を経て,16年より日本初の足と糖尿病の専門病院である下北沢病院の病院長を務める。「足病医学の知見を当院から発信していきたいと思います」。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。