My Favorite Papers
無限に広がる論文の宇宙から自分だけの星を見つける
寄稿 巽 浩一郎,坂田 泰史,高橋 都,古川 壽亮,中村 清吾,田中 靖人
2022.05.23 週刊医学界新聞(通常号):第3470号より

日進月歩の医学の世界では,日々新しい論文が発表されています。それらを追いかけ続けることは果てしない道のりのように感じられるかもしれません。しかし,星の数ほどある論文の中から偶然出合った1編が価値観やキャリアに大きな影響を与えることもあれば,励まし,悩みを払拭してくれることもあるでしょう。
今回は,識者の方々にこれまでの医師・研究者としてのキャリアの中で出合った「印象深い論文」を紹介していただきました。読者の皆さんも,自身のキャリアを語るに当たって外せない論文をぜひ探してみてください。
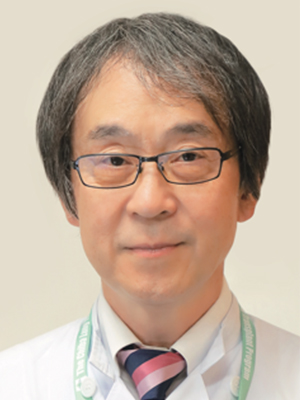
巽 浩一郎
千葉大学真菌医学研究センター
呼吸器生体制御解析
プロジェクト 特任教授
①Humbert M, et al. Cellular and molecular pathobiology of pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2004;43(12 Suppl S):13-24S.[PMID:15194174]
②Gross TJ, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2001;345(7):517-25.[PMID:11519507]
③Anderson GP. Endotyping asthma:new insights into key pathogenic mechanisms in a complex, heterogeneous disease. Lancet. 2008;372(9643):1107-19.[PMID:18805339]
「私のお気に入り(My Favorite Things)」は,1965年公開のミュージカル映画『サウンド・オブ・ミュージック』の挿入歌である。劇中のきれいな品々,美しい風景などに触発されて思わずご機嫌な気分になり,「私のお気に入り(My Favorite Things)」をつい口ずさみたくなるような経験。論文との出合いでもそうした経験がある。
紹介する3論文は私が国際学会に参加した際,世界の最先端を走る研究者が講演に引用していた論文である。講演拝聴後,該当論文を探し,手に入れて読む。まさに「読むことで道が開けた」「これがパラダイムシフトだ」と感じた。昨今,mRNAワクチンや分子標的治療薬は,テクノロジーの発展によりすさまじいスピードで開発が進んでいるが,通常,新しい作用機序の薬物開発には基礎研究から臨床開発まで20年ほどは必要であった。新規治療戦略の根底に流れる思索や研究者のたどった長い時間,深い探索の道を知ることのできる論文との出合い。思わず「私のお気に入り(My Favorite Things)」のメロディが浮かぶ,幸運な出合いである。
肺高血圧症の分野では,この10年くらいで新規の肺血管拡張薬の上市が一段落した。肺血管拡張薬開発前の患者予後不良であった暗黒時代,世界の研究者は肺高血圧症における肺血管の細胞・分子病態の研究から新規治療薬の開発をめざしていた。次に,低酸素性肺血管攣縮を中心に研究されていた時代から,肺血管収縮物質・肺血管拡張物質が肺血管の緊張に影響する時代,BMPR II遺伝子変異を含むTGFβ superfamilyが肺血管リモデリングに関与し得ることまで解明された時代に進んだ。①の論文中に記述されている,肺血管の緊張に関係し得る物質・分子を調節・制御可能と考えられる薬物が,現在は全て治療薬となり有効性が証明されている。
肺線維症に対し,現時点では抗線維化薬が開発され,治療薬として使用されている。抗線維化薬が開発される以前の時代,間質性肺炎のphenotypeは多種多様であり,どのように臨床分類,病理分類すれば病態・予後を区分けできるかが主な研究対象であった。何らかの外的刺激が慢性炎症を惹起し,組織傷害を招き,肺線維化に至ると考えられていた。治療薬としては慢性炎症を抑制する可能性のあるステロイド薬が試みられていた。一方現在は,ステロイド薬による治療は慢性安定期に益はなく,治療として勧められないとされている。②の論文では,抗線維化薬が開発されるはるか前の2001年に,特発性肺線維症について新規の発症仮説が提唱されている。繰り返す肺傷害は慢性炎症を起こす一方,傷害からの異常な創傷治癒過程が肺線維症につながるという仮説である。現時点ではこの仮説の下,抗線維化薬による治療が試みられている。2001年の段階で,現在の病態概念を先取って認識している論文である。
喘息の治療は気管支拡張薬のみの時代から,気道の抗炎症薬である吸入ステロイド(ICS)が開発され,喘息死の著減につながった。しかしICSの普及によっても完全寛解しない難治性喘息患者が残っている。では,なぜICSおよび経口ステロイド薬による治療に反応しない難治性喘息患者が存在するのか? ③は2008年の論文であるが,喘息は複雑な複合病態であり,遺伝的背景と同時に免疫系を含む病態分子を考慮する必要があると述べている。難治例では,ICSに反応し得る獲得性Th2免疫系の喘息病態への関与は弱まり,自然免疫系/T細胞に関係しないTh2反応/マクロファージ炎症などの関与が強まる。このような免疫系の反応と合致してICSの反応性が低下するという理論である。その後,Th2細胞でない自然リンパ球ILC2(group 2 innate lymphoid cell)の存在,そして難治性喘息病態への関与が証明され,分子標的治療薬の開発を経て現時点に至っている。
*
読者の先生方も論文との出合いを重ね,ぜひ自分だけの「私のお気に入り」を見つけていただきたい。
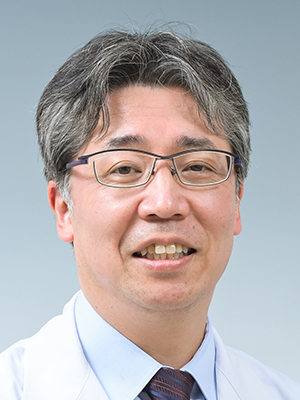
坂田 泰史
大阪大学大学院
医学系研究科
循環器内科学 教授
①Rahimtoola SH. The hibernating myocardium. Am Heart J. 1989;117(1): 211-21.[PMID:2783527]
②Molkentin JD, et al. A calcineurin-dependent transcriptional pathway for cardiac hypertrophy. Cell. 1998;93(2):215-28.[PMID:9568714]
③Yusuf S, et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and preserved left-ventricular ejection fraction: the CHARM-Preserved Trial. Lancet. 2003;362(9386):777-81.[PMID:13678871]
①の論文,Rahimtoola先生のThe hibernating myocardiumは,循環器内科の研修を始めた直後に読んだeditorialです。私は大阪警察病院にて循環器内科の研修を開始し,研鑽の後,心筋梗塞の患者さんの主治医を担当しました。その患者さんはいわゆる3枝病変で心不全を併発しており,左室造影でも動きが悪いのがわかりました。その時,この論文を通じて,心筋は「冬眠する」ことを知りました。バイパス手術後,見事に動き出した左室を見て,論文で言われていることが目の前の自分の患者さんに起こった点に深い感動を覚えたのを思い出します。同じ頃,心筋が「気絶する」ことも知り,実際に心筋梗塞後数日たつと動き出したのを初めて見た時も本当に感動しました。ただし,気絶心筋と違い,冬眠心筋は動物モデルでの再現ができません。このことは,臨床現場で患者さんを診ることの重要性を示していると思います。
その後,大阪大学大学院で,今で言うところの左室駆出率が保たれた心不全(HFpEF,当時は「拡張不全」と呼ばれていました)の研究を行いました。ダール食塩感受性高血圧ラットへの高食塩食投与の時期を調整することにより,臨床で見られるHFpEFモデルを確立し,心肥大の性質について調べていたところ,1998年,米国心臓協会の報告で,今までとは異なる心肥大の機序が見つかったということを知りました。それがMolkentin先生らがCellに掲載した②の論文です。カルシニューリンという,免疫に関係していると考えられていたリン酸化酵素が心肥大形成に関与しているとする論文の丁寧な論理展開,遺伝子改変動物を用いた証明,最後にカルシニューリン阻害薬であるシクロスポリンAによる肥大抑制に至るまでを一気に読み通し,一言「美しい」と思いました。この美しい論文を読んだ時,「自分も書きたい」という気持ちと,「こんな論文には,自分の力では至らないだろう」という気持ちとが入り交じったのを覚えています。残念ながら後者のほうが正しかったのは,私の力不足以外の何物でもありません。
それでも,動物モデルで研究を続け,「拡張不全」にはアンジオテンシン受容体拮抗薬が有効であるという結果を得て,論文に発表しました。動物実験はなかなか再現実験が難しいことが多いのですが,この薬剤は複数回同じプロトコルで試しても必ず同じような結果を示したので,有効性に自信を深めました。その頃,同じ薬剤がヒトのHFpEFで試されているのを知り,「おお,確かめてくれてるんだな」ぐらいのかなり上からの目線で結果を心待ちにしていました。それがLancet誌に発表された③のCHARM-Preserved試験です。残念ながら結果はfailureで,非常にがっかりしたのを覚えています。それまでHFpEFはわれわれのみならず,多くの研究者が心肥大や心筋線維化,そして拡張機能障害で説明しようとしていました。しかし,この研究の結果から,私もHFpEF患者さんの多様性を意識し始め,もう一度ヒトに目を向けるようになりました。
*
この中から,さらに一つだけ選べと言われれば,迷わずRahimtoola先生の論文①

高橋 都
NPO 法人日本がん
サバイバーシップネット
ワーク代表理事/内科医
①Kagawa-Singer M. Redefining health:living with cancer. Soc Sci Med. 1993...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
