難敵トキソプラズマ症に挑む
西川 義文氏に聞く
インタビュー 西川 義文
2022.03.21 週刊医学界新聞(通常号):第3462号より
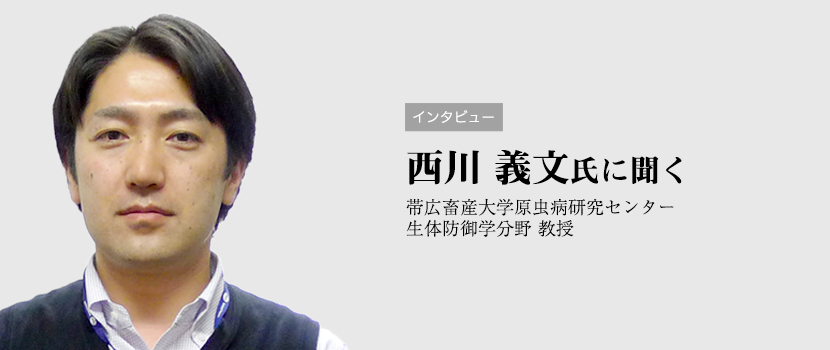
数多くの寄生虫のうち,ヒトにとって最も身近な存在の一つが体長5 μmほどの真核単細胞微生物,トキソプラズマ原虫(Toxoplasma gondii,写真)だ。ネコ糞便との接触や生肉の摂取等により経口感染するこの原虫の感染者数は世界人口の約3人に1人,日本でも約5人に1人に及ぶという。トキソプラズマ原虫は時に重篤な身体症状を宿主に引き起こし,近年では精神疾患との関連性も指摘されているが,いまだ有効な予防法・治療法は確立されていない。本紙では,トキソプラズマ原虫について約20年間研究を行ってきた西川氏に最新の研究動向と臨床への期待を聞いた。
巧みな戦略で宿主の免疫機構をジャック
――トキソプラズマ原虫(以下,トキソプラズマ)は,地球上およそ全ての恒温動物に寄生し,宿主特異性の低さは寄生虫内でも屈指です。ヒトの場合,感染するとどのような症状を呈するのですか?
西川 健康なヒトの場合は軽い風邪に似た症状が出るのみで,自分が感染していることに生涯気が付かないケースがほとんどです。しかし,感染によって引き起こされるトキソプラズマ症は日和見感染症の一つであり,HIV感染や臓器移植により免疫不全状態となると,重篤な脳炎や網膜炎,心筋炎などを発症します。また妊娠中に新規感染した場合には自然流産や死産,あるいは網脈絡膜炎,脳内石灰化,水頭症などを主徴とする先天性トキソプラズマ症を胎児に引き起こす場合があり,注意が必要です。
――健康状態が良好であれば感染を過度に恐れる必要はないのでしょうか。
西川 そうとも言い切れません。なぜなら近年では,自殺率1)や統合失調症の有病率2, 3)といった精神・神経症状を呈する割合と,トキソプラズマ感染歴との相関が複数報告されているからです。すなわち寄生されれば身体的には無症状でも,その脅威にさらされる可能性があると言えます。ヒトでのメカニズムは明らかになっていませんが,マウスやラットを使った研究では,宿主の脳細胞に寄生してドーパミン,セロトニンといった神経伝達物質やホルモンの分泌量を制御し,終宿主であるネコ科動物にたどり着きやすいように現宿主の行動変化を引き起こす4, 5)と考えられています。
――ウイルスや細菌などほとんどの異物は宿主の免疫機構で排除されるはずです。なぜトキソプラズマは宿主の生体内で生き続けられるのでしょう。
西川 理由の一つは,宿主のリンパ球に寄生するためです。トキソプラズマは赤血球以外のあらゆる細胞に対して寄生能を持ち,本来異物を攻撃するはずの免疫細胞も例外ではありません。宿主の免疫機構を乗っ取り血流に乗って体内を移動するトキソプラズマは,筋肉や胎盤,眼,脳などあらゆる臓器に感染し,潜伏します。そして宿主の免疫力が低下すると内部から一気に奇襲を仕掛ける。あるいは,脳から宿主の精神や行動をコントロールするかのような動きを取る。その戦略は,しばしばギリシア神話の“トロイアの木馬”に例えられるほど巧妙なのです。
“トロイアの木馬”の罠に落ちないための方法は
――現在,トキソプラズマ症に有効な予防法や治療法は確立しているのでしょうか。
西川 ヒト用のワクチンは開発されておらず,十分に加熱した肉を食べるなど日常生活で自衛するほか予防する術はありません。また,治療はサルファ剤やピリメタミン,スピラマイシンなどの薬剤投与が一般的です。これらの薬剤は,動物細胞が生存する上で欠かせない代謝経路やタンパク質合成系を阻害します。しかし,選択毒性が低いため宿主の細胞にもダメージを与え,骨髄抑制や血液障害等の副作用が懸念されていま...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

西川 義文(にしかわ・よしふみ)氏 帯広畜産大学原虫病研究センター生体防御学分野 教授
1996年東京理科大基礎工学部卒。2001年東大大学院修了。博士(農学)。米イェール大医学部日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て,18年より現職。トキソプラズマ症をはじめとする原虫感染症の病態メカニズムの解明,創薬,ワクチンおよび診断系の開発を目標に研究を続ける。「寄生虫学は未開の部分が多く,治療法の開発も発展途上です。だからこそ研究の意義と面白さに溢れています」。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
