新春随想
寄稿 吉新 通康,大津 欣也,玉城 和光,伊原 和人,河北 博文,石川 賀代,水方 智子,西島 正弘,塚田(哲翁) 弥生,仲間 知穂,大内田 美沙紀,藤田 千代子
2022.01.03 週刊医学界新聞(通常号):第3451号より
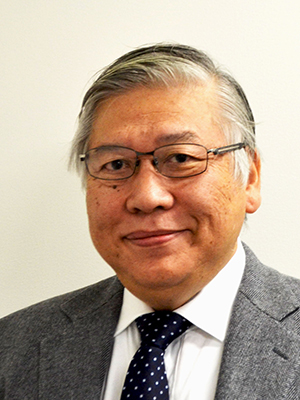
自治医大創立50年と地域医療の歩み
吉新 通康
公益社団法人 地域医療振興協会 理事長
本年は自治医大が創立して50年。自治医大の卒業生が中心となって設立した地域医療振興協会も36周年を迎えた。
1979年,1期生が初期研修の2年目を終え,翌春にはいよいよ地域に出るころ,自治医大の1,2期生100人ほどの卒業生が集まる同窓会で,当時の全国自治体病院協議会会長の諸橋芳夫先生があいさつされた。「自治体の悲願でできた自治医大。これからの君たちの頑張りで本学の評価が決まる。頑張ってほしい」とへき地医療に新たに取り組む卒業生を激励された。
自治医大の仕組みとして,都道府県単位で選抜入試が行われ,入学後は全寮制で6年間,仲間と起居を共にする。そして卒業と同時に母校を離れて出身都道府県に戻り,義務年限9年間(その半分はへき地)を知事の指定する施設で勤務すれば,学費は返済免除になる。へき地に行くかどうか心配した者もいたが,93%が義務を果たしている。
入学してほぼ50年たった昨年,100人の1期生全員に自治医大の仕組みについてアンケート調査を実施した。89人と予想を上回る回答があり,うち95%が「へき地を含む義務年限内の勤務」に満足していた。義務年限の勤務で良かった点として「幅広い医療の経験ができた」「地域住民・団体の中に知己を得た」,そして「職場の同僚」を挙げていた。1期生の6割は,「医学部に再び入学するなら,また自治医大に入学する」と答えた。全寮制にも,教員にも,同窓生にも皆満足で,高い評価を得ていた。緊密な人間関係が自治医大の基礎になっていることがわかる。
今,へき地勤務の義務年限を過ぎても3割がへき地に勤務している。へき地医療は,個人の頑張りから「へき地医療のシステム化へ」の流れができつつある。へき地と言っても,研修システム,インターネット環境,道路事情などの改善で,50年前とは状況が全く異なる。流行や情報に遅れがあるようなへき地はもうない。
少子高齢化,過疎化が一段と進み,常勤医師の診療所は,出張診療所になったり,合併や統廃合が進んだりしている。これは,へき地・離島だけではない。その手前の地方都市でも,似たような現象が至る所で起こっている。かつての商店街は閉じ,患者さんを紹介した病院もない。
へき地から見ると「国全体が,確実に小さくなっている」。

循環器病克服への期待
大津 欣也
国立循環器病研究センター 理事長
国立循環器病研究センター(以下,国循)は,循環器疾患の究明と制圧をめざして設立された国立高度専門医療研究センターである。対象疾患は,脳・心臓循環器疾患に特化し,その予防や診断,治療法の開発,病態生理の解明を推し進めている。1つの建物に病院,研究所およびオープンイノベーションセンターの3つの機関が入る,世界レベルの医療研究機関である。周辺には,吹田市民病院,大規模マンション,高齢者向け住宅,企業や国立健康・栄養研究所が建設予定のイノベーションパークなどがあり,一帯は,北大阪健康医療都市(健都)と呼ばれ,医療クラスターの形成をめざしている。
国循の対象疾患である脳卒中や心臓病などの循環器疾患は,不適正な生活習慣や生活習慣病による発症,脳梗塞,心筋梗塞などの突発的な発症や重症化,合併症の発症,徐々に進行する慢性期,繰り返す急性増悪が幅広い年代に存在し,かつ長い経過をたどる。循環器疾患は年齢によって増加するため,これからの高齢化社会においてはさらに増加することが予想される。主要な死亡原因であるとともに医療費に占める割合も最多である。また介護が必要となる主な原因であり平均寿命と健康寿命との乖離の大きな要因である。
循環器疾患診療には,急性期患者搬送体制の不備や急性期から慢性期へのシームレスな医療体制の不備,チーム医療を行うための人材不足,全国規模の疾病登録事業の不備,国民への教育・周知不足などの問題がある。さらには循環器疾患に対する原因治療が欠如している。
これらの諸問題に対応するため,2018年12月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中,心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が成立した。この法律により,義務教育における予防教育や市民への啓発や循環器疾患予防を目的とした健診システムの構築による発症抑制をめざす。そして救急受診を促す市民啓発,医療機関のネットワーク作成,遠隔医療の活用による再灌流療法や緊急手術が受けられる急性期医療の充実を促進する。さらにリハビリテーションや在宅医療,介護,社会支援の充実による慢性期医療の充実,また登録事業による医療の質を評価する体制を構築すること。それらによる高齢者医療費の削減,さらには人材育成や臨床・基礎研究の強化などにより循環器病の克服への道が加速することが期待される。

しなやかで,たくましい医療提供体制実現に向けた一歩の年に
伊原 和人
厚生労働省医政局長
国内で2020年初めから始まった新型コロナウイルス感染症との闘いは,ついに3年目に入ろうとしています。この間,医療現場の最前線で保健・医療従事者の方々が懸命に奮闘されてきたこと,感謝の念に堪えません。「医療崩壊」などと言われる厳しい状況の中,患者さんのために全力を尽くされる姿に,多くの人々が心を動かされ,医療の大切さを改めて身近に感じたと思います。実際,欧米諸国と比べても格段に低い感染率や死亡率は,感染防止に向けた国民の理解と協力と共に,こうした保健・医療従事者の方々のご尽力によるものだと感じています。
幸いにも昨年後半に入り,短期間に効果の高いワクチンが普及し,中和抗体薬など新たな治療手段を手にできました。何より今は,昨年末に取りまとめた保健・医療提供体制確保計画の実行など,さらなる感染拡大への備えに万全を期したいと考えています。
他方,これまでのコロナ対応を振り返ると,わが国の保健・医療提供体制をめぐるさまざまな課題が浮き彫りになりました。「日本の感染者数は欧米に比べはるかに少なく,人口当たりの病床数は多いのに,なぜ病床ひっ迫が起こるのか」など,政策担当者にとって耳の痛い指摘も数多くあります。
近い将来,次の新興感染症の襲来リスクが決して低いとは言えません。今回得られた教訓を基に,いざという時の人材確保,地域における医療機関の役割分担と連携強化など,保健・医療提供体制を見直し,次に備えることが必要だと感じています。同時にこうした備えは,2040年頃を見据えた時に,担い手不足等のさまざまな問題に直面している日本の医療現場の課題解決にもつながるものと思います。
今回の経験を次につなげていくために,2022年が,いざという時に頼りになる「しなやかで,たくましい」医療提供体制の実現に向けた一歩になればと願っています。

沖縄の本土復帰50年 医療制度の激変を乗り越えて
玉城 和光
沖縄県立中部病院 病院長
今年は沖縄が本土に復帰して50年目に当たる。医療においては,1972年5月15日を境に本土の現物給付制保険が導入された。激変緩和措置もない,いきなりの移行で沖縄の医療は大混乱に陥った。この復帰前後の激動を,患者側と医療者側両方の視点から私の知る限りで述べてみたい。
本土復帰後,患者側にとっては,診察後帰る時に窓口で診療費の3割分を支払うだけになり,相当楽になったと言える。大変だったこれまでを簡単に振り返ると,沖縄戦で医療は完全に崩壊し,その後は実質上の無保険状態が続く。1965年に現金給付制保険が制定されるが,これは受診した患者が医療機関の窓口で診療料金全額を支払い,診療料金受取証書を受領する。証書に給付申請書を添えて保険事務所に提出。さらにそこで診療料金受取証書に記された個々の診療行為を算定基準に照らして算出し,その額の7割が給付額として患者に支払われるというものであった。当時はバスなどの公共交通機関も十分整備されておらず,多くの患者が保険事務所まで出向けずに還付を受けられなかったと聞いている。
医療者側にとっては,これまで診療料金全額が毎日入っていたのが,2か月以上経ってからしか入らなくなり,諸経費等の支払いが大変になった。その上,診療報酬の大部分は診療月の初日から末日までの1か月分を翌月の10日までに診療報酬請求書として社会保険診療報酬支払基金に提出,さらにそこで請求書の診療内容の適否を審査した上で診療報酬が支払われるなど事務作業も複雑化した。
疾病を長く抱えながらも医者へかかれずにいた患者(潜在的疾患を抱えた患者)が,気軽に受診可能になったことで多く掘り起こされ,ただでさえ少ない医療機関に殺到し,そこに慣れない事務作業が追い打ちをかけた。これらの負担増加で,これまで輪番制で行っていた夜間救急診療を断る医療機関が続出。ついには当院が本島で救急を受け入れる唯一の施設となってしまう。当院はまさに野戦病院と化し,夜間は200人以上の受診が当たり前,緊急手術の連続で予定手術が夜中から始まるというのも日常茶飯事,あまりに厳しい勤務で看護師の約3分の1が退職する等,本当に凄まじいものであった。
その困難を全職員が協力して乗り切った。このことで,“当院は救急医療の最後の砦であり,救急患者は決して断らない”という認識が全職員の心に刻み込まれ,その姿勢は現在に至るまで変わらぬ伝統となったのである。

「公」「私」・「官」「民」を意識した改革を
河北 博文
社会医療法人 河北医療財団 理事長
公益財団法人日本医療機能評価機構 代表理事 理事長
「公」「私」「官」「民」はよく混同して用いられる言葉ですが,整理して考えなければなりません。「公」「私」は気持ちの持ちよう,あるいはその立場での事柄・事態のことを指します。Public mindとpersonal mind,public matterとpersonal matterという使い方をします。一方,「官」「民」は運営主体を指したものでgovernment sectorとprivate sectorのことです。
日本は明治維新以降,多くの「公」が「官」によって運営されてきました。しかし,日本国有鉄道がJRに民営化され,日本電信電話公社がNTTになったように,多くの社会インフラを含めて「公」は「民」でも運営できるのです。軍隊や警察は難しいかもしれませんが,「公」のほとんど全ては「民」によって運営できると思っています。社会保障においても全てを「官」が担う必要はないと考えています。
わが国は「貧しい国日本」になりつつあり,多くの経済指標がそれを物語っています。それにもかかわらず,政治は自らの立場を擁護することだけにこだわり,行政は前例を踏襲し,“お上”意識がいまだに全く抜けていません。一方,民間と私人は行政に対しての依存心が極めて高く,社会を牽引する気概が見られません。
今日,話題になっている渋沢栄一は,明治初期にこれらのことを見透かし,民間の立場で社会作りを進めました。戦後,鈴木善幸内閣に始まり中曽根康弘内閣まで続いた土光臨調,そして小倉昌男氏の「クロネコヤマトの宅急便」が,まさにこの公私・官民の在り方を強く意識した変革を実現してきたわけです。
医療も例外ではありません。将来「官」の立場だけで政策を進めれば,財政は破綻するでしょう。ぜひ,これからの社会保障政策,社会保険制度に民間の立場を大いに反映させなければならないと考えています。
本稿をお読みの方にも,医療における「公」「私」「官」「民」の在り方を考えていただきたいと強く思います。
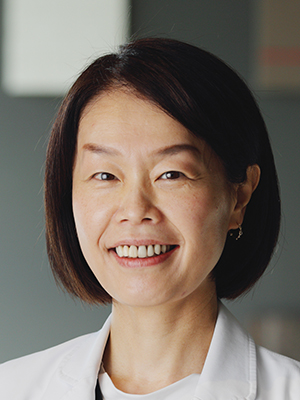
未来を見据えた病院DXの推進に今こそチャレンジ
石川 賀代
社会医療法人石川記念会HITO病院 理事長
石川ヘルスケアグループ 総院長
日本の置かれた急激な社会構造の変化の中で,地域に必要とされる医療機能を維持し,少子高齢化に伴う働き手不足をマイナスのイメージからプラスへと転換していくためには,テクノロジーの活用が必須である。人口構造においても高齢者の割合が増加し,高齢者特有のmultimorbidity(マルチモビディティ)に対応するために,多職種協働のチーム医療が必要となる。2024年から医師の働き方改革が実装される中で,当院では医療の質を担保し,かつ業務の効率化の両立を図っていくために,5年前からICTの利活用を推進してきた。
病院でデジタル化が進まない背景として,いくつかの要因が挙げられる。無線LANなどの環境整備における課題,導入と維持のコスト,IT人材の確保などである。また,デジタル化を開始する時点でのシステム構築への完璧主義も物事が進まなくなる要因であると考えている。
加えて,病院運営の中で,医師の指示の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
