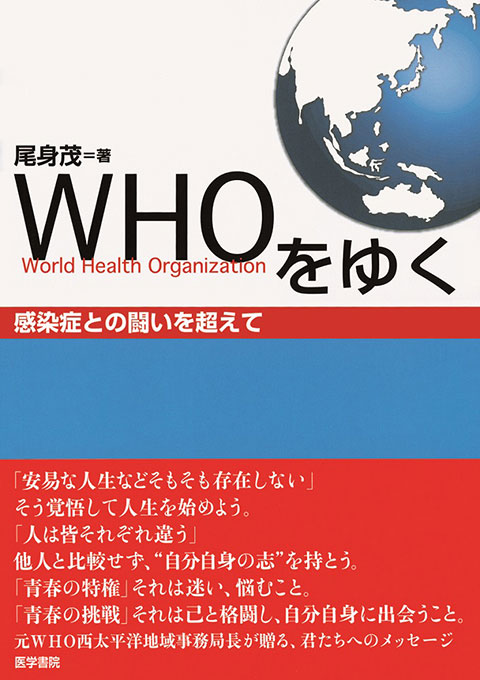- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2021年
- 医学界新聞プラス [第1回]WHOに至るまで:第1の青春物語
医学界新聞プラス
[第1回]WHOに至るまで:第1の青春物語
『WHOをゆく――感染症との闘いを超えて』より
連載 尾身茂
2021.06.25
WHOをゆく――感染症との闘いを超えて
著者の尾身茂氏は現在,政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長として感染症の収束に向け尽力する。困難に立ち向かう覚悟と原動力はどこから湧き出るのか。WHO西太平洋地域事務局で同地域のポリオ根絶に貢献し,事務局長時代にはSARS対策で陣頭指揮を取った経験が,今まさに直面する感染症危機管理のリーダーシップにも一貫する。感染症と闘い続ける尾身氏が若者に向けて著した『WHOをゆく』のうち,自身の「得手」を探し求めた「青春物語」を3回に分けて公開する。
「これからの長い人生において,様々な困難,挫折,悲哀に遭遇するであろう。しかし,君たちには,人生の最後に『自分の人生は厳しかったが,十分堪能することができた』と言えるような生き方をしてほしい」――(「第11章 若者へのメッセージ」より)。
WHOに至るまで
医師を目指す動機は人によって様々だと思う.身近に医療関係者がいて影響を受ける人,また家族や自らの闘病が契機になる人もあるだろう.しかし,私の場合は中学・高校を通して,医学・医療を自分の将来の仕事として考えたことは皆無だった.学校でも理科は苦手で文化系の科目に相性がよく,また生徒会活動や剣道など,人と話したり,体を動かすことが好きだった.したがって将来の職業としては,世界を飛び回る外交官や商社マン等を漠然と考えていた.
是非ともアメリカに留学してみたかったが,当時は高校生の海外旅行など,考えられなかった時代である.しかし,たまたま,American Field Service(AFS)という留学制度があり高校生でもアメリカで勉強する機会があることを知り,柄にもなく教会の英語バイブル教室にも通い,英語だけは懸命に勉強した.
2回目の挑戦で幸いにもAFSの留学試験に合格した.カナダにほど近いニューヨーク州ポツダムという町で,インド文化を専攻するドイツ系アメリカ人の大学教授の家に1年間寄宿し,現地の高校に通う機会を得た.当時,1960年代半ばといえば,古き良きアメリカの最後の時期.まだ1ドルが360円の時代で,彼我の国力の差は歴然としていた.大きな庭の芝生,各家に2台の自家用車といった,それまで映画で垣間見るだけだったアメリカでの毎日は鮮烈だった.日本のように大学受験を意識することもなく,郊外の湖で生まれて初めてヨットを楽しみ,また,テニスに熱中,時にはデートにも成功した日々は,今でも「天然色」で記憶に残っている.

さて,1968年に帰国してみれば,待ち受けていたのは灰色の世界だった.日本中が,学園紛争で騒然としていた.例えば安田講堂が占拠された東京大学は,1969年の入試が中止になったほどだった.その年に私は慶應義塾大学(法学部)に入学した.その慶應義塾大学でもストライキに入った.反権力,反体制が声高に叫ばれる中,「商社マンや外交官志望」などと口にすれば,「人民の敵」と言われかねない雰囲気であった.青春の彷徨の始まりである.
ゲバ棒を持ってデモに参加するという気分にもなれず,さりとて「ノンポリ」に徹して勉学に打ち込むこともできず,徐々に大学に通う回数が減り,通学途中渋谷で下車して,ある書店に入り浸り,哲学,宗教,人生論などの本を漁る日々が多くなっていった.
そんなある日,件の書店でぶらぶらしていると,ふと『わが歩みし精神医学の道』(内村祐之著)という1冊が目にとまった.医学など夢想だにしなかった私だったが,悩む青春の心には“医学”という言葉が何か人間的な響きを持ち,自分の悩みを一挙に解決してくれる救世主に思えた.医学部受験を密かに決心し,両親に話すと,普段おとなしい父親は激怒,文字通り取っ組み合いとなった.何とか母の仲裁で勘当は免れた.医学部合格の確信のないまま医師を目指すこととなった.勉強を始めて数か月後,自治医科大学という地域医療に従事する医師を育てる大学が創設され,翌春1期生を募集することを知った.「地域医療」という言葉の響きは,悩む心には魅力的だった.しかも学費は無料だという.両親にこれ以上経済的に迷惑をかけるわけにはいかなかった.第一志望を自治医科大学と決めた.食事,睡眠,トイレ以外の時間はすべて勉強,後にも先にもあれほど懸命に勉強したことはなかった.
二度目の転機は30代後半に訪れた.卒業後に都立病院で研修した後,伊豆諸島の離島での診療をはじめとする自治医科大学卒業生としての就業義務も終わりにさしかかり,人生の後半の生き方を考える時期に来ていた.僻地医療にまた戻るか,都立病院で専門医を目指すか,開業するか,都の保健医療行政に従事するか,いくつかの選択肢があった.


そんな時,偶然,高校時代に共にアメリカに留学した仲間に会う機会があった.彼は当時UNICEFで仕事をしていた.たまたま赴任地のインドネシアから東京に一時帰国した際に電話をくれたのである.彼は高校の頃の私を想い出しながら言った.「尾身,WHOで働いたらどうだ」.
そのまま,ものに憑かれたようにWHOへ突き進むことになる.家族の迷惑も省みず,私の身勝手な決断だった.早速取り寄せたWHO関係の資料によれば,WHOへの就職には高度の専門性が必要とのことだったので,母校,自治医科大学の真弓忠教授のご厚意で,B型肝炎の分子生物学の研究に取り組むことになった.試験管を振る日々が続いたが,不得手の分野だったので,この時期,不整脈が頻発した.真弓先生,岡本宏明先生(現自治医科大学教授)のご指導のお陰で,博士号を取得した.その後真弓先生のアドバイスで厚生省(当時)へ就職した.ここで役立ったのは,医学部学生時代に入れ込んだマージャンである.人数合わせに駆り出されることがしばしばあった.「リーチ」をかける度に,幹部に「WHOへ派遣してください」と訴えた.
これが実ったのか,ほどなくWHOの選抜試験を受ける機会を得,合格した.こうしてWHO西太平洋地域事務局(以下WPRO)での仕事が始まり,それからはや15年,今日に至る(注:2004年4月執筆時).
振り返ってみれば,高校を1年留年しての留学,法学から医学への転向,都立病院での診療,離島での僻地医療,基礎医学研究,厚生省での行政と,随分回り道をしてきたようだ.当初志した外交官や商社マンにはならなかったが,結局は巡りめぐって同じような仕事をしていると言えるかもしれない.WHOの仕事は,後述するSARSなど感染対策における各国政府との交渉など,外交の要素を持っている.また,人と人,情報と情報,モノとモノの橋渡しをするという意味では,商社マンの仕事と異なるところはない.
最近は若い人たちから,「WHOで働きたいのですが」と相談を受けることもよくある.例えば,笹川記念保健協力財団は毎年10人あまりの学生をWHOに研修に送って来るが,WHOに関心を持つ若者が必ず何人かいる.そうした際に自らを振り返って説くのは,“自分の本当に好きなことを見出す大切さ”である.人道や博愛に対する熱い想いのみでは,数日・数か月は頑張れても,数十年のキャリアを勤め上げることはとてもおぼつかない.自分の能力は何処に向いているのか,自分は何が得意なのか,何が好きなのかを突き詰めて考える“自分探し”の過程が必要である.
私が若かった頃には,好むと好まざるとにかかわらず,そうせざるを得ない時代の雰囲気があった.「人生をまじめに語る」ことに気恥ずかしさを感じる時代風潮の中で,若者が自分の人生を突き詰めて考えることは容易ではないが,自分探しの旅は,今の時代でも大切ではないかと思う.
(第2回につづく)
「週刊医学界新聞」(第2952号 2011年11月7日)のインタビュー記事もご覧ください。
〔シリーズ〕 この先生に会いたい!! 悩み,失敗して“個性”を獲得する医師の道を歩んでほしい(尾身茂,渡邊稔之)
WHOをゆく――感染症との闘いを超えて
WHOで感染症と闘い続けた尾身茂氏が語る奮闘記
<内容紹介>著者の尾身茂氏は、WHOアジア西太平洋地域における小児麻痺(ポリオ)根絶の立役者。また21世紀最初の公衆衛生の危機となったSARS対策でも陣頭指揮をとり、日本に戻ってからは新型インフルエンザ対策で活躍した。『公衆衛生』誌の連載をもとにした本書であるが、3.11後の医療・社会について加筆されている。本書は、まさに感染症と闘い続けた尾身氏の奮闘記。志とは? 覚悟とは? 己との格闘とは? 自ら道を拓こうと欲する、若者に贈る。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
サルコペニアの予防・早期介入をめざして
AWGS2025が示す新基準と現場での実践アプローチ寄稿 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療を楽しく知る・学ぶ社会をめざして
おもちゃAED「トイこころ」開発への思い
坂野 恭介氏に聞くインタビュー 2026.03.10
-
寄稿 2026.03.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。