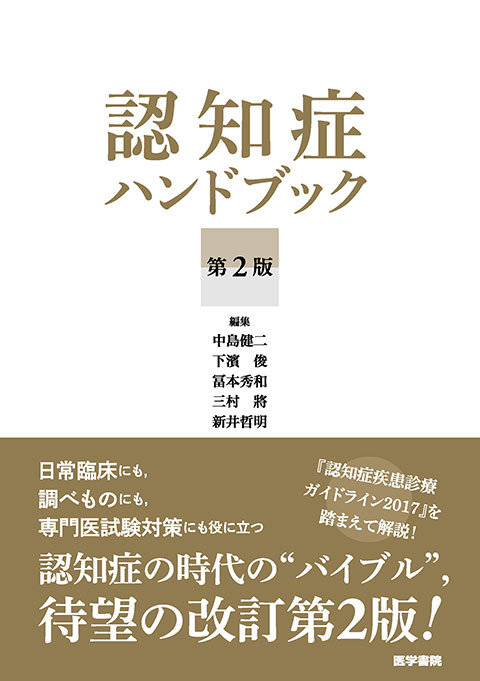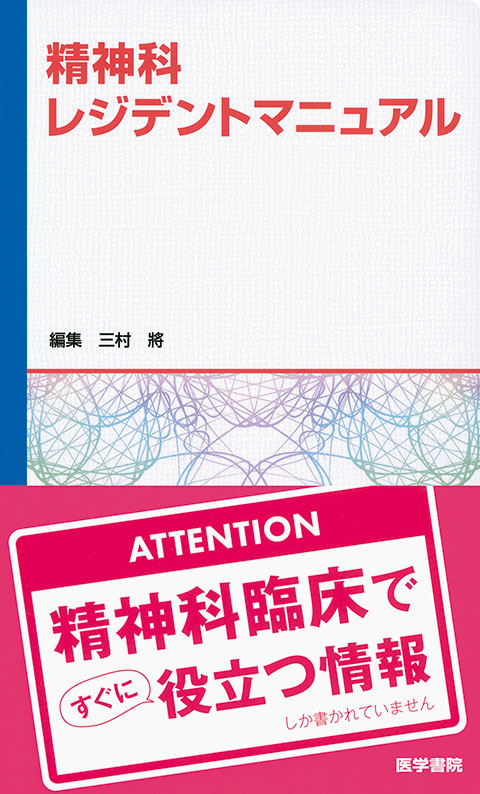ニューロサイエンスは刑事司法に何をもたらすか
寄稿 村松 太郎
2021.09.20 週刊医学界新聞(通常号):第3437号より
裁判所に課せられた「意思決定を証明する」という本来的に不可能な作業
心理現象が脳の活動の現れであるのなら,脳を調べることによって心理現象を説明することができるはずである。
そこに刑事司法が注目している。なぜなら,裁判所が有罪・無罪の判決を下すためには,被告人の心理を証明しなければならないからである。刑法38条には「罪を犯す意思がない行為は,罰しない」,刑法39条には「心神喪失者の行為は,罰しない」と記されている。どちらも本人の意思にかかわる記載であり,「意思決定を証明する」という本来は不可能な作業が裁判所には課せられている。脳を通して被告人の心理状態を証明することができれば,刑事裁判の精度は格段に増す。裁判所が脳に注目するのは当然であると言えよう。
法廷へのニューロサイエンスの導入が加速している
しかしながら脳の所見は,心理現象を説明することはできても,証明することはできない。そもそも医学でエビデンスと呼ばれているものはグループデータにすぎず,特定の個人の特定の行為に適用することは困難である。ましてや被告人の犯行時の意思決定を正確に判定することは不可能だ。それでも,法廷へのニューロサイエンスの導入は加速している。裁判が争いであるという事情も,この加速を助長している。弁護側も検察側も,自分の側に有利な「科学的」データがあれば,積極的に法廷に提...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

村松 太郎(むらまつ・たろう)氏 慶應義塾大学医学部精神・神経科 准教授
1983年慶大医学部卒。博士(医学)。同大にて研修後,米NIH Visiting Fellow,国立療養所久里浜病院精神科医長,慶大医学部精神・神経科専任講師などを経て2008年より現職。『精神科レジデントマニュアル』『認知症ハンドブック(第2版)』(いずれも医学書院)を分担執筆。その他,著書多数。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。