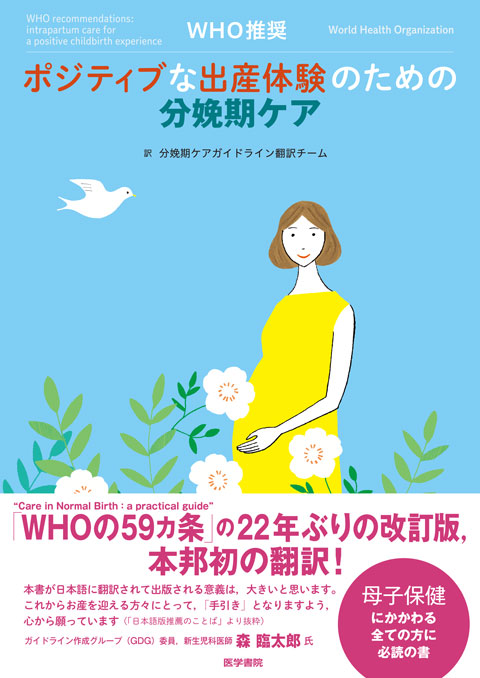WHOの推奨から学ぶエビデンスに基づく分娩期ケア
寄稿 永井 真理
2021.06.07 週刊医学界新聞(通常号):第3423号より
「エビデンスに基づく医療」という言葉は広く使われているが,一つひとつの医療行為がどの程度のエビデンスに基づいているのか,疑問に思ったことはないだろうか。そんな時に参考になるのが,世界保健機関(WHO)が公開している推奨である。
エビデンスと実践に基づいた推奨はどのように作られているのか?
WHOからは感染症を含むさまざまな疾患に関し,予防から治療まで,数多くの推奨が公開されている。2007年以降,これら全ての推奨は,WHOガイドライン作成の手引き1)(約300ページ)に定められている手順に厳格に従って,利益相反のない外部の臨床家や研究者たちが医療行為の要・不要を検証することで作られている。
まず,臨床上の重要な問題を同定する。その問題一つひとつに対し,どのような状態の人がどのような医療行為を受け,何と比較して,どのような結果であったか,世界中の研究データの系統的レビューを行う。さらに,その医療行為に必要なリソース,費用対効果,公正性(患者間の格差助長につながらないか)なども検討する。
数年がかりでこれらの過程を経て,1つの医療行為に対し,1~2文による「推奨項目 Recommendation(要・不要)」が作成される。また,それを補完する「注釈 Remarks」も非常に重要で,この2つはセットで読まれることが想定されている。最後に,やはり第三者組織であるガイドラインレビュー委員会がその質を厳密にチェックしたのち,WHOから出版される。
女性が「ポジティブな出産体験」の機会を得られるための分娩期ケア
そのようにして出版された推奨集の1つが,今回和訳された『WHO推奨 ポジティブな出産体験のための分娩期ケア』(医学書院)である。妊娠・出産と新生児に対するさまざまな医療行為のエビデンスを検証した一連のWHOガイドラインの一冊で,原著2)は2018年に出版された。特徴的なのは,「ポジティブな出産体験のための」とのタイトルが示す通り,出産する女性自身がその医療行為をどうとらえたかも検証した点である。女性および新生児の生命を最重要アウトカムとしつつ,その医療行為は女性にとって喜ばしい体験となるのか,と...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

永井 真理(ながい・まり)氏 国立国際医療研究センター国際医療協力局専門職
1992年東北大医学部卒。国境なき医師団などで紛争地の医療活動後,2004年米ジョンズホプキンス公衆衛生大学院修士課程修了。博士(医学)。15年よりWHO西太平洋地域事務局に勤務し,妊産婦と新生児に関する各種WHOガイドライン作成に携わった。18年より現職。専門は国際保健。『WHO推奨 ポジティブな出産体験のための分娩期ケア』(医学書院)の編集にかかわる。(写真撮影/河合蘭)
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。