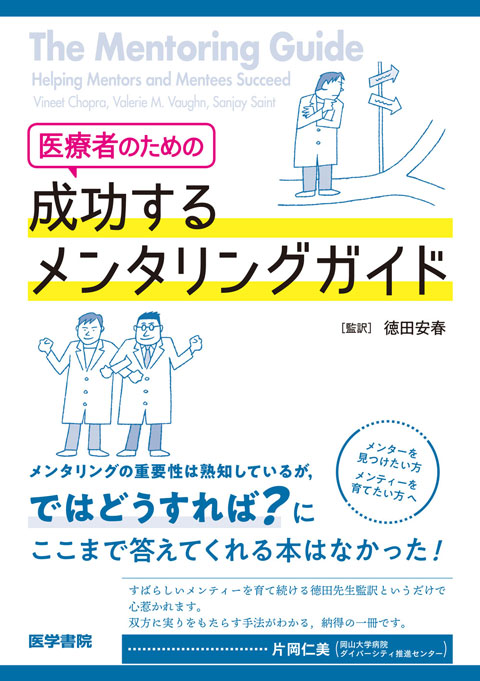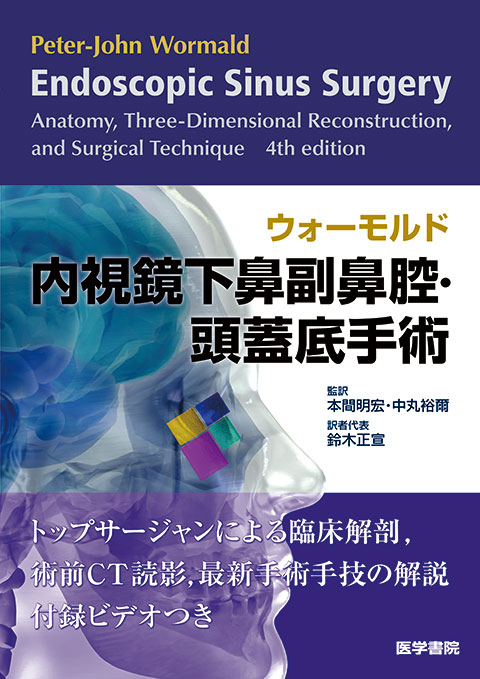MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.12.07
《評者》志水 太郎獨協医大教授・総合診療医学
徳田安春&オール沖縄Presents,メンタリングの金字塔
まず,本書評を書かせていただくにあたって触れるべきこと。それは何をかくそう,評者(私)の最強メンターは本書の監訳者,徳田安春先生であるということである。徳田先生はどのようなメンターであったか? それを語るには,本書で個人的に最重要章と感じる,Chapter 3をお読みいただきたい。同章の骨格となるポイント,すなわち「メンターでなく,メンティー自身の成長に有益なタスクを与えよ」「動き続けよ」「難しい対話に備えよ」「いつでもつながれるようにする」(詳細は本書をお読みください)などは,まさに往年の徳田(メンター)―志水(メンティー)の関係そのものを言語化したものである。徳田先生と出会ったのは2005年11月,東京都立墨東病院での徳田先生の講演で,自分はそのシャープかつ俯瞰的な指導に魅了され,徳田先生の行く先々に追随し,オンライン・オフライン問わず,バスの中で,飛行機の隣で,新幹線の往復で,フレッシュひたちの中で,貴重な教えをスポンジのように学んだ。宝物のような時間だった。それは自分が米国に滞在した中でも後も継続したのである。「ジャーナルではレビューとエディトリアルを毎週フォローしてください」「私が診ます,といえば丸く収まるのです」「スピードと集中がカギです」など枚挙にいとまがないが,全てメンティーの自分がメンターとして拡散すべき“グレート・アントニオ”徳田の教えである。
いきなりChapter 3にフォーカスしたが,ここで本書の構成を紹介したい。本書は全10 chapterからなり,メンターへ(Chapter 1-3),メンティーへ(Chap ter 4-7),そしてメンター&メンティーへ(Chapter 8-10),という3部構成に分けられている(さらに巻末に約50ページにわたるメンタリングの参考文献の数々の紹介もうれしい)。とはいえ,メンターはメンティーの章を,またメンティーはメンターの章を読むことで,相手の立場をおもんぱかることができる。その結果,全ての読者は本書の全ページから重要な学びを得られるだろう。
本書の優れたところは他にもたくさんある。ダイバーシティ(Chapter 9)やミレニアル世代(Chapter 8)にも配慮しているところは秀逸である。特に,世代間の違いでは,例えば評者が心酔する昭和プロレス式「プッシュアップとスクワット」でナンボ,はミレニアルには地雷(というかアウト)である。このような時代のギャップへの配慮も大事である。徳田先生の「年齢を重ねると時代にマッチした戦略を立案することが難しくなる」(p.96)はメンターにとって心すべき金言である。だからこそ,メンターとメンティーのお互いの振り返り(Chapter 10)と柔軟な心が必要ということになる。
序文にもある通り,メンタリングの関係は相互的であり,メンターはメンティーによって知の拡散を実現し,メンティーはメンターにより知へのガイドを得られる。しかしそれがWin-Win,Give and Takeのようなドライな関係で終わらないのは,本書では明言して強調こそされてはいないものの,その文底で語られる,師弟愛ともいうべき互いの信頼関係である。そう,究極的にはメンタリングとは愛だと思う。
本書はメンタリングという難しくとっつきにくいテーマを,米国を代表するSaint/Chopraという臨床教育2大巨頭がわかりやすく解説し,それが日本代表の臨床教育マイスター徳田安春&沖縄アソシエイツの手によって日本のあらゆる層にコモディティ化されたという,希代の名著ともいえる。2020年,いや,2020年代を通じたMust Buyといえるだろう。
《評者》寺坂 俊介社会医療法人柏葉会柏葉脳神経外科病院理事長・院長
頭蓋底手術に携わる医師に必読の手術書
私は脳神経外科医として顕微鏡手術を学び,現在も手術を継続している。北大脳神経外科で初めて内視鏡手術が行われたのは,下垂体腺腫の手術だったと記憶している。私の部下が初めて下垂体腺腫に対して内視鏡手術を行った時のことは今でも鮮明に覚えている。私は術衣に着替え顕微鏡と共に手術室内に待機した。手術が難航した際には顕微鏡手術に切り替えるつもりだったからだ。当時の内視鏡は今よりも解像度が低く,内視鏡手術用の道具も限られていた。顕微鏡手術の倍の手術時間と出血量を要したが,私は一度も手術を替わろうとは思わなかった。自分がどんなに工夫しても顕微鏡下手術では見えなかった海綿静脈洞壁や鞍上部がモニターに映し出されていたからである。
ウォーモルド先生が執筆された本書には内視鏡下手術の利点,特に優れた可視性を最大に生かした手術手技が網羅され,しかもその一つひとつが細部に至るまでしっかりと書かれている。例えば内視鏡下髄液漏閉鎖術の章で紹介されるバスプラグ法などは脂肪の採取の部位,糸のかけ方,使用する道具,術後の管理,腰椎ドレーンを入れた場合はその排液量までが細かく記載されている。「賛否が分かれるかもしれないが」とただし書きをつけた上で,ウォーモルド先生の手技が紹介されている。本書を読んでいると,このような細かな手術手技や術後管理を学びにかつてはお金と時間を費やして海外にまで行ったのに,と思われる諸兄も多いはずである。
1990年代,本邦の頭蓋底手術は世界をリードしていた。しかし当時の日本には手術に必要な外科解剖を学ぶ方法が少なかった。われわれは海外のカダバーラボに在籍して毎日微小外科解剖の勉強をし,来るべき手術に備えて解剖学的指標をアナログ写真に残していった。本書の特筆すべき点は,献体を使った高画質の微小外科解剖写真がふんだんに使用されていることである。例えば頭蓋底手術では手術の手順に沿って,蝶形骨洞,海綿静脈洞や斜台の解剖学的指標が明確に示され,それらはCT写真やナビゲーション画像と連動してわれわれを安全な手術へ導いてくれている。スマートフォンでQRコードを読めば動画で手術道具の使い方や止血方法が解説される。微小外科解剖が安全な手術を行うためにいかに重要であるかを熟知した外科医の書いた手術書である。高画質の頭蓋底微小外科解剖が提示されているという点...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。