MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.03.30
Medical Library 書評・新刊案内
BRAIN and NERVE―神経研究の進歩
2019年11月号(増大号)(Vol.71 No.11)
増大特集 ALS2019
《評者》糸山 泰人(国際医療福祉大名誉教授)
ALS患者さんが待望の新薬を手にする日まで
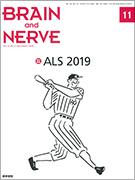 この特集号が発行された2019年からちょうど150年前の1869年に,Charcotらによって筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)の報告がなされたわけであるが,その当時からALSは神経難病のシンボル的存在であり,「病因につながる手掛かりをまったく残さない難攻不落の難病」の印象を長い間持たれてきた。しかし,このたび『BRAIN and NERVE』誌の増大特集「ALS 2019」を読んだところ,本特集には新たな病因・病態論が多く紹介されているとともに,いくつかの有望な治療薬開発研究が示されていて,これまで抱いていた「難攻不落の神経難病ALS」の見方を変えざるを得なくなった。
この特集号が発行された2019年からちょうど150年前の1869年に,Charcotらによって筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)の報告がなされたわけであるが,その当時からALSは神経難病のシンボル的存在であり,「病因につながる手掛かりをまったく残さない難攻不落の難病」の印象を長い間持たれてきた。しかし,このたび『BRAIN and NERVE』誌の増大特集「ALS 2019」を読んだところ,本特集には新たな病因・病態論が多く紹介されているとともに,いくつかの有望な治療薬開発研究が示されていて,これまで抱いていた「難攻不落の神経難病ALS」の見方を変えざるを得なくなった。
有望な病因論の多くはALSの分子病態の解明研究の進歩によるものである。1993年に家族性のALSの原因遺伝子SOD1が発見されたのに端を発して,TARDBP,FUS,OPTNそれにC9orf72など,いまでは20を超える家族性ALSの原因遺伝子が明らかにされてきている。SOD1を例に挙げるまでもなく,新たな病因遺伝子の発見はその動物モデルなどの作製を通して,病態に関与するであろうミトコンドリア障害,小胞体ストレス,酸化ストレス,軸索内輸送障害,グルタミン酸毒性,それに神経栄養因子の欠如などさまざまな神経細胞死の経路が病態機序として明らかにされてきた。中でも家族性ALS病因遺伝子の一つのTARDBPはTDP-43をコードするものであって,そのTDP-43はALSの大部分を占める孤発性ALSの運動ニューロンの細胞質内封入体の主要成分であり,ALSの神経病理学的指標となっている。今後,その細胞質内封入体形成,分解機構,RNA代謝機構および自己調節機構がALSの病態機序解明研究の中心となるものと考えられる。
本誌を読む中で,こうしたALSの病因・病態論の進歩とともに感心させられたのはALSの治療薬開発研究である。現在,ALSの治療薬として国内で認可されているのは,リルゾールおよびエダラボンのみである。いずれもALSの進行を止めることはできず,またその効果は限定的なものであり,とても患者さんが満足できるものではない。かと言って,ALSのような難病や稀少疾患に対する新規治療薬の開発研究は多くの困難が付きまとい,時に「研究者にとって死の谷」と表現されることもある。しかし,本邦ではその困難を乗り越えんとして5つもの治験,しかもそのほとんどが医師主導の治験が進行中であり,本特集ではそのうち4試験が詳しく紹介されている。それらの候補薬を列挙すると,①臨床経験的な有用性を参考に開発されている高用量メコバラミン,②新たな神経栄養因子としての効果を持つ肝細胞増殖因子(hepatocyte growth factor:HGF),③AMPA受容体を介したCa2+流入を抑制し神経細胞死を抑えるペランパネル,④ドラッグ・リポジショニングとiPS細胞の技術から開発されたロピニロール塩酸塩などである。これらの治験が順調に進むとともに,でき得れば画期的なデータが出ることを祈るが,事はそう簡単ではないと考える。しかし,このような科学的な治験を一歩一歩重ねていくことが,必ずや「ALS患者さんが待望の新薬を手にするその日」に近づいていく道であることを信じるものである。


「おしりの病気」アトラス[Web動画付]
見逃してはならない直腸肛門部疾患
稲次 直樹 著
《評者》板橋 道朗(東京女子医大消化器病センター教授・消化器外科学)
診察室や内視鏡室に置いて活用すべき肛門部疾患のバイブル
 久しぶりに若手医師へ自腹での購入をお薦めしたい本に出合えました。まさに感動です。『「おしりの病気」アトラス』は,肛門部疾患のバイブルといえます。
久しぶりに若手医師へ自腹での購入をお薦めしたい本に出合えました。まさに感動です。『「おしりの病気」アトラス』は,肛門部疾患のバイブルといえます。
非常に丁寧に読者の必要とするものは何かを考え抜き,緻密な計画をもって作られています。まさに,直腸肛門疾患に対する稲次直樹先生の長年の真摯な診療そのものが反映された本といえます。
何より,質の良い疾患画像やイラストが1200点以上,非常に豊富に掲載され,驚いたことにスマートフォンでWebにアクセスすると,写真をみて取り込むことができます。もちろんPCにもダウンロード可能です(註)。
肛門科でなければみることが少ない疾患も写真入りで惜しみなく紹介されています。一例として挙げるならば,「温水洗浄便座症候群」をご存じでしょうか? 「温水洗浄便座症候群」の患者さんの特徴的なおしりの所見が写真入りで紹介されています。肛門科でなければみることが少ないであろう疾患です。写真とともに疾患の治療法まで解説され,さらにWeb動画配信のQRコードが盛りだくさんにちりば...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
