地域に根差した施策実行に向けて
寄稿 磯部 光章,木原 康樹,宮本 享
2020.01.06
【寄稿】
地域に根差した施策実行に向けて
脳卒中・循環器病対策は都道府県ごとの計画策定が求められる。基本法の施行によって,診療に携わる医療者や患者の暮らしはどう変わるのか。地域の医療資源の有効利用,地域包括ケアを見据えた病院・在宅の垂直連携,データに基づく2次医療圏ごとの施設配置についてそれぞれ,3氏が展望を紹介する。基本法をよりどころに社会システムの整備を
磯部 光章(榊原記念病院 院長)
わが国は少子,高齢,多死という深刻な社会問題を抱えている。高齢化で増加するのは心血管疾患であり,今後患者のケア・介護のニーズが増え,死亡者の増加が病院の機能を圧迫する。何より求められるのは心血管疾患の0次予防,1次予防と適切な急性期治療の普及・均てん化であり,疾患発症後の2次予防,さらにフレイル,介護を未然に防ぐことによる健康寿命の延伸である。個人がより幸福な老後を送ることは健全な社会の構築につながる。疾病予防による医療費の抑制も重要な課題である。その意味で2019年12月に施行された脳卒中・循環器病対策基本法に期待するところは大きい。この法律は,今後ますます増加すると考えられる循環器疾患の診療提供体制を大きく変える力を持つからだ。
対策で最も重要となるのが予防である。循環器疾患の予防が日常生活に浸透するよう学校教育の充実や市民啓発が求められる。医師や医療機関にはこれまで手の届かなかった重要な活動と言える。現在行われている特定健診は必ずしも心血管疾患の早期発見につながるものではない。例えばBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)の測定などを健診に組み込んでいけば,心不全や心房細動の早期発見につながるであろう。
救急診療体制についても診療の内容がより高度化し,また地域の交通事情,人口分布,医療資源が大きく変化しつつある現在,より効率のよいシステムに柔軟に対応することが求められる。循環器疾患は超急性期の早期治療が極めて有効であることから,がん診療のような診療施設集約化はなじまないと思われるが,限られた医療資源を有効活用するために,地域の実情に合った拠点化と高度診療施設の重点化が必要ではないだろうか。
多死社会を迎え,高度急性期治療を要する大動脈解離などの急性期症例と,積極的侵襲的治療になじまない超高齢者の急性心不全症例が秩序なく高度急性期病院に収容されている現況について,医療資源をより適切に有効利用する方向で改善する必要があろう。心血管疾患に罹患した患者が社会生活を取り戻し,再入院を予防して健康な生活を維持することに最も有効なのは,心臓リハビリテーションなどの運動療法と多職種による総合的な介入である。現在進められている地域包括ケアにこのようなケアが組み込まれるよう社会システムの整備を行う必要がある。
さらに心血管疾患の実態調査や登録事業は疾病対策に不可欠であり,また研究の発展による新薬や新規治療の開発にも期待は大きい。これらの対策は国民が一丸となって進めるべき課題であり,法律はそれを支えるよりどころになると期待される。この法律が,明るく健全な社会構築に寄与する一助となることを祈念するものである。
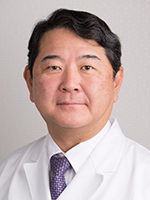 いそべ・みつあき
いそべ・みつあき
1978年東大医学部卒。2001年東京医歯大大学院循環制御内科学/循環器内科教授,17年より現職。日本心不全学会前理事長。東京医歯大名誉教授。厚労省の臓器移植委員会委員長,同省厚生科学審議会委員などを務める。脳卒中・循環器病対策基本法の立法化に向け活動。
在宅支援を実現,広島県心臓いきいき推進事業
木原 康樹(広島大学大学院医系科学研究科循環器内科学 教授)
医療計画の5疾病・5事業などの基盤整備と対策の推進により,循環器疾患の治療成績は格段に向上し,急性心筋梗塞を代表とする循環器疾患への拠点施設整備は完了したかに思われる。一方,急性期患者の心血行動態安定や生命危機の回避に伴って,それ以降のプロセスは回復期施設・病棟あるいは地域包括ケア施設・病棟に移行せざる...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


