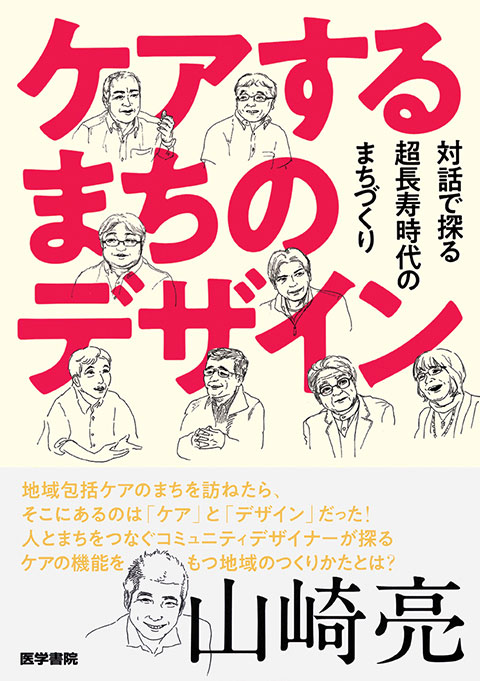「ケアするまち」をつくる(山崎亮)
インタビュー
2019.03.25
【interview】
「ケアするまち」をつくる
| |
|
地域包括ケアが推進される中,医療者にも地域での活躍やまちづくりへの参画が期待されている。地域に活躍の場を広げるに当たり知っておきたいのが,「コミュニティデザイン」という手法だ。
コミュニティデザイナーの草分け的存在として,さまざまな地域で「人と人のつながり」を生み出してきた山崎亮氏は,最新刊『ケアするまちのデザイン――対話で探る超長寿時代のまちづくり』(医学書院)で,まちづくりにおけるケアとデザインの協働の重要性を語っている。本書に込めた思いとともに,地域包括ケアに活かせるコミュニティデザインの視点を尋ねた。
――コミュニティデザイナーとは,どのようなお仕事ですか。
山崎 例えば地域に公園や図書館などの公共施設をつくる際,住民の意見を設計に取り入れるための工夫を考えます。具体的にはワークショップを開催して住民を集め,どのような施設をつくりたいか,施設で何をしたいかのアイデアを出し合ってもらいます。
アウトプットの一つは公園や図書館の設計図です。しかしそれ以上に,何度も話し合いを重ねることで生まれる,住民同士のつながりにこそ価値があると考えています。でき上がった施設で住民たちが活動し,さらに新たな人々を「ようこそ」と迎えてくれる。このような状態をつくりたいのです。
――形あるもの以外にまで,デザインの概念を広げているのですね。
山崎 studio-Lでは,公共施設の設計の他,自治体の総合計画をつくりたい,健康な人も集える病院にしたい,お寺を活性化したいなど,さまざまな依頼を受けます。しかし基本的には,目に見えるものはつくりません。「こうすればいいですよ」と具体的なアイデアを提示することもしません。
つくるのは住民や関係者たちのつながりです。地域の人たちと一緒に課題を見つけ,地域の人たち自身が解決するプロセスを手助けする。これが,コミュニティデザイナーの仕事なのです。
地域包括ケア実現の鍵は人と人のつながり
――そもそもコミュニティとは,どのようなものでしょうか。
山崎 現在,コミュニティという言葉には2つの意味が混ざってしまっています。1つ目の意味は,共通の関心や目的のために集まった人為的な集団のことです。わかりやすい例として,Facebookやmixiなど,SNSの“コミュニティ”がありますね。実はこちらには,アソシエーションという言葉を当てるほうが適切です。
本来のコミュニティとは,同じ地域に居住する人々や同じ文化を有する人々などの共同体を意味します。関心や目的によらない点で,アソシエーションよりも広い概念です。
――限定的な意味であるアソシエーションも含めて,コミュニティと呼ばれているのですね。
山崎 アソシエーションとコミュニティの関係性は,よくビールに例えられます。ジョッキが地域なら,ビールの泡がアソシエーションで,ジョッキを満たす液体がコミュニティです。
コミュニティ(=ビールの液体部分)は,もともとデザインできない,つまり人為的にはつくれないと考えられてきました。しかし,ビールの泡も液体も含めた全体をコミュニティと呼んでいる以上,私は両方へのアプローチが必要だと考えています。つまり,特定のテーマへの関心を持つ集団(=アソシエーション)を対象とするだけでなく,もともとは関心のない人にも参加してもらえるよう,工夫が必要です。
これは,特に地域包括ケアでは重要な視点です。医療や福祉の専門職だけでは,地域の課題のごく一部しか解決できないからです。地域包括ケアは専門職連携と住民参加の両方がそろって,初めて実現するものだと思います。
――コミュニティデザインによって,一般の住民にもケアに参加してもらいたいとお考えなのでしょうか。
山崎 はい。専門職連携も住民参加も,突き詰めれば人と人のつながりです。地域包括ケアの実現に向けて,コミュニ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。