MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2017.04.24
Medical Library 書評・新刊案内
一歩先のCOPDケア
さあ始めよう,患者のための集学的アプローチ
河内 文雄,巽 浩一郎,長谷川 智子 編
《評 者》亀井 智子(聖路加国際大大学院教授・老年看護学)
時代の「一歩先」を追求する,患者ファーストが貫かれたチーム医療の実用書
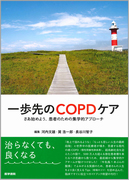 医療や看護の領域で,「一歩先」とはどのくらい先を示しているのだろうか――。評者は慢性呼吸不全患者の在宅ケアに長く取り組んできた者として,この標題から強いメッセージを感じながら,期待を持って本書のページを開いた。
医療や看護の領域で,「一歩先」とはどのくらい先を示しているのだろうか――。評者は慢性呼吸不全患者の在宅ケアに長く取り組んできた者として,この標題から強いメッセージを感じながら,期待を持って本書のページを開いた。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は非可逆的・進行性の疾患で,“地上で溺れるような”症状を伴う。そのような患者の苦しみを目の前にしたとき,患者にそのライフヒストリーを取り入れた人生の意味付けを促進しながらスピリチュアルペインを緩和し,吸入薬剤の種類も患者に合ったものと,それに適切な使用方法を患者と共に見つけることや,栄養の摂取方法の見直しに至るまで,まさに多職種による集学的アプローチが不可欠となる。
本書のユニークさとして,患者の“生活の場”を念頭に置き,家庭医(本書では「町医者」),呼吸器専門医,専門/認定看護師,理学療法士などによって,それぞれ外来,在宅,入院という患者の生活場面,言い換えるとケアを提供する場に沿っての内容構成がなされている点がある。これら別個の専門職による「団体戦のみの精神的総合格闘技」(p.27)と本書で表現されるCOPDのチーム医療の神髄が,ユニークでわかりやすい表現を随所に交えながら記されている。例えば評者の目を引いたものの一つに,慢性呼吸器疾患看護認定看護師の上田真弓さんが,患者に生体の難解なしくみを説明するため,肺胞でのガス交換を一目でイメージできるようにと作成されたイラストがある。患者教育はCOPDの包括的リハビリテーションの中でも重視されているが,労作性呼吸困難を経験している患者の肺の奥で何が起こっているのかをわかりやすく説明することは現場ではなかなか難しい。本書では,いかに患者自身が理解できるように説明するか,患者をケアの中心に置くかという「患者ファースト」の視点が貫かれているように思う。
また,COPDの診断にまつわる章では,検査値という数値だけが診断基準とされることへの警鐘が医師サイドから鳴らされている(p.36)。一つの定規による一律の長さでの「線引き」だけでなく,患者の自覚症状こそ重視するという医療の本分の「復権」について,ここでは,「穴のあいた定規」も時として必要であると説かれていることが,評者自身も忘れかけていた“呼吸の状態を一番...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


