暮らしを支えるがん対策とは(川越正平,小松浩子,天野慎介)
寄稿
2017.01.02
【寄稿】
暮らしを支えるがん対策とは
がん医療にかかわる人々は患者・家族・医療者と多岐にわたる。一人ひとりのニーズに即したがん医療の実現に向け,これからのがん対策には何が求められ,どう行動に移せばよいのだろうか。在宅医療・がん看護・患者団体,それぞれの立場から見据える「次の10年」とは――。
2027年がん診療連携の未来予想図
川越正平(あおぞら診療所院長)
がんに代表される専門性の高い疾患を有する患者に対して,生活の視点に基づく併存疾病の管理や療養生活に対する指導を行う医療の必要性が,2027年の今では広く認識されるようになった。化学療法を開始する時点で患者が居住する地域の診療所医師を副主治医(かかりつけ医)として選定する「二人主治医制」が診療報酬で評価されるようになり,医療現場にすっかり定着している。神経難病や心不全をはじめとした臓器不全で入院歴のある患者についても,副主治医を構えるようになった結果,再入院率が低下した。
かかりつけ医は,糖尿病や慢性腎臓病など,生活や環境に関するアドバイスが必要不可欠な併存疾患について,その管理を第一に担当する。また,発熱等の変化があった場合,患者はまず副主治医の診療所を受診する。上気道炎等の軽微な急性疾患なのか,肺炎等の重篤な合併症なのか,化学療法や腫瘍熱等がんに関連する病態なのかについて,大まかな見極めまでを副主治医が担当する。そして,必要に応じて主治医であるがん治療医に連絡し,速やかな対応につなげる。
さらに副主治医は,主治医の依頼に基づいてがん診療の一翼を担う。例えば,化学療法から2週間後のデータをチェックするための採血を副主治医診療所が実施し,その検査結果を,2017年以降に新たに整備された「地域電子伝言板」にアップする。外来の合間に採血データを適宜閲覧することによって,患者が病院に通院することなく,病院主治医は「白血球数が減少していたから次の化学療法を1週間延期する」という判断ができる。患者には保険証と同じサイズのカードが発行されている。そこにあるQRコードの提示をもって医療機関がクラウドにアクセスできるこの連携システムは,廉価で簡便であり,ICTが苦手な医療従事者にとっても使いやすい。
過去に行った地域連携の実績を全てのがん診療連携拠点病院が登録し,それらの情報を集約する拠点病院間の連携体制も整ったため,地域の緩和ケア提供状況の把握が格段に向上した。例えば,ある地域で過去に頭頸部がん患者を担当した経験のある診療所の有無や,その経験値がわかることは,連携先を選定する際に大いに役立つ。
そんなある日,化学療法を開始することになったある進行がんの患者について,地域連携カンファレンスが行われることになった。MSWは,地域の医療資源,そして家族や住環境が有する問題点などについてレビューした。
この患者が住む地域の場合,日常生活圏域にはがん診療経験を有し在宅医療に取り組む診療所である「がん診療連携応需医療機関」(地域密着型と広域専門型がある)は存在しないが,幸い隣接している圏域に2つの「地域密着型診療所」があり,隣の市には広域在宅医療に取り組む在宅専門のクリニックが1つあるとのことだった。
この患者に対して,主治医であるがん治療医が病状説明の場を設けた。その席上で先の3つの医療機関が提示され,患者は1つの診療所を副主治医として選んだ。そこで主治医は,「その先生なら知っているから,今から電話してお願いしましょう」と,患者の目の前でその診療所に電話をかけ,診断の詳細やこれまでの経過,治療方針,依頼したい診療分担の内容について,手短に伝えた。この演出の効果は絶大であり,不安げだった患者の顔はみるみる安堵の表情へと変わっていった。ちなみに,この診療所医師と病院治療医は,以前に一度電話で話したことがあるだけだった。
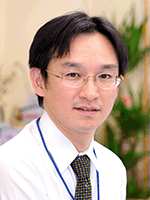 かわごえ・しょうへい
かわごえ・しょうへい
1991年東医歯大卒。虎の門病院内科レジデント,同院血液内科医員を経て,99年在宅医療を中心に行う「あおぞら診療所」を千葉県松戸市に開設,2004年より現職。地域のがん患者の在宅緩和ケアも担う。
社会で創るがんサバイバーシップケア
小松浩子(慶應義塾大学看護医療学部教授)
がん医療の進歩によって命が救われ,社会の中で生活しながらがんの治療およびフォローアップを受ける「がんサバイバー」が増えている。しかし,サバイバーにとっては治癒や健康状態の回復が全て保証されるわけではない。多くは疾病そのものの他に,副作用や障害,QOLの低下を経験している。直面する問題は多様であり,うつ,再発に対する恐怖,性機能障害,対人関係性の問題,勤務状況,社会活動,家事能力の制限,収入源などに関する心理・社会的な影響をもたらす。米国では既に,米国医学研究所(Institute of Medicine)からサバイバーシップケアの4つの本質的要素に関する勧告が出され,国を挙げてサバイバーシップケアを推進している。
では,翻ってわが国はどうだろうか。サバイバーの実...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


