MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2015.09.21
Medical Library 書評・新刊案内
崎山 弘,本田 雅敬 編
長谷川 行洋,広部 誠一,三浦 大 編集協力
《評 者》前野 哲博(筑波大病院総合診療グループ長)
経験豊富な小児科医の思考プロセスを追体験できる一冊
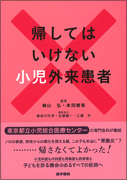 小児診療について,全国全ての地域・時間帯を小児科医だけでカバーすることは不可能であり,実際には救急医や総合診療医などの「非小児科医」が小児診療に携わる機会は多い。特に総合診療医には「地域を診る医師」としてあらゆる年代層の診療をカバーすることが期待されており,実際,2017年度から新設される総合診療専門医の研修プログラムにおいても,小児科は内科,救急科とともに必修の研修科目として位置付けられている。
小児診療について,全国全ての地域・時間帯を小児科医だけでカバーすることは不可能であり,実際には救急医や総合診療医などの「非小児科医」が小児診療に携わる機会は多い。特に総合診療医には「地域を診る医師」としてあらゆる年代層の診療をカバーすることが期待されており,実際,2017年度から新設される総合診療専門医の研修プログラムにおいても,小児科は内科,救急科とともに必修の研修科目として位置付けられている。
このような小児診療にかかわる非小児科医にとって,最低限果たさなければいけない役割は何だろうか? さまざまな意見があるかもしれないが,最終的には「帰してはいけない患者を帰さない」ことに尽きるのではないだろうか。たとえ自分一人で診断を確定したり,治療を完結したりできなくても,「何かおかしい」と認識できれば,すぐに小児科専門医に相談して適切な診療につなぐことができるからだ。
このたび,そんな非小児科医にとっても最適の本が発刊された。タイトルはズバリ『帰してはいけない小児外来患者』である。
本書は第1章の総論と第2章のケースブックから構成されている。
第1章では,筆者の豊富な診療経験と,臨床推論の理論的背景をもとに,一見軽症に見える「死の合図に該当」する疾患をうっかり見逃してしまうプロセス(=見逃さないためのポイント)が症例や図を交えてわかりやすく述べられている。その内容は小児診療のみならず,全ての診療に通じるものであり,ぜひ一読をお勧めしたい。
第2章はケースブックである。ここに提示されている40の症例は,ほとんどはありふれた訴えから始まる。ケースの紹介に続いて,外来担当医の考えた鑑別診断やそれに至る思考回路が示される。その一連のプロセスの中で,危険な疾患が潜んでいることに気付いたポイントが「転機」として示され,さらに「教訓」としてその解説,そして「最終診断」「TIPS」の順に記載されている。
ちなみに,同じ医学書院からは2012年に,主に成人患者を対象とした『帰してはいけない外来患者』が発刊されている。私もその編集にかかわったが,両書とも症例の経過と医師の思考回路を通して危険な疾患を見逃さないためのポイントを解説するコンセプトは同じである。読者は,思わず見逃しそうになった経緯から,どんでん返し! で最終診断がつく経過まで,臨場感をもって学ぶことができるため,非常に興味深く,また記憶に残りやすい構成になっている。
一般的な教科書では,知識を学ぶことはできても,経験豊富な小児科医の「頭の中」,つまり思考プロセスを学ぶことは難しい。それを追体験できる本書は,小児科研修中の医師はもちろん,小児診療にかかわる全ての人にお薦めの一冊である。
A5・頁224 定価:本体3,600円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02138-8


野村 総一郎,中村 純,青木 省三,朝田 隆,水野 雅文 シリーズ編集
中村 純 編
《評 者》秋山 剛(NTT東日本関東病院精神神経科部長)
最高水準,かつわかりやすく述べられたガイドブック
各分野の最も優れた臨床医が執筆され,症例→解説という流れもわかりやすい。「依頼患者の診方と対応」「精神症状・心理的問題が生じやすい身体疾患とその病態」「精神症状・心理的問題が生じやすい身体疾患治療薬」という構成は包括的であり,病態についてのMedicalな説明,治療薬の解説が現在の最高水準で,かつわかりやすく述べられている。
ただ,本書は,「他科のスタッフの対応能力を高めるようにどう支援するか」「リエゾン精神看護専門看護師(Certified Nurse Specialist;CNS)の働き」「精神科リエゾンチーム(LT)でのスタッフの協働」などについては,記述が乏しい。これは,他科への対応・支援をLTが行うという体制が,まだ十分に確立していないためであろう。
しかし今後は,他科の患者に精神症状が生じた場合の対応は,LTを通して行う流れになると思われる。LTでは,患者や家族に対する支援は主にCNS,臨床心理士などが担当し,他科の看護師へはCNSが支援・コンサルテーションを行い,他科の医師へはLTの医師が支援を行うという協働体制が基本となろう。他科で困っている関係者が複数いる場合には,LTの支援も複合的になるので,支援の方向性が一貫するように,LTとしてケースカンファレンスを行う必要がある。
他科の関係者の中で,看護師は患者の身近にいて,精神症状を一番正確に把握し,ケアの責任を負い,困難を感じやすい立場にある。一方,看護師は集団としてケアを行うために,看護師が獲得したスキルは集団として受け継がれる傾向がある。精神症状へのケアに対するモチベーションの高さ,スキル伝承の可能性を考えると,他科の対応能力を高めるには,看護師のスキルアップを図ることが最も効率的であると考えられる。CNSによる他科看護師への研修,コンサルテーションを精神科医がうまくバックアップすることが重要である。
本書で述べられている個別の問題について筆者の経験を述べると,患者の怒りによるトラブルに前向きに対応するためには,「診療効果の限界」「他の患者への不利...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

